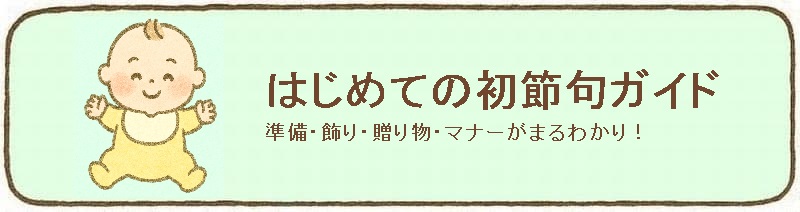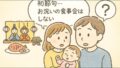初節句のお祝いを贈るとき、のし袋や祝儀袋の書き方に悩む方は多いものです。
特に
「表書きはどうする?」
「名前は連名でいいの?」
「金額の書き方にルールはあるの?」
といった疑問は、いざ準備しようと思ってから浮かぶことがほとんどです。
このページでは、初節句のお祝い袋に関する正しい書き方やマナーを、名前の書き方から金額の記入方法まで、やさしく丁寧に解説しています。
基本的なルールさえ押さえておけば、相手に失礼のない、気持ちのこもった贈り方ができますよ。
誰でも迷わず準備できるように、実例も交えながらわかりやすくまとめているので、初めての方も安心して参考にしてみてくださいね。
初節句のお祝い袋とは?まず知っておきたい基本
初節句のお祝いとは?贈る時期と金額相場
初節句とは、赤ちゃんが生まれてから初めて迎える節句のことで、男の子なら5月5日の端午の節句、女の子なら3月3日の桃の節句を指します。
それぞれの節句には、子どもの健やかな成長や無事を願う意味が込められており、日本では昔から大切にされてきた伝統行事なんです。
初節句では、鯉のぼりやひな人形を飾ったり、家族そろって食事をしたりして、赤ちゃんの成長をみんなでお祝いするのが一般的です。
お祝いを贈るタイミングは、節句当日だけでなく、その前後で予定を合わせることも多く、家庭によっては祖父母や親戚を招いて、ちょっとしたお祝いの会を開くケースもあります。
地域によって風習に違いはありますが、共通しているのは「赤ちゃんを思って気持ちを贈ること」が何より大切だということです。
お祝い金の相場については、祖父母やごく近い親族であれば1万円~3万円ほどが一般的で、節句の飾りなどを一緒に贈ることもあります。
それに対して、いとこやおじおば、友人などの場合は、3,000円~1万円程度が目安です。
とはいえ、金額に正解があるわけではなく、あくまで気持ちを表すものなので、無理のない範囲で包むようにするといいですよ。
のし袋と祝儀袋、どちらを使う?
「のし袋」と「祝儀袋」は似ていますが、基本的にはどちらもお祝い金を包むための袋です。
違いとしては、「祝儀袋」は水引や飾りが付いているものが多く、少しフォーマルな印象になります。
一方、「のし袋」はやや簡素なデザインのものもあり、カジュアルなお祝いごとに使われることもあります。
初節句のような家族向けのお祝いには、蝶結び(何度繰り返しても良いお祝いごとに使う)の紅白水引がついた祝儀袋を選ぶと、失礼がなく安心です。
最近は文房具店やスーパーでも「初節句用」と表示された祝儀袋が販売されているので、それを選ぶのもおすすめです。
表書き欄が印刷されているものもあるので、筆に自信がない場合にも便利ですよ。
初節句のお祝い袋の書き方マナー
表書きの書き方:「御祝」or「初節句御祝」?
表書きには「御祝」「初節句御祝」「桃の節句御祝」「端午の節句御祝」などがありますが、もっとも一般的で無難なのは「御祝」です。
「御祝」と書くことで、さまざまなお祝い事に対応できるため、迷ったときにも安心して使える表現なんですね。
もう少し具体的に書きたい場合には、「初節句御祝」とすると、相手にも気持ちがより伝わりやすくなります。
たとえば、女の子には「桃の節句御祝」、男の子には「端午の節句御祝」と書くこともあります。
ですが、これは少し格式ばった印象になることもあるので、親しい間柄では「初節句御祝」がちょうどよいバランスです。
名前はフルネーム?連名はどうする?
表書きの下に記載する名前は、1人ならフルネームで、楷書を使って丁寧に書くことが大切です。
手書きに自信がない場合でも、ゆっくりと丁寧に書くことで気持ちはしっかり伝わります。
夫婦で贈る場合は、右から夫→妻の順で書き、その下や横に子どもの名前を加えるのも一般的です。
また、家族全員でお祝いする場合は、全員の名前を並べてもかまいません。
でも、名前が多くなるとバランスが取りにくくなるため、代表者の名前の右横に「他一同」や「○○家一同」と添えるとすっきりまとまります。
会社やグループなど複数人で贈るときも、この方法がよく使われます。
金額の中袋の書き方と注意点
中袋(中包み)は、お金を包む内側の袋で、表面には「金○○円」、裏面には差出人の名前と住所を記入するのが基本です。
金額の書き方には少しルールがあり、「金壱万円」「金五千円」など旧字体を使うのが正式とされています。
でも最近では「1万円」「5,000円」などの現代数字でも問題ないケースが増えてきました。
地域や相手との関係性によっては、旧字体にこだわらなくてもマナー違反にはならないことが多いです。
ただし、記入の際は濃い黒のインクで丁寧に書きましょう。
また、中袋のないタイプの祝儀袋の場合は、外袋の裏面に直接記載することになります。
そのときも、表面に表書き、裏面に金額と名前・住所を書くようにしておくと、受け取る側も誰からか分かりやすく、後の内祝いの準備などもスムーズに進められますよ。
書くときの道具とNGマナー
筆ペン・ボールペン・サインペンの使い分け
お祝い袋の文字を書くときには、相手への敬意を表すためにも、使う筆記具を意識することが大切です。
もっとも一般的でおすすめなのは黒の筆ペンで、文字にやわらかさと格式が加わるため、フォーマルなお祝いの雰囲気にぴったりです。
特に毛筆タイプの筆ペンを使うと、より丁寧で温かみのある印象を与えられます。
もし筆ペンに慣れていない、文字がうまく書けないという方は、濃い黒インクのサインペンを使ってみると良いでしょう。
筆ペンよりも扱いやすく、それでも見た目はしっかりと整います。
ただし、インクがにじみやすい紙もあるので、筆記前に試し書きをしておくと安心です。
一方、ボールペンは手軽で普段使いに便利ですが、お祝いの場では少しカジュアルすぎる印象になるため、できれば避けた方が無難です。
特に青や赤インクは失礼にあたるため、使用は控えるようにしましょう。
どうしてもボールペンしか使えない場合でも、黒の油性インクでしっかりと書くようにしてくださいね。
間違えた場合の修正方法と避けたい書き方
お祝い袋の文字を書いているときに、うっかり漢字や金額を間違えてしまうこともありますよね。
そんなときでも、修正液や修正テープで直すのはNG。
こうした修正はどうしても雑な印象になってしまい、失礼とされる場合があるんです。
そのため、書き直しが基本になります。
間違えてしまった袋はもったいない気もしますが、新しい袋に書き直すことで、きちんとした気持ちが伝わります。
祝儀袋は予備も含めて数枚用意しておくと、いざというとき安心ですよ。
また、字がにじんで読みにくかったり、かすれたりしていると、気持ちが雑に見えてしまうことがあります。
走り書きのような字も避けたほうが良く、できれば机の上など安定した場所で、ゆっくり丁寧に書くよう心がけてください。
たとえ字に自信がなくても、丁寧に書こうという気持ちは必ず伝わりますよ。
お祝い袋の選び方と渡し方のマナー
水引の色・結び方はどう選ぶ?
初節句のお祝い袋を選ぶときには、見た目のデザインも大切ですが、水引の種類にも意味があるので注意して選びたいところです。
初節句のような、子どもの成長を祝うお祝いごとには、紅白の蝶結び(別名:花結び)の水引がぴったりです。
この蝶結びは「何度でも繰り返して良いお祝い」という意味を持ち、入園や出産、七五三などにも使われる定番の水引なんですよ。
一方で、結び切りの水引は「一度きりで良いこと」に使われるため、初節句などの繰り返しても良いお祝い事には適しません。
結婚やお見舞い、お葬式などでは結び切りが使われます。
うっかり間違えると、相手に不快な思いをさせてしまうこともあるので、購入時には「蝶結びで紅白」のものを選ぶと安心です。
また、最近ではキャラクター入りや華やかなデザインの祝儀袋もありますが、格式を重んじる家庭や年配の方に贈る場合は、伝統的で落ち着いたデザインを選ぶのが無難です。
袋の大きさや紙質にも違いがあるので、中に入れる金額や相手との関係にあわせて選んでみてくださいね。
手渡しするタイミングと添える言葉の例
せっかく心を込めて用意したお祝い袋は、渡すタイミングや言葉にもひと工夫すると、より感謝やお祝いの気持ちが伝わります。
一般的には、初節句当日の訪問時やお祝いの食事会など、赤ちゃんと家族に直接会える場で手渡すのが理想的です。
玄関先や席に着いたときに「今日はお招きいただきありがとうございます。
初節句、おめでとうございます」とひと声かけて渡すと、丁寧で印象も良くなります。
さらに、
「ささやかですが、お祝いの気持ちを込めて」
「少しですが、心ばかりのお祝いです」
といったひとことを添えると、形式的になりすぎず、温かみのあるやりとりになりますよ。
もしどうしても直接渡せない場合は、事前に郵送してメッセージカードを添えるのもおすすめです。
その際は、お祝い袋を水引が折れないよう丁寧に梱包し、簡単な挨拶文を一緒に入れておくと好印象です。
まとめ|心を込めたお祝いの気持ちが伝わるように
初節句は、赤ちゃんが無事に生まれて成長してきたことを家族みんなでお祝いする、とても大切な行事です。
そんな晴れの日には、心からのお祝いの気持ちが伝わるように、贈る側としても丁寧な準備が求められます。
お祝い袋は、ただ金額を包むだけのものではなく、そこに込められた気持ちや心づかいがにじみ出る大事なアイテムです。
袋の選び方や表書きの書き方、筆記具のマナーや渡し方まで、ちょっとしたポイントを押さえるだけで、相手に「気持ちを大切にしてくれている」と感じてもらえるはずです。
また、お祝い袋は受け取った側がその後のお返しや管理をしやすくなるための役割も持っています。
丁寧に名前や金額を書いておくことは、思いやりのひとつでもあるんですね。
この記事では、そんな初節句のお祝い袋にまつわる疑問やマナーを、できるだけわかりやすくまとめました。
形式だけにとらわれず、何よりも「おめでとう」の気持ちを込めることがいちばん大切。
今回ご紹介した内容を参考にして、心のこもったお祝い袋を用意してみてくださいね。
きっとその気持ちは、相手にしっかり伝わりますよ。