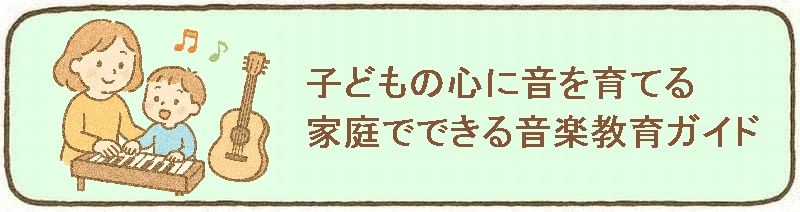兄弟や双子と一緒に音楽を練習する時間は、親にとって何よりも愛おしい瞬間ですよね。
笑い声があふれる日もあれば、順番をめぐってちょっとしたケンカになってしまう日もあって、「どうしたらもっと楽しくできるんだろう」と悩んだことがある方も多いと思います。
私自身も子どもたちがピアノやリトミックを練習するときに、はじめは仲良く弾いていたのに突然
「僕が先にやる!」
「私の番なのに!」
とぶつかり合う姿を何度も目にしてきました。
でもその経験を通して、兄弟や双子が一緒に練習することは単なる「楽器の習得」以上の意味があるのだと気づいたんです。
お互いに刺激し合うことで協力心や思いやりが育ち、親子の関わり方次第で音楽の時間が「ケンカの種」ではなく「絆を深めるきっかけ」になっていきます。
この記事では私自身が試行錯誤して得た体験談や、年齢や性格の違いによる悩みにどう向き合えばいいかというヒントを交えながら、兄弟や双子ならではの音楽練習を家庭で無理なく楽しく続ける方法をお伝えしていきますね。
読んでくださる方が「うちもできるかもしれない」と安心できるように、実際に役立つポイントや親が気をつけたい視点も盛り込んでいきますよ。
兄弟・双子で音楽練習をするときの魅力と難しさ
一緒に練習することで生まれるメリット
兄弟や双子が一緒に音楽を練習する時間って、見ているだけであたたかい気持ちになりますよね。
とくに幼児期や就学前の時期は、遊びの延長のような感覚で音楽とふれあえるので、兄弟がそばにいるだけで安心感が生まれたり、自信を持って取り組めたりすることもあります。
どちらかが覚えたフレーズをもう一人が真似して弾いてみる、そんな何気ないやりとりの中にも学びがぎゅっと詰まっているんです。
私自身もよく、「上の子がリズムを口ずさみながら弾いていたら、下の子がそれを聞いて自然と拍子を感じるようになった」なんて場面を見てきました。
大人が教えようとするよりも、同じ目線でいる兄弟からの刺激のほうが、子どもにとってはスッと入ってくることがあるんですよね。
音感やリズム感の育ちという面でも、こうした家庭でのふれあいはとても大きな意味を持っています。
また、音楽は感情を共有する手段にもなります。
同じ曲を一緒に歌ったり演奏したりすることで、兄弟同士の共感や一体感が育まれていく感覚があるんですね。
だからこそ、ただの習い事の時間ではなくて、兄弟で一緒に音楽をするという行為自体が、親にとっても子どもにとってもかけがえのない時間になっていくのだと思います。
よくある悩みやトラブル
とはいえ、現実は甘くないこともたくさんあります。
兄弟で同じ楽器を練習していると、「自分の番が短かった」と不満をぶつけたり、片方が先に進むともう一方がやる気をなくしてしまったりという場面もよくありますよね。
とくに双子の場合は「同時にスタートしたのに、なぜかできることに差が出る」ということが起きると、親としては焦ってしまう気持ちもわいてくるかもしれません。
私も実際に、上の子がリズム感よく弾けるようになってきたころに、下の子が「なんで私はできないの」と泣き出してしまったことがありました。
その時のあの表情が今でも忘れられません。
頑張っているのに、うまくできない自分を責めてしまう小さな背中を見て、なんとかしてあげたくなったんですよね。
でもその経験があったからこそ、子どもたちの「できる」「できない」よりも「楽しい」「やりたい」と思える気持ちを育てることのほうがずっと大事なんだと気づけました。
兄弟・双子ならではのプレッシャーと感情の動き
兄弟や双子が同じことに取り組む時、無意識に比べてしまうのは子ども自身も同じなんです。
とくに下の子は「お兄ちゃんみたいにできなきゃいけない」という気持ちを抱えやすく、逆に上の子は「できて当たり前」と思われるプレッシャーに疲れてしまうこともあります。
それに、双子の場合は外からも「どっちが上手?」と無邪気に聞かれてしまう機会があって、どちらかの心をそっと傷つけてしまうこともあります。
そういった微妙な感情の揺れを受け止めるには、親の見守り方や声かけがとても大切になります。
「どっちがすごいか」ではなく「どっちもがんばってるね」と、同じ目線で認めてあげることで、子どもは安心して自分のペースで進んでいくことができるようになるんですね。
親が知っておくべき“ペースのちがい”を受け入れる視点
兄弟や双子の育ち方には、それぞれの個性やペースがしっかりあります。
「同じ時期に始めたのに上達の差がある」と感じることは、決して珍しくないんです。
でもその違いに過剰に反応してしまうと、子ども自身も「遅れている自分はだめなんだ」と思い込みやすくなってしまいます。
私もある時期、つい「なんで弟のほうがまだこの曲を覚えられないんだろう」と感じてしまったことがありました。
でも、実は耳で聞いた音を覚えるのが得意な子と、指の動かし方を何度も確認して覚える子では、同じ練習法が合うとは限らないんですよね。
そこに気づいてからは、「この子にはこの方法が合ってるかも」と、それぞれのタイプに合わせた工夫をするようにしたら、2人とも音楽をもっと楽しめるようになったんです。
練習をうまく進めるための環境づくり
ピアノや楽器の順番を決めるルール作り
兄弟や双子でひとつの楽器を使っていると、どっちが先に弾くかでモメることってほんとによくありますよね。
うちでも
「昨日はお兄ちゃんが先だったよ!」
「今日は私が先の番でしょ!」
って、朝からお互いの主張がぶつかり合っていた時期がありました。
でも、あれって決してわがままとか意地悪じゃなくて、子どもなりにちゃんと「公平」でいたいという気持ちの表れなんですよね。
だからこそ、「順番ルール」は練習のストレスを減らすための大事な工夫になりますよ。
たとえば「今日は偶数の日だから弟が先」「月水金は姉、火木土は弟」みたいに、カレンダーとリンクさせる形にすると親も覚えやすくておすすめです。
それでもどちらかが不満そうな顔をしたら、「後の番の人はゆっくり練習を見て学べる特権があるんだよ」と伝えてあげると、少しずつ気持ちの切り替えもできるようになっていきます。
年齢差がある兄弟のペース合わせのコツ
年齢が違えば、できることや理解の速さに差があるのは当たり前なんですよね。
なのに、同じ練習内容をやらせてしまうと、下の子はついていけなくて自信を失ったり、上の子は「なんでこんな簡単なの?」と物足りなさを感じてしまったりします。
だから私は、練習する内容を少しずつアレンジするようにしてみました。
上の子には両手で弾くことに挑戦させて、下の子には同じメロディを片手でだけ練習してもらうようにしたり。
下の子には「今日はお兄ちゃんの演奏を聴いてリズムをまねしてみてね」と聞き役になってもらったりするんです。
これだけでも「同じ時間を共有する」感覚は残しながら、それぞれに合った練習ができるようになりますよ。
集中力が続きにくい子への声かけと休憩の入れ方
3~6歳くらいの子って、そもそも長時間じっと練習するのが難しい時期なんですよね。
集中できるのはほんの10分、いや5分のときもあります。
でも、だからこそ「集中できなかった=ダメな子」って思わせたくなくて、うちでは“短時間でもOK”のスタイルを取り入れるようにしたんです。
たとえば「5分弾いたら、シールを1枚貼れるチャレンジボード」を作ったり、「今日は1回だけでも音が出たらママとハイタッチ!」みたいなミニゴールを用意したりしました。
すると自然と「やってみようかな」って気持ちが湧いてくるようになるんですよね。
それでも疲れてしまったときは、無理に続けるのではなく「ちょっと一緒におやつ食べよっか」と声をかけて、練習そのものを嫌な思い出にしないこともすごく大切だなと感じました。
練習スペースを“ふたりの居場所”にする工夫
兄弟や双子が一緒に練習するとなると、場所選びって意外と大事になってきます。
テレビの横や通路の途中だと、ちょっとした音や人の動きで気が散ってしまったり、集中が切れてしまうこともありますよね。
だから私は、部屋の一角に「ふたり専用の音楽コーナー」を作ってみたんです。
- 好きなキャラクターの楽譜を並べたり
- 「今日の練習係」の名札を作って交代で貼れるようにしたり
そうやって「ふたりだけの特別感」を出すことで、子どもたちの気持ちも自然とそこに向くようになりました。
練習するためだけの場所があるって、それだけで「ちょっとやってみようかな」という気持ちにつながっていくんですね。
兄弟・双子ならではの親のサポート法
ケンカを減らすための声かけとほめ方
兄弟や双子で練習していると、ほんの些細なことで空気がピリッと張りつめることってありますよね。
「そこ違う!」
「なんで横取りするの!」
って言い合いになったと思ったら、あっという間に泣き出したり、手が出てしまったり。
でも、そんなときこそ親の声かけが空気をほぐす鍵になるんです。
たとえば、つい「なんでケンカするの!」って叱りたくなる気持ちをグッとこらえて、「お互いに一生懸命だったんだよね」と気持ちに寄り添う声をかけてみる。
すると子どもたちの目に少しだけ安心が戻ることがあるんですよ。
そして、争いのあとには
「さっきはちゃんと順番守ろうとしていたね」
「譲ってあげたところ、ママ見てたよ」
って、どちらにも“がんばり”を見つけてあげる。
叱るよりも、そうやってほめる視点を持つだけで、子どもたちは次からもう少し落ち着いてやってみようって思えるようになるんですね。
比べない・競わせない工夫
兄弟や双子って、どうしても
「どっちが先にできるか」
「どっちが上手か」
って、比べられやすい環境にいるんですよね。
しかもそれって親の無意識なひと言から始まってしまうこともあるから、ほんとに注意が必要なんです。
私自身も、無意識に「お兄ちゃんはもうここまでできたよ」と言ってしまって、下の子の目からすーっと光が消えていくような瞬間を見たことがあります。
あのときの自分を思い出すたびに胸がぎゅっと苦しくなるんです。
でも、そこから学んだことがありました。
子どもは「誰かよりすごい」って言われるより、「あなたらしく頑張ってるね」って言われることのほうがずっと嬉しいんですよね。
だから私は、「比べる」じゃなくて「それぞれの努力を見つける」ほうに意識を向けるようになりました。
小さな成長も逃さず、「昨日より一音増えたね」とか「今日は笑顔で練習できたね」って、本人の中の“進み”に寄り添う。
それだけで、兄弟どちらも自信を失わずに前に進めるようになりますよ。
失敗したときのフォローと安心感の与え方
子どもって、意外と自分に厳しかったりしますよね。
練習でうまくできなかっただけなのに、「もうやらない!」って楽譜を閉じてしまったり、涙をこらえて唇をかんでいたり。
そんなとき、親がどう寄り添うかで、そのあとの子どもの気持ちが大きく変わっていくんです。
私が意識しているのは、「失敗=終わり」ではなく「次へのステップ」として受け止めてもらうこと。
たとえば
「間違えたけど、ちゃんと最後まで弾こうとしたね」
「今は難しく感じるけど、きっと少しずつ慣れていけるよ」
そんなふうに言ってあげると、子どもは「またやってみようかな」と少しずつ前を向けるようになるんですよね。
特に兄弟や双子の場合、お互いの失敗を見てしまうからこそ、「恥ずかしい」「できない自分が嫌だ」と感じやすいところがあります。
だからこそ、どちらの子にも「失敗しても大丈夫だよ」っていう空気を作ってあげることが、親の大切な役目なのかなって思います。
練習の上達ももちろん大事だけど、それよりもっと大切なのは、音楽を続けたくなる気持ちを守ってあげることだと私は思うんです。
練習を続けるための楽しいアイデア
ごっこ遊びやリズム遊びを取り入れる
「さあ、練習の時間だよ」って言った瞬間に子どもの顔が曇ってしまうとき、ありませんか?私は何度もありましたよ。
「ピアノの前に座る=なんか大変なことが始まる」というイメージになってしまっていると、どんなにやさしく声をかけても子どもの心は動かないんですよね。
そんなときに効果があったのが、「遊び」として取り入れることでした。
たとえば、ピアノを弾くんじゃなくて「音楽屋さんごっこ」をするんです。
お兄ちゃんがピアノを弾いて、妹がお客さん。
演奏のあとに「すてきでしたー!」と拍手してもらう。
それだけで、子どもたちの目がキラキラするんですよ。
リズム遊びもおすすめです。
タンバリンやカスタネット、手拍子でもいいんです。
「ドレミに合わせてこのリズム打てるかな?」なんてチャレンジをすると、兄弟で競いながらも笑顔があふれる時間になります。
練習というより、“一緒に楽しいことをしている”という空気が、子どもたちの中に「またやりたいな」の気持ちを育ててくれるんですよね。
発表の場を家庭で作ってあげる(家族ミニ発表会など)
音楽って、人に聴いてもらってこそ嬉しさが大きくなるものなんですよね。
うまく弾けたときに「すごいね!」って言ってもらえるだけで、子どもたちは次へのやる気がぐっと増していきます。
だから我が家では、月に1回だけ「家族発表会」を開いています。
小さな紙でチケットを作って、招待状まで用意するんです。
パパと私が観客になって、ふたりが順番に演奏を披露してくれる。
ほんの3分のミニコンサートでも、子どもたちは練習に向かう気持ちが全然違ってくるんですよ。
兄弟で連弾ごっこをしたり、おそろいのリボンをつけて「今日はスペシャルデーだね」ってちょっとだけ特別感を演出する。
そういうちょっとした工夫が、「練習=イヤなもの」から「練習=みんなに見てもらう楽しみ」に変わっていくきっかけになっていくんです。
達成感を味わえる小さなゴールの設定
長い曲や難しい課題を前にすると、大人でも気が重くなってしまうことがありますよね。
それは子どもも同じで、「最後まで弾けるようにならなきゃ」と思うだけで、やる前から気持ちが折れてしまうこともあります。
だから私は「小さなゴールをたくさん用意してあげる」ことを意識しています。
たとえば「今日は最初の3音だけ弾けたらOK」「ここだけリズムが合ったらクリア」っていう感じで、どんなに小さな一歩でも“ゴール”として認めてあげるんです。
そして、できたらすぐに「すごいね!やったね!」と一緒に喜ぶ。
その繰り返しが、子どもたちの中に「自分はできるんだ」という自信を積み重ねてくれるんですよね。
兄弟で同じように進める必要はなくて、それぞれに合ったステップで進んでいけばいい。
その考え方が、家庭で音楽を続けるうえでとても大切だなあと感じています。
親も無理をしないために気をつけたいこと
練習の目標は「毎日同じ時間」より「その子のペース」
兄弟や双子の音楽練習を支える親として、つい
「ちゃんと毎日やらせなきゃ」
「同じ時間に習慣づけないと」
そう思ってしまうこと、ありませんか?
私もそうでした。
最初のころは、夕飯前の30分!と決めて、それを守らせることに一生懸命だったんです。
でもね、だんだんと気づいたんですよね。
「子どもって、その日その時の気分や体調で、まるで違う生きものみたいになるなあ」って。
毎日同じ時間に練習できたら理想だけど、現実はそう簡単じゃないんですよね。
遊び疲れていたり、幼稚園や保育園で頑張ってきた日は、ピアノの前に座る気力すらないこともある。
そんなときに「なんでやらないの!」と責めてしまったら、子どもにとって“音楽=しんどいもの”という印象になってしまうかもしれない。
そう思ってからは、「今日はやる気あるかな?」って声をかけて、様子を見ながら柔軟に対応するようにしたんです。
習慣って、厳しさの中で作るものじゃなくて、“続けたくなる空気”の中で育っていくんだなって、今は心からそう思っていますよ。
親のイライラをためない工夫
音楽の練習って、子どもが主役のはずなのに、気づくと親の感情もものすごく揺れますよね。
「なんでふざけてばっかりいるの」「ちゃんと聞いてってば」って言いたくなる気持ち、もう何百回と経験してきました。
でも、あるときふと、自分のイライラが子どもにも伝染してしまっていることに気づいたんです。
練習中の空気がピリピリしていると、子どもも緊張してうまく弾けなくなるし、ミスが増えてまた怒ってしまう…っていう悪循環にハマるんですよね。
だから私は「今日はちょっと疲れてるな」と思ったら、潔く“今日はやらない日”にしちゃいます。
お互いにイライラしそうな日には、無理して続けるよりも、
「一緒におやつを食べながら音楽の動画を見たり」
「CDを聴いたり」
そのほうが、ずっと心に残る時間になることもあるんですよね。
そして、自分の気持ちを整えるために、私はこっそりお気に入りのハーブティーを用意してから練習に向かうようになりました。
自分の心を整えてから、子どもの前に立つ。
それだけで、同じ時間がまったく違うものに変わることもあるんですよ。
習い事や家庭練習を長く続けるために大切な考え方
どうしても私たち親って「上達してほしい」「無駄にしてほしくない」っていう気持ちが強くなってしまいますよね。
月謝を払って通わせていると思えばなおさら。
でも、本当に大切なことって、“どれだけ上手に弾けるようになるか”じゃないんだなって、ある日気づかされたことがあったんです。
それは、発表会でうまく弾けなかった日。
兄弟それぞれにミスがあって、私は内心ハラハラしていたけれど、終わったあとに「すっごく楽しかった!また出たい!」と満面の笑みで話す子どもたちを見たとき。
「ああ、これでよかったんだ」って思えたんですよね。
音楽は、上手にやるためのものじゃなくて、心を動かすもの。
親がそのことを忘れずにいるだけで、家庭での練習がもっと温かく、もっと子どもらしい時間になっていくんじゃないかなって思います。
目指すのは「完璧」じゃなくて「一緒に楽しめる関係」。
そうやって続けていくからこそ、音楽が子どもたちの中に優しく根づいていくんですよね。
まとめ:兄弟・双子だからこそ育つ音楽の力と絆
兄弟や双子と一緒に音楽を練習するというのは、ただ「二人で仲良く演奏できたら素敵だな」という理想だけでは片づけられない、現実の葛藤や感情の揺れがたくさんあるんですよね。
順番の取り合いや、上達のスピードの違い、時には「なんで自分だけできないの」と涙を見せる場面だってあって。
親としては心がぎゅっと締めつけられるような気持ちになることもあります。
でも、そうした一つひとつのやりとりの中にこそ、子どもたちの成長や絆の種がたしかに蒔かれているんです。
今回ご紹介したように、
「順番を決めたり」
「それぞれのペースに合った練習を工夫したり」
「小さな達成感を味わえる環境を用意したり」
そういった工夫をすることで、兄弟だからこそ育つ思いやりや協力の心を音楽を通じて育んでいくことができます。
そして何より大切なのは、親自身が「無理しすぎない」「完璧を求めすぎない」という柔らかさを持ち続けることだと思うんです。
音楽は「うまくなる」ことももちろん大事だけど、それ以上に
「好きでい続けられること」
「楽しみながら続けられること」
が子どもたちの未来にとって何よりの宝物になっていきます。
兄弟や双子と一緒に奏でる音の重なりが、親子の記憶にもそっと残っていくような、そんなかけがえのない時間になりますように。
焦らなくていいんです。
一歩ずつ、親子で心を重ねていけたら、それがいちばんの“上達”かもしれませんよ。