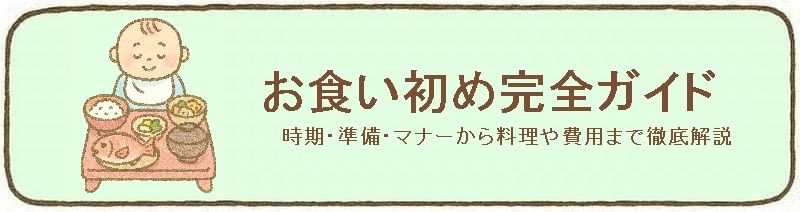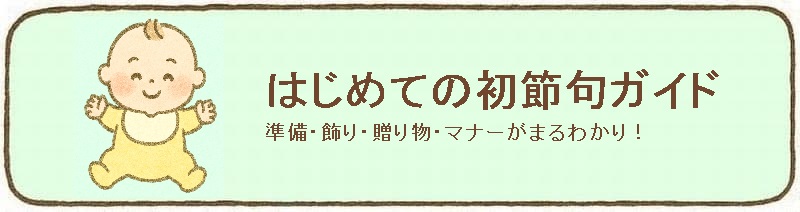出産を終えてホッとする間もなく、赤ちゃんとの生活が始まると
「お七夜」
「お宮参り」
「お食い初め」
「初節句」
など、慌ただしく行事が続いていきますよね。
初めての育児でただでさえ余裕がないなか、「どこまでやるべき?」「体調が戻ってないのに大丈夫かな…」と戸惑うママは本当に多いんです。
私も初産のとき、退院してすぐに名前の発表をどうしようとか、お宮参りの段取りを誰が仕切るかでぐるぐる悩みました。
育児書やSNSには素敵な行事の写真がたくさん並んでいて、比べては落ち込む日もありました。
でも、今ならはっきり言えます。
行事は“きちんとやること”より“そのときを家族でどう過ごしたか”のほうが何倍も大事なんですよね。
体調や気持ちに余裕がないときには無理しなくていいし、形にとらわれず「今の自分たちにできるかたち」で祝うことができれば、それで十分なんです。
この記事では、産後すぐにやってくる行事の流れや準備のポイントを、心と体を大切にしながら乗り切るためのヒントと一緒にやさしく紹介していきますね。
産後ママが行事でしんどくなるのは「あなたの弱さ」じゃない
出産を終えたばかりのママにとって、行事が続く日々は、想像以上に負担が大きいものなんですよね。
赤ちゃんのお世話は昼も夜も関係なく続くし、体の回復もまだまだこれから。
なのに、周囲から
「そろそろお宮参りかな?」
「お食い初めはどうするの?」
なんて聞かれると、どこか焦るような置いていかれるような、心がざわつく感じがしてしまう人も多いと思います。
でも、行事の準備や参加がつらく感じてしまうのは、決してあなたが「気力が足りない」とか「手を抜いている」からじゃないんです。
それは「ちゃんとやりたい気持ち」と「今の自分の限界」との間で、心が頑張りすぎている証拠なんです。
産後の体と心は、まだ回復途中にあるものだから
出産という大仕事を終えたばかりの体は、例えるなら全治1~2か月のケガをした状態に近いとも言われています。
さらに、ホルモンの変化や夜間授乳、寝不足による自律神経の乱れなども重なり、心のほうも揺れやすくなっている時期なんです。
そんな中で「周りと同じようにやらなきゃ」と思ってしまうと、それだけで体も心も限界を超えてしまいますよね。
だからまずは、自分の体調が戻っていないのは当たり前だという前提に立って、焦る気持ちを少しずつほぐしていってあげることが大切なんです。
「ちゃんとやらなきゃ」の呪いが、いちばん心を苦しめる
「ちゃんとやらなきゃ」
「サボってると思われたらどうしよう」
そうやって自分を追い詰めてしまう気持ちって、すごくよくわかります。
でも本当は、「ちゃんと」の基準なんて誰にも決められないし、何をどうしたら正解かなんて家庭によって全然違うんですよね。
SNSで目にする素敵な飾りつけや衣装は、そのご家庭なりのベストの形であって、それがそのままあなたにとっての正解とは限りません。
「みんなやってるのに自分はできていない」と感じてしまうと、必要以上に自分を責めてしまいがち。
でも、本当に大切なのは「何をやったか」より「どんな気持ちで過ごしたか」なんです。
行事を「つらいもの」にしないためにできること
まず、自分の体調や気持ちに正直になって、「今の私にできる範囲ってどこだろう?」と立ち止まって考えてみてください。
行事をスキップしたり、簡略化したり、誰かにお願いしたりすることは、決して悪いことではありません。
むしろそれは、家族や自分の安全を守るための、とても大事な判断なんです。
そして、気持ちがつらくなったときは、「しんどいのは私が弱いからじゃなくて、状況が大変だからなんだ」と、そっと自分に声をかけてあげてください。
それだけでも、心の中にふっとやさしい風が通るような感覚になることがあります。
あなたが「ちゃんと」していなくても、赤ちゃんは笑ってくれる
完璧な衣装じゃなくても、カメラマンに頼んだ写真じゃなくても、赤ちゃんはママの笑顔がいちばん好きなんですよね。
だから「行事をちゃんとこなす」ことに力を注ぐよりも、「赤ちゃんと今日一日穏やかに過ごせた」そんな気持ちのほうが、ずっとずっと価値があるんです。
誰かと比べず、自分のペースで、自分たちらしい過ごし方を選ぶこと。
それこそが、赤ちゃんとの大切な日々を心から祝ういちばんの方法なんです。
どうしても参加できないときは「休んでいい」という選択肢もある
子どもの行事って、学校や園のイベントスケジュールにしっかり組み込まれていて、「みんな出てるもの」と思い込んでしまいやすいですよね。
でも実際には、体調や家庭の事情で参加できない人もたくさんいます。
なにより産後という特別な時期には「お休みする」という選択肢も当たり前に用意しておいていいんです。
「私だけ参加できていない」そんなふうに感じてしまうのは、周りが見えているからこそ。
でも、見えていないところには、あなたと同じように悩んで、立ち止まっているママもきっといるんですよ。
学校や園には「伝えてみる」ことで道が開けることもある
行事に参加できないことを誰かに伝えるのって、なんとなく後ろめたさを感じてしまったりしますよね。
でも、ちゃんと相談してみると、意外なほどあたたかく対応してもらえることって多いんです。
先生たちもママたちの体調や家庭の背景をよく理解していて、「写真だけお渡ししましょうか」と言ってくれたり。
「他の日に少しだけ見学に来てもらえたら」なんて代案を出してくれたりすることもあります。
無理をして倒れてしまうより、できる範囲で関わる方法を一緒に考えてもらえることのほうが、結果的に子どもにとってもプラスになることが多いんです。
「行けないこと=ダメなこと」じゃないと知るだけで気持ちがラクになる
休むとき、参加できないとき、「どう思われるかな」と気になってしまうのはとても自然なことです。
でもその不安が膨らみすぎて、自分の限界を超えてしまうようなことがあったら、それは本末転倒なんですよね。
あなたが無理をしている姿よりも、穏やかに笑っている顔のほうが、子どもにとってはずっと嬉しいんです。
「参加しない」という選択は、けして消極的なものではなく、状況を見て最善を選んだ立派な判断です。
誰かにそう言ってもらえるだけで、気持ちはふっと軽くなりますよ。
「休む選択」ができることは、実はとても前向きな力
本当の意味で強い人って、自分の体調や限界をちゃんと見つめて「ここは一度立ち止まろう」と判断できる人だと思うんです。
行事に出ないとき、勇気が必要になるかもしれませんが、その勇気は子どもにとっても、家族にとっても、とても尊いものなんですよね。
「大事な日に休んだ」経験があるからこそ、次の行事がより愛おしく感じられたり、「やっぱり行けてよかったね」と笑顔になれたりするものです。
どんな選択をしても、それは“あなたが家族のことを大事に思っているからこその決断”なんだと、どうか忘れないでいてくださいね。
産後の行事は「完璧より、できる範囲」で十分
産後のママって、ほんとうに頑張り屋さんが多いからこそ、
「行事もちゃんとやらなきゃ」
「失敗したらかわいそう」
なんて、自分で自分にプレッシャーをかけてしまいやすいんですよね。
でも、そもそも完璧にやらなきゃいけない理由なんてどこにもないんです。
行事って、赤ちゃんの健やかな成長を願ったり、家族の記念を残したりするためのものであって、誰かに評価されるためのものではありません。
できる範囲で、気持ちを込めて、その日を迎えることができたら、それはもう十分素敵なお祝いなんです。
「ちゃんとしなきゃ」と思うほど、苦しくなるのは自然なこと
育児書やSNSには、「これをやりました」「こんなふうにお祝いしました」っていう華やかな記録がたくさん並んでいますよね。
でも、それを見て「私もこうしなきゃ」って思ってしまうと、気づかないうちに「できなかった自分」に落ち込んでしまったり。
誰に責められてるわけでもないのに、心がざわざわしたりしてしまうんです。
私も、お食い初めのときに豪華なセットを準備できなかったことが気になって、しばらくモヤモヤしていました。
でもあとになって、赤ちゃんがケラケラ笑っていた写真を見返したら「これでよかったんだな」って、ようやく思えたんです。
たとえば「午前だけ参加」でも、思い出はしっかり残る
全部をこなさなきゃいけないって考えなくて大丈夫です。
お宮参りも、無理して遠出しなくても、近所の神社でお参りするだけでじゅうぶん。
体調がすぐれないときには写真だけでもいいし、タイミングが合わないときは、数日ずらしたってまったく問題ありません。
実際、時間を短くしたり、午前中だけ参加したり、赤ちゃんの機嫌に合わせて内容を変えたりしているご家庭はたくさんあります。
「みんなと同じ形」でなくても、自分たちのスタイルでやれたら、それが一番なんですよね。
行事の本当の目的を思い出してみて
思い出って、準備の完璧さや飾りの豪華さよりも、「そのときの気持ち」で記憶に残ることが多いんですよね。
たとえば、少しぐらい予定通りに進まなくても、家族で笑い合えた時間があれば、それはかけがえのない宝物になります。
赤ちゃんが主役の日だからこそ、ママや家族が無理をしてヘトヘトになってしまうよりも、みんなが笑顔でいられることのほうが、ずっと大切なんです。
家族と協力することで行事はもっとラクになる
産後の行事って、どうしても「ママが準備して段取りして…」という流れになりがちなんですよね。
でもそれ、ほんとうに全部一人で背負う必要はないんです。
むしろ、ママが倒れてしまうより、家族みんなで力を合わせて少しずつ進めていくほうが、ずっとあたたかい行事になります。
小さなことでも「これ、お願いできる?」と声に出して頼ること、それがあなたの負担を減らす一番の近道です。
家族との協力体制が整ってくると、イベント自体ももっと穏やかで幸せな空気になりますよ。
「全部自分でやらなきゃ」は思い込みかもしれない
赤ちゃんのことも行事のことも「私がやらなきゃ」と気負ってしまうのは、ママとして頑張っている証拠。
でもその一方で、「手伝ってもらってもいい」「むしろ手伝ってもらうべき」っていう考え方に切り替えることも、とても大切なんですよね。
実際、お願いされる側のパートナーや家族は、「何をすればいいかわからなかっただけ」ということも多くって。
なので「こういう準備をお願いしたいな」って具体的に伝えるだけで、意外なほどスムーズに助けてもらえたりします。
「お願いの仕方」で家族の動き方が変わることもある
協力してほしいときは、できるだけ「誰に・何を・どのタイミングで」お願いするかをはっきりさせると、家族も動きやすくなります。
「当日の買い出しだけお願いしたいな」
「お参りの運転だけお願いできる?」
のように、ポイントをしぼって伝えると、負担の分担が明確になって、ママも安心しやすくなるんですよね。
大切なのは、相手に気を遣いすぎて何も言えなくなることより、「言葉にすることで自分を守る」ことなんです。
感謝の気持ちは素直に、だけど遠慮しすぎないで
誰かに手伝ってもらったとき、「ありがとう」の気持ちを伝えることはとっても大事。
でもそれは「自分がダメだったから」じゃなくて、「みんなで協力できてよかったね」という前向きな感謝でいいんですよね。
「助かったよ」
「一緒にやれてよかったね」
そう伝えるだけで、家族の中に優しい空気が流れていきます。
行事は家族のイベントだからこそ、みんなでつくる時間として楽しめたら、それだけで素敵な思い出になるんです。
「産後だからこそ」気をつけたい心と体のサイン
産後って、赤ちゃんのお世話に気持ちが向きすぎて、自分の体調や心の変化に気づきにくくなってしまうことがあるんですよね。
でも実際には、ホルモンバランスの大きな変化や、寝不足、授乳の負担、予想外の孤独感など、見えない疲れが静かに積み重なっていきます。
行事の準備や「ちゃんとしなきゃ」という気持ちが重なってくると、体や心からのSOSがじわじわと表に出てくることもあるんです。
だからこそ、「私、大丈夫かな?」って自分に問いかける時間を、ほんの少しでも持ってあげてほしいんです。
「疲れてる」だけじゃない、心のサインに目を向けて
なんだか涙もろくなったり、いつもなら気にならないことでイライラしたり、理由もなく不安になったり。
そんな心の変化があったとき、「産後だから仕方ない」と流すこともできるけれど、それがずっと続いているなら、一度立ち止まってほしいんです。
「また明日も同じことの繰り返し…」という気持ちが重たくなってきたら、それは心の中で小さな悲鳴が上がっているサインかもしれません。
がんばりすぎている人ほど、そのサインに気づかないまま無理を重ねてしまうことがあるんですよね。
体が発している違和感にもちゃんと気づいて
産後の体は、見た目ではわからなくても、内側ではまだ傷が癒えきっていなかったり、筋力や内臓のバランスが戻りきっていなかったりします。
長時間立っているだけでめまいがしたり、食欲が落ちたり、眠りが浅くなったりしていませんか?それは「少し休んでほしい」という体からのメッセージです。
行事に追われていると、「とりあえずやらなきゃ」と気合いで動いてしまいがちだけど、まずはあなたの体調がいちばん大事なんですよね。
心と体のサインを見逃さないためにできること
日々の中でほんの少しでも、「あ、今ちょっとしんどいな」と感じたら、その気持ちをメモに残したり、誰かに話したりしてみてください。
自分の状態を言葉にすることで、ふっと冷静になれる瞬間が生まれたり、思わぬサポートが得られたりすることもあります。
「頑張らないと」だけじゃなく、「今日は休もう」と思えることも、育児を続けていく上でとても大切な力なんですよ。
心と体の声に耳を澄ませて、必要なときには勇気を出して「今日はムリかも」と声に出してみてくださいね。
まとめ:赤ちゃんとママが心地よく過ごせる行事の形を選ぼう
出産を終えたあとって、何をするにも「いつもの自分」じゃいられなくて、どこか置いていかれたような気持ちになる日がありますよね。
行事だって、「ちゃんとやってあげたい」って思う気持ちはあるのに、体がついてこなかったり、気持ちがついてこなかったりして。
「なんで私はできないんだろう」って自分を責めたくなるときもあると思います。
でも、それって決して“手抜き”でも“サボり”でもなくて、むしろ“家族を大事にしようとする心”のあらわれなんだと思うんです。
私も、初めてのお宮参りの日に、無理して準備をして、結局帰ってきてから熱を出して寝込んだことがありました。
あの日の写真を見ると、頑張って笑ってる自分が写っていて、「今なら、あの私に“ちょっと休もうよ”って声をかけたいな」って思います。
完璧にやろうとするよりも、心からその日を味わえるほうが、ずっと大切だったなって今では思えるんです。
だから、どうか忘れないでください。
行事は「しっかりやること」が目的じゃなくて、「あなたたちらしい形で、赤ちゃんの成長を喜ぶこと」がいちばんの本質です。
たとえ省略したり、別の日にしたりしても、笑顔で過ごせたなら、それだけで十分素敵な思い出になるんです。
ママが無理をしないでいられること、それは赤ちゃんにとっても、家族にとっても何よりの贈り物ですよ。
今日読んでくれたあなたが、少しでも気持ちを緩めて「私たちのペースでいいんだ」と思えたなら、それだけでこのページの意味はあったと思います。
大丈夫、あなたのやり方で、あなたの大切な日々をゆっくり歩んでいってくださいね。