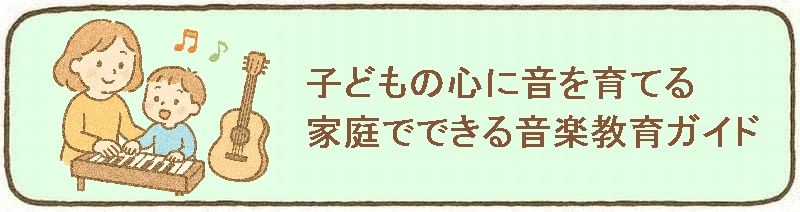「ピアノって早く始めたほうがいいのかな」「やっぱりリトミックってみんなやってるしやらせたほうがいいのかな」そんなふうに考えて胸の奥が少しざわついた経験、きっと一度はあるんじゃないでしょうか。
子どもの習い事って、ただの趣味じゃなくてこれからの成長や将来にも関わることだから、親としてはどうしても慎重になりますよね。
自分の選択が本当にこの子のためになるのか、このタイミングでいいのか、迷えば迷うほど不安が大きくなってしまうものです。
私自身もそうでした。
周りの子がどんどん習い事を始めていく中で、焦るような気持ちや置いていかれるような感覚があったんです。
でも実際に始めてみると、よかったこともあれば、あのときこうしていればと感じたこともありました。
きっとそれは、どの家庭にもある“リアル”なんですよね。
だからこそ、この記事では「習わせてよかった」と心から思えた瞬間と「ちょっと後悔したな」と胸がチクリとした瞬間を、年齢別の体験をもとに丁寧に伝えていきたいと思います。
習い事は誰かと比べるためのものじゃなくて、わが子の未来を育てていくための選択です。
正解が一つじゃないからこそ、いろんな声を知ることで見えてくるものがありますよ。
あなたがこれから踏み出す一歩を少しでも安心して選べるように、ここにたくさんの親たちの本音を置いていきますね。
音楽の習い事、始める前に知っておきたかったこと
「みんなやってるから」だけで決めるのは危ないかも
「お友達が通い始めたからうちもそろそろ…」
そんなふうに周りの動きに背中を押されるようなかたちで音楽の習い事を始めるケースは、とても多いと思います。
私も最初はそうでした。
「周りと同じようにしておけば安心」そんな気持ちも正直あったんです。
でもね、本当に大事なのは「わが子にとって今がそのタイミングなのか」という視点だったんですよね。
リトミックやピアノのような習い事は、興味や好奇心が育ちやすい時期にうまく出会えると、子どもの世界が一気に広がっていくものです。
でも、まだ体力的にも精神的にも準備ができていない時期に無理に始めてしまうと、それは“音楽そのものを苦手にさせてしまう入り口”になってしまうこともあるんです。
だからこそ「うちの子はどう感じているか」「どんな音や動きに興味を示しているか」をしっかり見つめることが、何より大事だったなって、今なら思います。
早く始めたほうがいい?遅くても間に合う?
「3歳から始めると絶対に有利」とか「6歳過ぎたら耳が育たない」とか、ネットや本にはいろんな情報があふれていて、何を信じたらいいのか本当にわからなくなりますよね。
確かに、幼いうちの耳の感度やリズム感はぐんぐん伸びていく時期ではあるけれど、それは“個人差がとても大きい”ということも同時に知っておいてほしいんです。
実際、3歳で始めてすぐに夢中になる子もいれば、5歳でも「まだちょっと早かったかな」と感じる子もいます。
小学生になってから始めたお子さんが、驚くほどの集中力と理解力で一気に上達していったケースもたくさんありますよ。
早く始めたからといって成功するわけでもなく、遅かったからといって不利になるわけでもない。
だからこそ、焦らずに、その子自身の“やりたい”のサインを丁寧に見つけてあげることが、いちばんの近道になるんじゃないかなと思います。
親の「期待」が子どもにプレッシャーになることも
「楽しんでくれたらいいな」と思って始めた習い事なのに、いつの間にか
「もっと練習してほしい」
「このくらいはできて当然」
そんなふうに親の側の期待がどんどん膨らんでいってしまうことって、ありませんか?
私も気づけば「せっかく高い月謝を払ってるのに」とか「先生に褒められてほしいな」なんて気持ちが頭をよぎるようになってしまって、練習がうまくいかないとイライラしてしまったりしていました。
でも、子どもからすれば“親が笑顔で見てくれているかどうか”が何よりの安心材料なんですよね。
親の期待が強すぎると、子どもは「もっと頑張らなきゃ」じゃなくて「失敗しないようにしなきゃ」と感じてしまって、のびのびと音楽に向き合う気持ちがしぼんでしまうこともあります。
だからこそ、うまく弾けた日もそうじゃない日も、「がんばってるね」「音楽って楽しいね」と、結果よりも気持ちや過程を認めてあげることが、いちばんの応援になるのかもしれません。
一度始めたらやめられない?習い事に「柔らかい選択肢」を持っておく
「途中でやめたらもったいない」「せっかく始めたのに中断したら…」そう感じて、子どもの意思よりも“続けること”を優先してしまいそうになることもあると思います。
でも、本当はやめることも、立ち止まることも、もう一度やり直すことも全部“選んでいい”ことなんですよね。
習い事は続けることがゴールじゃなくて、その中で何を感じて、どう自分の中に積み重ねていくかが大切なんだと、後から気づきました。
だから
「いったんお休みしてもいいんだよ」
「別の方法もあるかもしれないね」
と、親の側が柔らかく構えているだけで、子どもは案外すっと自分で答えを出してくれたりするんです。
親も子も、“今だけの正解”にとらわれすぎないで、ゆるやかにその子のペースに寄り添えるといいですよね。
【年齢別】習わせてよかった・後悔したリアル体験談
3歳で始めたケース|遊び感覚の中に芽生えたリズム感
3歳といえば、まだまだ日々の遊びや生活の中で世界を広げていく時期ですよね。
そんな幼い時期に始めたリトミックや音楽遊びは、まさに“遊び”と“音”が自然に混ざり合った時間でした。
うちの場合も、教室で音楽が鳴ると手を叩いたり体を揺らしたりしながら、笑顔で楽しんでいたんです。
決して“習う”という堅苦しさはなくて、親子でふれあいながら音を感じる、そんなひとときでした。
その中で少しずつ音の高低に反応したり、リズムを覚えて真似してみたりするようになって、「音楽ってこんなふうに心と体で入ってくるんだな」と感じることが多くて。
この時期だからこそできた“無理のないスタート”だったなと、今でも思います。
親としてもプレッシャーが少なく、習い事というより“特別な遊び時間”という感覚で始められたのがすごくよかったです。
5歳で始めたケース|楽しさと真剣さのバランスがとりやすかった
5歳になると、自分で「これやってみたい!」という気持ちが育ってくる時期でもありますよね。
実際にうちの子も、幼稚園で歌を習ったり、お友達のピアノを聴いたりしているうちに「弾いてみたい」と言い始めたんです。
そのときに始めたピアノは、本人の中に“やりたい”という気持ちがあった分、吸収のスピードも違いました。
そして何より、「がんばったら弾けるようになった」という体験が、子どもにとっての大きな自信になっていったのを感じました。
もちろん毎日スムーズに練習が進んだわけじゃないけれど、5歳くらいになると先生の話もきちんと聞けるし、集中できる時間も少しずつ長くなるんですよね。
その分、レッスンの内容もしっかりしてきて、「学び」としての手ごたえもありました。
楽しさとちょっとした緊張感、そのバランスがとりやすかった時期だったなと感じています。
小学校入学後に始めたケース|理解力はあるけど時間のやりくりが大変
小学校に入ると、子ども自身の理解力や集中力はぐんと伸びて、先生の指導もどんどん入ってくるようになります。
でもその反面、習い事をする時間をどう作るかという点では一気に難しくなるんですよね。
学校の宿題もあるし、お友達と遊びたい気持ちもあるし、ピアノに向かう時間がついつい後回しになってしまうこともありました。
特に低学年のうちは、親がある程度“習慣づくり”をサポートしてあげる必要があって、そこに疲れてしまうこともあったのが正直なところです。
でも、小学生だからこそ「譜面を理解して弾く」ことができるようになるし、「曲のイメージをふくらませて演奏する」楽しみも少しずつ出てきて、本人がぐんと成長していく姿を感じられました。
時間との戦いはあったけれど、それ以上に「理解して自分の表現にしていく力」がついていくのを見て、始めてよかったと感じた場面もたくさんありました。
始めるのが遅かった?後悔よりも大事な「今」の気持ち
「もっと早く始めていれば…」と思ったこと、正直あります。
でも、それ以上に大切だなと気づいたのは、「今この子がどう感じているか」でした。
小学生の高学年になってから始めた子も、最初は緊張していたけれど、レッスンで楽しく曲を覚えられるようになってからは
「ピアノが好き」
「もっと弾いてみたい」
とどんどん前向きな気持ちを見せてくれるようになりました。
始めるのが早かったか遅かったかはあくまで“比較”であって、今の本人にとっての“ベストなタイミング”がいつなのかが大事なんですよね。
遅かったからダメなんじゃなくて、「このタイミングで出会えてよかったね」と思えるような関わり方ができれば、それは何より価値のあるスタートになると思います。
焦らず、比べず、わが子の「今ここ」の気持ちを大切にしてあげること。
それがいちばんの「後悔しない選び方」なのかもしれません。
「後悔してるかも…」と感じたポイントとその乗り越え方
「もっとしっかり教室を選べばよかった」
習い事を始めるときって、最初は「とにかく近くて通いやすいところで」とか「体験でなんとなく楽しそうだったから」っていう気持ちで選びがちですよね。
私もそうでした。
だけど、いざ通い始めてみると、先生の教え方がうちの子にはちょっと厳しすぎたり、雰囲気が合わなくて毎週のレッスンがだんだん億劫になっていったんです。
子どももなんとなく元気がなくなって、「行きたくない」と言う日が増えていきました。
あのとき、「まあ、続けていけば慣れるよね」と見過ごさずに、もう少し比較検討していたら、違ったかもしれないなと少し後悔しています。
教室選びって“ただ近くて安いから”だけじゃなくて、先生との相性や教室の雰囲気、子どもが安心して通えるかどうかまで含めて見てあげることが、本当に大切なんだなと実感しました。
「子どもに合うタイミングじゃなかった」
始める時期って、親の都合や焦りで決めてしまいがちなところがあって、「今始めたほうがいい気がする」という感覚で突っ走ってしまうこともありますよね。
でも、実際に始めてみたら、子どもが全然ついていけなかったり、レッスン中も集中できずにぼーっとしていたりして、「あれ、ちょっと早かったかも…」と気づくことも。
うちの場合も、ちょうど下の子の育児と仕事復帰が重なっていた時期で、親の余裕がなかったのに「今しかない」と思い込んでスタートしてしまったんです。
結局、レッスンにも身が入らず、親もイライラしてしまって、お互いにしんどい数ヶ月になってしまいました。
後から思えば、あのときは“始める”よりも“待つ”ことが必要だったんですよね。
子どものペースを見てあげること、それがいちばんの近道になることもあるんです。
「親が無理して通わせてしまっていたかも」
送迎、月謝、発表会の準備、毎日の練習の声かけ。
どれも「子どものために」と思ってやっていたはずなのに、ある日ふと「私、ちょっと無理してない?」と感じたことがありました。
習い事って“続けることが正義”みたいに思ってしまいがちで、自分の疲れやしんどさにフタをしてしまうんですよね。
でも、親が余裕をなくしてしまうと、その空気ってやっぱり子どもにも伝わってしまって、
「練習しなさい!」
「また忘れたの?」
っていう言葉ばかりが増えてしまったんです。
あのとき、もっと素直に「ちょっとしんどいな」って認めて、スケジュールを見直したり、回数を調整したりしていれば、お互いもっと楽に続けられたかもしれないなと振り返ります。
頑張ることは大事だけど、頑張りすぎないことも、親としての優しさなのかもしれませんね。
やめたいと言われたとき、親としてできること
「もう行きたくない」と子どもに言われたとき、最初は正直ショックでした。
あんなに応援してきたのに、もう終わりなの?って、心のどこかで寂しさや悔しさも感じてしまって。
でも、その言葉の裏には、疲れていたり、不安だったり、理由がちゃんとあるんですよね。
だからこそ「やめるなんてダメ」と否定するんじゃなくて、「どうしてそう思ったの?」って優しく聴くことから始めてみたんです。
すると、「練習がしんどい」「先生がちょっと怖い」そんな小さな本音がポロポロと出てきて。
やめるかどうかはあとで決めればいい。
まずは気持ちをしっかり受け止めてあげること。
それが、子どもにとっても“自分の気持ちを大切にしてもらえた”という安心につながって、結果的にまた前向きに向き合ってくれるようになったんです。
習い事って、技術よりも“気持ちのやりとり”がいちばん大事なのかもしれませんね。
やらせてよかったと実感できた瞬間とは
自信を持って舞台に立ったとき
発表会の日、照明に照らされたステージに立つわが子の姿を見た瞬間、それまでのすべての練習の日々が一気によみがえってきました。
不安で泣きながら練習した日も、思うように弾けなくてくやし涙をこらえていた日もあったけれど、本番ではしっかりと鍵盤を見つめて、最後まで弾ききったんです。
その姿に、こらえていた私の涙がふっとこぼれました。
たとえ間違えても、途中で止まってしまっても、それでもステージに立って音を奏でたという経験は、子どもにとっても親にとっても大きな「成功体験」になりますよね。
自信って、こういう「できた」という積み重ねの中で育っていくんだなと感じました。
あの姿を見たとき、心の底から「やらせてよかった」と思えました。
日常で音楽が身近になっていく変化
ふとした瞬間に鼻歌を歌っていたり、テレビのBGMに合わせてリズムをとっていたり。
気がつけば、生活の中に音楽が自然とあふれてくるようになっていました。
宿題の合間にピアノをつま弾いたり、「この曲知ってる!」と学校で覚えた歌を口ずさんだり。
以前は音楽と無縁だった日常が、いつの間にか“音のある暮らし”になっていて、それがとても心地よかったんです。
音楽って、何かのスキルとしてだけじゃなく、心を満たしてくれるものなんですよね。
習い事という枠を超えて、日々の中で自然に音を楽しめるようになったこと、それがいちばんのギフトだったように思います。
練習を通じて子どもとの会話が増えたこと
「今日この曲むずかしかった~」「ここ、左手がうまく動かないんだよね」そんなふうに練習をきっかけに、子どもと自然に会話が生まれるようになりました。
以前は忙しさに流されて、つい
「宿題やったの?」
「早く寝なさい」
ばかりだった日々が、ピアノという共通の話題を通して、子どもの小さな努力や気持ちに寄り添える時間に変わっていったんです。
「ここ、弾けるようになったね!」「頑張ったんだね」と言葉をかけることで、子どもの目がぱっと輝いたりして、そんな姿にこちらが励まされることもありました。
音楽はただ聴くものじゃなくて、親子の心をつなげる“コミュニケーションの道具”にもなるんだと実感しましたよ。
「習わせてよかった」は、親子で共有できる思い出になる
最初はドキドキしていた体験レッスン、初めての発表会、うまく弾けなくて悔しくて泣いた日、そして「できた!」と笑顔で手を叩いた日。
そのすべてが、今となっては宝物のような記憶です。
親子で同じ時間を過ごして、同じ喜びや悔しさを共有できるって、習い事があったからこそ生まれた関係性だったのかもしれません。
子どもが成長していく中で、これから先、音楽を続けるかどうかはわからないけれど。
「あの時、音楽と一緒にがんばった時間があったね」って、いつか一緒に振り返れる思い出ができたことが、本当にうれしいんです。
音楽は、技術だけじゃなくて、こうして“思い出”としても親子の心に残っていくんですね。
後悔しないために…始める前に考えておきたいこと
その習い事、本当に「うちの子」に合っている?
「ピアノは脳にいいらしいよ」
「音感は小さいうちが勝負らしいよ」
そんな情報を見聞きすると、「じゃあうちの子にも…!」って気持ちになりますよね。
私もそうでした。
でも、あとから思ったんです。
どんなに良さそうな習い事でも、“その子に合っているかどうか”がいちばん大事なんですよね。
たとえば、じっと座って細かい作業が好きな子にはピアノは向いていたけど。
体を動かすことのほうが得意で、リズムに合わせて踊ったりするほうが楽しそうな子には、リトミックのほうが合っていたり。
もちろん、やってみなければわからないこともあるけれど、「この子、どんなときにいちばん楽しそうかな?」と日常の様子からヒントを探してあげると、意外と“向き”って見えてくるものなんですよ。
習い事って「とりあえず始める」よりも、「ちゃんと見て選ぶ」ほうが、結果的に長く楽しく続けられると思います。
「費用」「場所」「親の負担」もリアルに計算しておこう
通うとなれば月謝はもちろん、発表会や教材費、交通費や衣装代など、思っていた以上にかかる費用があとからじわじわと出てくることもあります。
うちも、最初は「月○千円くらいなら大丈夫そう」と始めたものの、気づけば年間で十万円を超えていてびっくりしたことがありました。
さらに、送迎の負担や兄弟の予定との調整、日々の練習の声かけや付き添いも、想像以上に時間とエネルギーが必要でした。
でも、そうした現実をあらかじめ知っていれば、心の準備ができるし、夫婦でどう分担するかを相談したり、回数や教室を見直したりと、続けやすい形に整えていくこともできるんですよね。
無理なく続けるためには、“今の暮らしの中に自然に組み込めるかどうか”という視点も大切なんだと実感しました。
子ども自身の気持ちにちゃんと耳を傾けてあげてね
どんなに親が良かれと思って選んだとしても、子どもが「やってみたい」「楽しそう」と思える気持ちがなければ、それはただの“親の期待”になってしまいます。
子どもって、うまく言葉にはできなくても、ちゃんとサインを出してくれているんですよね。
目を輝かせて音楽に反応しているときもあれば、体験レッスンで不安そうにしていたり、家で話題に出すとふっと目をそらしたり。
そういうちょっとした表情やしぐさを見逃さずに、「無理してない?」「楽しそう?」ってそっと問いかけてあげること。
それが、お互いに納得したうえで始められる一歩になると思います。
やらせることが目的じゃなくて、一緒に「始めてみようか」と言い合える関係でいられたら、それだけで習い事の時間がぐんと豊かなものになりますよね。
まとめ|「習わせてよかった」も「ちょっと後悔」も親子の経験になる
習い事って、始めるときも続けていく中でも、迷いや不安がつきものですよね。
うちも例外じゃなくて、「これでよかったのかな?」と何度も立ち止まりながらの毎日でした。
うまくいった瞬間はもちろん嬉しかったけど、それ以上に心に残っているのは、思うようにいかなくて一緒に悩んだ日々だったかもしれません。
でも、そんな時間があったからこそ、親子の会話が増えたり、少しずつお互いを理解し合えたりして、ただの習い事じゃない“特別な経験”になっていったんです。
始めてよかった、続けてよかった、そして「ちょっと失敗したかも…」と感じた出来事も、全部まるごとが私たち家族の宝物になっています。
音楽の上達以上に、その時間の中で子どもが見せてくれた表情や気持ちに気づけたこと。
それこそが、何より大きな成長だったのかもしれません。
他の家庭と比べて「遅いかも」「うちはうまくいってないかも」と不安になることもあるかもしれません。
でも、習い事は競争じゃないし、誰かの正解が自分たちの正解とも限りませんよね。
親子で一緒に考えて、一緒に選んで、一緒に進んでいけたら、それがいちばんの“うちらしい”道になるはずです。
どうか焦らずに、わが子の今と、これからと、ちゃんと向き合っていってくださいね。
たとえ遠回りに見えても、それはきっと“意味のある回り道”になって、あたたかい思い出として残っていきますから。