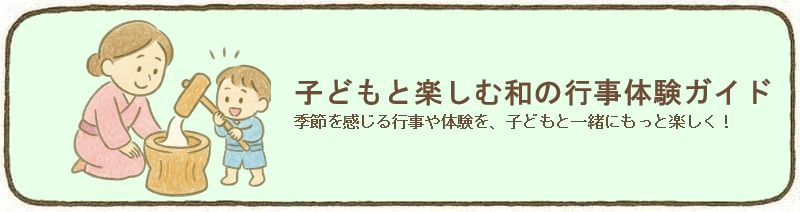七五三って、どこか「ちゃんとしなきゃ」と思わせる行事なんですよね。
私自身、最初は“子どもの成長を祝う日”くらいの気持ちでいたんですが、調べていくうちにその意味の深さと準備の多さに圧倒されてしまいました。
「どこにお参りするの?」
「何を着せればいい?」
「写真ってどうすればいい?」
そんなふうに次々に出てくる疑問に、親としての責任を感じて不安になったことをよく覚えています。
だけど、そんな中で気づいたのは、七五三って“きちんとする日”じゃなくて、“子どもと一緒に今日まで歩んできたことを喜ぶ日”でもあるということでした。
だからこそ、事前に流れやポイントを知っておくだけで、不安が減って心からその一日を楽しむ余裕が生まれるんです。
この記事では、初めてでも安心できるように七五三の意味や準備、当日の過ごし方まで、体験を交えて丁寧にご紹介していきます。
親としての「はじめての七五三」が、家族にとってあたたかい思い出になるように、少しでもお手伝いができたらうれしいです。
七五三ってどんな行事?意味と年齢の目安を知ろう
七五三の由来と込められた願い
七五三は、平安時代や江戸時代の貴族や武家に由来する伝統行事で、子どもが節目の年齢を無事に迎えたことへの感謝と、これからも健やかに育ちますようにという祈りを込めて行われるものです。
当時は今のように医療も栄養も十分ではなく、幼い命が無事に成長することは決して当たり前ではありませんでした。
だからこそ3歳、5歳、7歳という節目の年齢を迎えられたことが特別で、その喜びを家族で祝い、神様に報告し感謝する意味が込められているんです。
こうやって言葉にすると少し堅苦しく聞こえるかもしれませんが、私はこの背景を知ったとき、自分の子どもが元気にここまで大きくなってくれたことがとてもありがたく思えて、自然と涙が出そうになりました。
成長のありがたみって、行事に触れると改めて実感するものなんですよね。
なぜ3歳・5歳・7歳なの?年齢と性別による違い
七五三では、男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳にお祝いをするのが一般的です。
この3・5・7という年齢にはそれぞれ意味があります。
3歳は「髪置き(かみおき)」といって、それまで剃っていた髪を伸ばし始める儀式。
5歳は「袴着(はかまぎ)」という、男の子が初めて袴を着る節目。
7歳は「帯解き(おびとき)」といって、女の子がそれまで紐で結んでいた着物から、本式の帯を結ぶようになる通過儀礼です。
もちろん、現代ではこうした意味よりも「成長を祝う日」という位置づけが中心にはなっていますが、伝統的な背景を知ると、その行動ひとつひとつがより愛おしく思えてくるんですよね。
数え年?満年齢?悩んだときの選び方
よくある悩みのひとつに「数え年で祝うべきか、満年齢で祝うべきか」というものがあります。
昔は数え年(生まれた年を1歳とし、年が明けるごとに年齢を加える方法)で行うのが一般的でした。
でも現在は、子どもの成長や家庭の都合にあわせて満年齢(誕生日を基準に数える)で行う家庭も増えています。
我が家もこの点では迷いましたが、当時はまだ2歳の終わりだった娘が「着物着たくない」と涙目になっていた姿を見て、無理はさせたくないと判断して翌年に持ち越しました。
結果的に、本人が自分の意思で「これが着たい」と言ってくれた姿に成長を感じて、それだけでもう感無量でした。
何歳でやるかよりも「どう祝うか」「どんな思い出になるか」の方がずっと大切なんですよね。
地域や家庭によっても異なる七五三のかたち
実は七五三には明確な“全国共通ルール”のようなものはなく、地域によって風習も微妙に異なります。
たとえば、関東では11月15日にこだわらず10月中旬から11月下旬まで分散して行うことが多く、関西では満年齢で祝う家庭が比較的多いという傾向もあるようです。
また、祖父母の意見を尊重して昔ながらの形式を取り入れることもあるでしょう。
私も最初は「正解」を探して焦ってしまったのですが、最終的には「わが家らしくて心に残るお祝いのかたち」がいちばんだと気づいてからは、肩の力がすっと抜けました。
七五三は親にとっても“感謝の儀式”
七五三は、子どもにとっての成長の節目であると同時に、親にとっては「ここまで育ててこられたことへの感謝を実感する日」でもあると私は思っています。
夜泣きで眠れなかった日々や、初めての熱におろおろしたあの日、保育園の門の前で泣きじゃくる我が子を抱きしめながら背中を押したあの朝。
そんな日々の積み重ねを思い返していると、「ああ、この子と一緒にここまで来たんだな」と心がじわっと温かくなるんです。
七五三の参拝は、その歩みをそっと神様に報告する時間でもあるのかもしれませんね。
七五三当日の流れをチェック|何をするの?
参拝の時期はいつがいい?混雑を避けるポイント
七五三といえば11月15日が本来の日とされていますが、現代ではその前後1~2か月ほどの間に参拝するご家庭がほとんどです。
特に写真スタジオの予約や、神社の混雑具合を考えると「空いている日を選びたい」と思うのが正直なところですよね。
うちは土日の混雑を避けて、あえて平日に仕事を休んで家族で行ったのですが、それがもう大正解でした。
境内には人がまばらで、写真もゆったり撮れたし、なにより子どもが人の多さに疲れてしまうこともなくて、終始ニコニコでした。
子どもの体力や気分の波って、イベントの成功を大きく左右しますよね。
だからこそ「日付よりも過ごしやすさ重視」でスケジュールを組んであげると、親も子もずっと楽になれると思います。
神社でのマナーと参拝の順番を確認しよう
「初めての神社での参拝、何をどうすればいいの?」と緊張してしまう気持ち、よくわかります。
私も最初は
「お賽銭っていくら?」
「お祓いってどう受けるの?」
と頭がぐるぐるしていたのですが、当日神社で係の方が優しく案内してくださって、本当に救われました。
基本的には手水舎で手を清めてから、本殿で二礼二拍手一礼。
ご祈祷を受ける場合は社務所で受付を済ませて、案内された場所で待機します。
小さい子どもにとっては、ただ座って静かにしている時間ってすごく長く感じるんですよね。
でも、一緒に「がんばろうね」と手をつないで待っていた時間は、後から思い返すと、なんだかとても愛おしい親子の思い出になっていました。
祈祷は受けたほうがいい?費用や所要時間の目安
祈祷を受けるかどうかは自由ですが、私は「一生に一度の節目だからお願いしよう」と思って申し込みました。
初穂料は神社によって違いますが、5,000円~10,000円くらいが目安です。
祈祷自体は15分ほどで終わることが多く、そのあいだに名前を読み上げてくださったり、祝詞をあげてくださったりするのを聞いていると、
「ああ、ちゃんとこの子の成長をみんなで祝ってもらっているんだな」
と実感できて、じんときました。
静かで神聖な時間のなかで、あの頃の夜泣きやイヤイヤ期の大変さも、全部報われたような気がしたんですよね。
だからこそ、祈祷は“やるかどうか”だけじゃなく、“気持ちを整える時間”として考えてみるのもいいかもしれません。
衣装はどうする?レンタルと購入の選び方ガイド
人気の着物・袴スタイルとその特徴
七五三の晴れ姿って、親にとっても特別なご褒美みたいな瞬間ですよね。
うちの子が初めて袴を着たとき、まだ幼い顔にキリッとした表情を見せてくれて、その瞬間だけで「ああ、今日は一生の宝物になる」って思いました。
最近は伝統的な柄だけでなく、モダンで可愛い色合いやキャラクターモチーフを取り入れたデザインまであって、衣装選びだけでもかなり迷ってしまいます。
でも、選ぶときのポイントは「子どもが好きと思えるかどうか」なんですよね。
親が張り切って選んでも、本人が嫌がってしまうと当日ぐずってしまったり、せっかくの写真が泣き顔になってしまったり。
私も、最初に選んだ華やかな着物を本人が「イヤ」と拒否して、結局シンプルな色にしたんですが、それが意外と本人の雰囲気にぴったりで、結果オーライでした。
レンタルと購入、どっちがいい?メリット・デメリット比較
これはもう、かなり悩みました。
レンタルは手軽で安くて、使い終わったら返すだけというラクさがあります。
一方で、購入すれば記念として手元に残せますし、兄弟姉妹に使い回すこともできます。
私はいったん購入を考えていたのですが、よく考えたら下の子は性別も体格も違うし、実際には着回ししないかもなと思って、レンタルにしました。
結果的には正解だったと思っています。
移動中に汚してしまったり、着物の扱いに気を遣いすぎて疲れてしまったりする心配が少なかったし、撮影用・お参り用と衣装を分けられるプランも便利でした。
とはいえ「この衣装で一生の思い出を残したい」と感じるような一着に出会えたなら、購入という選択肢もとても素敵だと思います。
着付け・ヘアセットはどこまで必要?
着物って着せるのがとにかく大変そうで、初めてのときは心配でいっぱいでした。
でも実際は、写真スタジオや着付けのプロにお願いすると、子どもにも負担が少なくて、親も心の余裕が持てます。
私は自宅でやってみようとして、帯がうまく結べずにギブアップした経験があります。
笑 やっぱりプロに頼むと仕上がりもキレイですし、子どもの機嫌もよく保てるんですよね。
特に女の子のヘアセットは、本人のテンションをぐっと上げてくれる魔法みたいなもの。
鏡を見ながら嬉しそうに微笑む顔を見たとき、「ああ、今日はこの子が主役の日なんだな」って、しみじみ思いました。
記念に残る写真を撮ろう!撮影のタイミングとコツ
スタジオ撮影と出張カメラマンの違い
七五三の写真って、ただの「記録」じゃなくて、数年後に見返したときに一瞬でその日の空気や感情まで思い出させてくれるような、魔法のような力がありますよね。
だからこそ「どこで撮るか」はとても大切な選択だと思います。
うちはスタジオと迷った末、神社での出張撮影を選びました。
自然な表情を残したかったからです。
最初は「外での撮影なんて大丈夫かな」と不安でしたが、子どもが自由に動きながら笑ったり、落ち葉を拾ったりしている姿がそのまま写真に残っていて、それはそれは愛おしい思い出になりました。
一方で、スタジオは天候に左右されず、照明も安定していて衣装チェンジもスムーズ。
きちんとしたポーズでの記念撮影を希望するなら、やっぱり安心感は抜群ですよね。
どちらが正解というよりも、「どんな一日を残したいか」で選ぶのがいいんだと思います。
撮影時に子どもがぐずったらどうする?
これはもう、想像以上にあるあるです。
特に小さな子は、慣れない衣装に長時間の撮影、周りの大人たちの「ちゃんとして!」のプレッシャーで、突然スイッチが切れるように泣き出すことがあります。
うちの子も撮影の途中で「お腹すいたー!脱ぎたいー!」と大泣きしてしまって、正直私も焦りました。
でもそこで無理に「笑って!」と求めるのではなく、一度落ち着いて好きなおやつを食べさせて、「もう少しだけ頑張ってみようか」と声をかけたことで、少しずつご機嫌を取り戻してくれました。
ぐずった時間さえも含めて、今日という日が私たちの七五三だったんだなと思えたのは、後になってからです。
完璧な一枚を求めすぎずに、ありのままの子どもを残せたら、それだけで十分素敵なんですよね。
家族写真も撮る?親の服装マナーもチェック
七五三は子どもが主役の日。
でも、家族みんなで写った写真があると、あとからその価値の大きさに気づきます。
我が家も当初は「主役だけでいいよね」と思っていたのですが、フォトグラファーさんにすすめられて家族ショットも撮ってもらったら、想像以上に温かい1枚になっていて。
いまでは私のお気に入りになっています。
親の服装はスーツやセミフォーマルが基本ですが、神社や写真の雰囲気に合わせて選ぶと統一感が出て素敵です。
私は無地のワンピースにジャケットを羽織って行きましたが、子どもの着物と色合いがマッチしていて写真映えも良く、思わぬ形で記憶に残る装いになりました。
服装って、思い出の空気感をつくる大事な要素のひとつなんですよね。
当日の持ち物とスケジュールの立て方
子どもが疲れないようにするための工夫
七五三当日って、実は想像以上に子どもにとってはハードスケジュールなんですよね。
着慣れない衣装、慣れない場所、人混み、たくさんの「待ち時間」。
これだけでも小さな体には十分すぎるほどの負荷です。
だから私は、当日が近づくにつれて「大人の都合を押しつけすぎていないかな」と何度も立ち止まりました。
結果的に、予定は最低限に絞って「無理せず楽しむこと」を第一にしました。
早朝から写真、移動、神社、会食…と詰め込みすぎると、せっかくのお祝いが疲れの思い出になってしまいかねません。
あえて1日の中で「何もしない時間」もスケジュールに入れておくと、ちょっとした休憩が親にも子にも心の余裕をくれるんですよね。
雨天や体調不良のときの対応
せっかく楽しみにしていた七五三でも、当日が雨だったり、急に子どもの体調がすぐれなかったりすることって、実際あります。
私も実は、当初予定していた日は雨予報で、思い切って数日前に日程変更をしました。
正直「いまさら…」という気持ちもあったけど、延期して迎えた当日は秋晴れの青空。
無理せずに動いた自分を、あの瞬間だけはちょっとだけ褒めてあげたくなりました。
大切なのは「今日を逃したら終わり」ではなくて、「今日じゃなくてもいい」。
それができるだけで、親も気持ちに余白を持てるようになるんですよね。
忘れがちな小物・持ち物リスト
当日、「あれ持ってくるの忘れた!」が起きると、焦りと罪悪感でいっぱいになりますよね…。
私も足袋を家に忘れてしまい、撮影直前に慌てて買いに走った経験があります。
そんな自分を過去に戻ってなぐさめたいくらいでした。
だからこそ、前日までに持ち物リストを作って一度全部並べてみるのがおすすめです。
- 衣装関連の小物(足袋・腰紐・髪飾りなど)
- 予備の着替え
- 好きなおやつ
- 水分
- 絆創膏
- スマホの充電器
- ティッシュ…
準備は面倒に感じるけれど、未来の自分と子どもの笑顔を守るための“愛の仕込み”なんですよね。
よくある疑問と不安に寄り添うQ&A
数え年か満年齢、どっちでやるのが正解?
「うちの子、今3歳だけど今年やるの?それとも来年?」と、まず最初にぶつかるのがこの疑問かもしれません。
結論から言うと、どちらでも大丈夫なんです。
昔は数え年(生まれた年を1歳として数える)で行うのが一般的でしたが、今は満年齢でお祝いするご家庭も多くなっています。
我が家も悩みましたが、子どもの体力や気分を見て「本人が楽しく過ごせる年齢で祝おう」と決めました。
結果的に、ちょっと大人びた表情も撮れて、それがまた宝物になりました。
形式よりも「今のこの子にとって、無理なく心地よく過ごせるか」を基準に考えてあげると、親も気持ちがラクになりますよね。
兄弟姉妹がいる場合はどうすればいい?
もし兄弟姉妹がいると、七五三のタイミングがずれることもありますよね。
うちはちょうど年の離れたきょうだいがいて、下の子はまだお祝いの年齢じゃなかったんですが、一緒に着物を着せて記念撮影だけ参加させました。
これがまた可愛くて…!当日バタバタしていても、兄弟が並んでいるだけで絵になるんですよね。
もちろん、すべて一緒にやらなくてもいいんです。
でも、家族全員で祝う空気があると、本人の「お祝いしてもらった」という実感が深まるように感じました。
一人っ子ならではの特別感も良いし、兄弟と一緒のにぎやかさも素敵。
それぞれの家庭に合った形でいいんですよ。
両家の祖父母はどう誘う?どこまで関わってもらえばいい?
「声をかけるべき?どこまで来てもらえばいい?」と悩みやすいのが祖父母の存在です。
うちは両家ともに楽しみにしてくれていたので、撮影と参拝には一緒に行き、会食は家族だけにしました。
大切なのは
「誰が一緒にいたら、子どもにとってうれしいか」
「親にとって負担が少ないか」
というバランスかもしれません。
正直、人数が多くなると移動やスケジュール調整も大変になります。
でも、当日おじいちゃんおばあちゃんが孫を見て涙ぐんでいた姿を見ると、やっぱり呼んでよかったなって思えたんです。
無理のない範囲で、でも「来てもらってうれしかった」という思い出が残るように、できるだけ事前に相談しておくと安心です。
まとめ
七五三という行事は、ただの通過儀礼ではなく、子どものこれまでの成長をかみしめながら、これからの幸せと健やかさを願う、家族にとってとても大切な節目なんですよね。
はじめて七五三を迎える親御さんにとっては、分からないことだらけで不安もあると思います。
でも、その不安や戸惑いのひとつひとつが、子どもを思う気持ちから生まれていると考えると、それだけで胸がいっぱいになります。
当日の流れや衣装の準備、写真撮影、神社での参拝、どれも完璧じゃなくていいんです。
うまくいかないことがあっても、その日一日を家族で乗り越えた経験こそが、何年先までも心に残る思い出になります。
親としての選択に正解はありませんが、「この子のために何が心地よいか」を一番に考えたとき、きっとその七五三はかけがえのない一日になるはずです。
どうか肩の力を抜いて、家族にとっての「うちの七五三」を、大切にかたちにしていってくださいね。