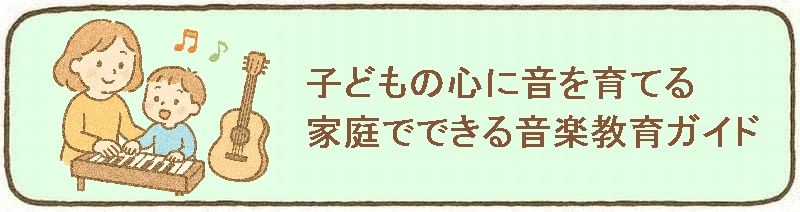「もうやめたい」その一言を初めて子どもから聞いたとき、胸の奥がズンと沈み込むような感覚がありました。
頭の中ではいくつもの思いがぐるぐる回りました。
「ここまで頑張ってきたのに」
「せっかく時間もお金もかけてきたのに」
「続けたほうがきっと将来のためになるのに」
そんな考えが押し寄せてきて、正直すぐには何も言えなかったんです。
でも一番印象に残っているのは、目の前の子どもの表情でした。
泣きそうで、でもしっかりとした目で「やめたい」と言っている姿に、ただならぬ本気を感じたのを今でもはっきり覚えています。
習い事を始めたときは、親も子どももワクワクしていました。
ピアノの音が初めて鳴ったときの笑顔、スイミングの帽子を誇らしげにかぶった姿、リズムに合わせて体を揺らすあの楽しそうな時間。
それがある日突然、「もうやめたい」という言葉に変わると、親としては戸惑うし不安にもなりますよね。
この子の将来のためにと思ってきたことだったのに、何が起きているのか、どこから気持ちが変わってしまったのか、頭の中で答えを探しても見つからなくて息が詰まるような感覚になります。
でもこの「やめたい」という気持ちは、決して悪いものではありません。
むしろ子どもが自分の心と向き合い始めているサインでもあります。
練習が嫌なのか、環境が合わないのか、成長する中で別の道を歩きたくなったのか、その背景にはその子なりの理由がちゃんとあるんです。
親にとって大切なのは、その一言の奥にある小さな気持ちをどう受け止め、どう一緒に歩んでいくかということ。
この記事では、習い事を「やめたい」と言われたときの心の揺れと向き合い方を、私自身の体験も交えながら、親の立場から丁寧に紐解いていきますね。
「もうやめたい」と言われたとき、まず大事なのは“反応しすぎないこと”
子どもがやめたがるときのよくある背景
「やめたい」と口にする子どもを前にすると、親の心には驚きや戸惑いが広がりますよね。
つい「どうして?」と問い詰めたくなったり、「ここまで頑張ってきたのに」と焦りが出てしまったり。
でも実は、その“やめたい”の裏には、いくつもの小さな感情やきっかけが積み重なっていることが多いんです。
たとえば、ある日突然練習が嫌になったわけではなくて、
「先生の言い方が怖かった」
「周りの子よりできていない気がする」
「家で注意されるのがつらい」
そんな日々の小さなストレスが、少しずつ溜まっていたのかもしれません。
子どもにとっては、自分の中でうまく処理しきれない思いがあると、それが「もうやめたい」の一言になって出てくることがあるんです。
また、身体の成長や環境の変化、学校での出来事などが影響していることもあります。
幼稚園から小学校に上がると生活リズムが大きく変わりますし、学年が上がるごとに友達関係や勉強への負担も増えていきます。
その中で「これ以上は無理かも」と感じてしまうのは、子どもにとってごく自然なことなんですよね。
子ども自身も自分の気持ちが整理できていないことがある
さらにやっかいなのは、子ども自身が自分の「やめたい理由」をうまく言葉にできていないことも多いということです。
大人のように思考を言語化して論理立てて説明するのは、子どもにとっては簡単なことではありません。
だからこそ、表面に出てくるのは
「もうやだ」
「行きたくない」
「やめたい」
といった強い感情の形だけになってしまうんですね。
実際に、私の子どもも「やめたい」と言ったとき、その理由をすぐには教えてくれませんでした。
問い詰めても黙り込んでしまって、それ以上話ができなくなったことがあります。
でもある晩、何気なく一緒にお風呂に入っていたときに、「できないときに先生が笑った気がして恥ずかしかった」とポツリと教えてくれたことがありました。
そのとき、私はようやく“やめたい”の奥にあった気持ちに触れられた気がしました。
親の焦りや不安が子どもの声をかき消してしまうことも
「もうやめたい」と言われた瞬間に、親としてはたくさんの思いが頭をよぎりますよね。
お金のこと、ここまでかけてきた時間や努力、これからの可能性。
それらが一気に心の中にあふれてきて、
「何を言ってるの」
「まだ早いよ」
「そんな簡単に決めないで」
と強い言葉で返してしまいたくなることもあるかもしれません。
でもそこで反応しすぎてしまうと、子どもは「自分の気持ちは受け止めてもらえないんだ」と感じて、心を閉ざしてしまうことがあります。
特に敏感な子どもほど、大人の顔色や口調に強く影響を受けやすく、次から本音を話さなくなってしまうこともあるんです。
子どもの「やめたい」は、単なるわがままではなく、心のどこかにある“しんどさのサイン”でもあります。
そのサインを見逃さないためにも、まずは大きく息を吸って、落ち着いて話を聞く準備を整えることが大切です。
「そう思ったんだね」と、ただそれだけをまず返す。
それだけでも、子どもの中の何かが少しずつほどけていくことがありますよ。
一度受け止めることで、親子の信頼が深まっていく
「やめたい」と言われたときに、すぐに答えを出さなきゃと焦らなくても大丈夫です。
まずは「そうか、そんなふうに感じてるんだね」と、気持ちそのものをそのまま受け止めてあげること。
これって簡単そうに見えて、実はとっても大事なことなんですよね。
子どもは、親がどういう反応をするかをよく見ています。
そして自分の言葉が大切に扱われたと感じると、それが信頼につながっていきます。
一度気持ちを受け止めてもらえた経験があると、その後も困ったことや悩みを話しやすくなるんです。
逆にそこで否定されたり、怒られたりした経験があると、自分の気持ちを閉じ込めてしまいやすくなります。
だからこそ、「やめたい」と言われたときこそが、親子の信頼関係を育てるチャンスなのかもしれません。
「受け止める」って、実はとても力強い愛情表現なんですよ。
本当に「やめたい」のかを見極めるための聞き方
「なぜ?」より「どう感じてるの?」と聞く
「なんでやめたいの?」とつい聞いてしまいたくなる気持ち、すごくよくわかります。
だけど、この“なぜ”という言葉は、子どもにとっては「理由を正しく説明しなきゃいけない」というプレッシャーにもなりがちなんですよね。
まだ気持ちが整理できていない状態の中で、突然理由を求められると、混乱したり、話すこと自体がイヤになってしまうこともあります。
だから私は、その代わりに「どんなふうに感じてるの?」と聞くようにしました。
この問いかけだと、正解を求められているような圧がなくて、子どもがそのままの気持ちを話しやすくなるんです。
「うまくできないとき、悲しい」
「友達と比べられるのがイヤだった」
そんな声がぽつりぽつりと出てきたとき、ようやく“やめたい”の意味が見えてきました。
イヤなことと続けられないことは違う
「やめたい」の背景には、ただ一時的にイヤなことがあっただけということもあります。
たとえば発表会で失敗した、先生に注意された、友達とケンカした。
こういった出来事が心に残って「もう行きたくない」に変わることもあります。
でもそれって、本当は「ちょっと休みたい」だけだったり、「もう一度気持ちを切り替える時間がほしい」だけだったりするんですよね。
それなのに、親がすぐに「やめるか続けるか」を迫ってしまうと、子どもは自分でも気づいていなかった本音にフタをしてしまうかもしれません。
だから私は、まず「イヤだったことがあるのか、それとも本当に続けたくないのか」を、ゆっくり一緒に探るようにしています。
一時的なスランプか、方向転換が必要なのかを整理する
子どもが「やめたい」と言ったとき、それがスランプの一部なのか.
それとも別の道へ進むサインなのかを見極めるには、少し時間をかけて観察することが大切です。
以前、うちの子もある日突然「もうピアノ行きたくない」と言い出して驚いたんですが.
でもよく話を聞いていくうちに、発表会前の緊張と不安が重なって、気持ちが追いつかなくなっていたんだとわかりました。
そこからは「無理に続けるか、完全にやめるか」という両極端ではなく、「少しお休みしてみる」という選択肢を作ってみました。
すると、一度気持ちをリセットできたことで、数週間後には自分から「また弾いてみたい」とピアノの前に戻ってきたんです。
このとき感じたのは、子どもの「やめたい」は決して“終わり”のサインではなくて、“気持ちの整理をしたい”というサインなのかもしれないということ。
だからこそ、問い詰めるのではなく、気持ちを一緒にたぐっていくような関わり方が大切だと思うんです。
親の「やめさせたくない気持ち」にも目を向ける
親の本音も悪者じゃない
子どもから「やめたい」と言われたとき、まず反応してしまうのは、たぶん子どもよりも親の心のほうなんですよね。
頭では「子どもの気持ちを尊重しなきゃ」と思いながらも、どこかにモヤモヤが残って苦しくなったり、「え…今さら?」と戸惑ってしまったり。
私も最初のときは、子どもに「やめたい」と言われた瞬間、自分の気持ちがグラグラ揺れてしまって、なんとも言えない寂しさやショックを感じたのを覚えています。
でもね、その感情って、決して悪いことじゃないんです。
親だって人間だし、感情があるからこそ真剣に向き合っている証拠なんですよ。
「ここまで送迎も頑張ってきたのに」
「せっかくレッスンにもお金をかけてきたのに」
そんな思いが湧いてくるのは当然のこと。
その気持ちを無理に押し殺そうとすると、あとで別の形で出てきてしまうこともあるので、まずは自分の本音にもちゃんと耳を傾けてあげてほしいんです。
「せっかく続けてきたのに」という思いとの付き合い方
何年も続けてきた習い事をやめるって、親にとっては「ここまでの積み重ねが消えてしまうような気がする」そんな感覚になることがありますよね。
でも、私はその気持ちを何度も反芻するうちに、ある日ふと気づいたんです。
それって「結果が出ないと意味がない」って思っていたから苦しかったんだなって。
だけど実際には、その過程で得た経験や時間って、もうすでに子どもの中にしっかり根付いてるんですよね。
毎日通った日々、できなかったことができるようになった喜び、泣きながらも頑張ったレッスン。
そのどれもが消えてしまうわけじゃなくて、ちゃんと心の栄養になっている。
だから私は、「やめる=失敗」と決めつけるのではなく、「今のこの子にとって次へ進むタイミングなのかもしれない」と考えてみるようにしました。
そうすると、やっと自分の気持ちに余白が生まれて、子どもの言葉を冷静に受け止められるようになったんです。
家計・時間・将来への期待も含めて整理してみよう
習い事を続けるには、親のサポートも相当なエネルギーが必要ですよね。
月謝や発表会費用、送迎や時間調整、家族のスケジュールへの影響…。
子どもが何気なく「やめたい」と言った一言の裏で、親はそれまでたくさんのものを調整してきていて、だからこそ簡単に「いいよ」と言えない気持ちもあると思います。
そしてもう一つ、言葉にはしにくいけれど、親の中にある“期待”も見逃せない要素なんですよね。
「続ければ将来の役に立つかもしれない」
「特技として武器になるかも」
「あの子は音楽に向いてるはず」
そう思っているからこそ、やめてしまうことが“可能性を閉ざす”ように感じてしまう。
だけど、その期待が親の想像の中だけでふくらみすぎてしまっていないか、一度立ち止まって整理してみることも大切です。
私はノートに
「なぜ続けてほしいと思っているのか」
「どんな未来を想像しているのか」
「どこが不安なのか」
全部書き出してみました。
そうすることで、自分の中にあった“見えない前提”に気づくことができて、そこからやっと子どもとの対話がスタートしたように感じました。
やめる・続けるを決める前に話し合いたい3つの視点
子どもの“気持ち”と“体の負担”
「やめたい」と言われたとき、親はどうしても“気持ちの問題”にばかり意識が向きがちですが、同時に
「体の疲れ」
「日々の負担」
にも目を向けてあげてほしいんです。
特に成長期の子どもは、心も体も日々変化していて、ちょっとした環境の変化でもエネルギーを使い果たしてしまうことがあります。
学校や宿題、他の習い事との兼ね合い、友達との関係。
大人が思う以上に、子どもの毎日は目に見えないプレッシャーや緊張感に満ちています。
「気持ちはまだやる気があるけど、体がついていかない」そんなとき、やめたいと感じるのは自然な反応でもあるんですよね。
私は子どもと一緒に、1週間の過ごし方を紙に書き出してみたことがあります。
「あれ?この子、こんなにスケジュール詰まってたのか」とハッとしたんです。
その瞬間、気持ちだけでなく“身体の声”にも耳を傾けてあげることの大切さを痛感しました。
家庭の状況(時間・お金・サポート体制)
習い事って、続けるにもやめるにも、親の生活に少なからず影響しますよね。
月謝や交通費、発表会の衣装代、兄弟姉妹のスケジュールとの兼ね合い。
習い事を支えているのは、実は子どもだけじゃなくて、家庭全体なんです。
うちは共働きで、送迎のたびに時間を調整したり、下の子のお世話をお願いしたりしていた時期がありました。
だから正直なところ「やめたい」と言われたとき、「助かるかも…」と思ってしまった瞬間もあったんです。
でもその気持ちを責めなくてもいいと思うんですよ。
それくらい、親にとってもエネルギーのいることなんです。
一度、家族全体の時間の使い方やお金の流れを見直してみることで、
「今は続けるタイミングなのか」
「一度休んでみてもいいのか」
が冷静に判断できる材料になります。
将来的な目的(楽しみ・特技・受験・習慣)
習い事って、そもそも「何のために始めたんだっけ?」というところに立ち返ってみることもすごく大切なんです。
最初は「音楽を楽しんでくれたらいいな」と始めたピアノが、いつの間にか
「発表会で失敗しないように」
「上の級に合格しなきゃ」
って、目標ばかりが先走ってしまっていたりすることもありますよね。
子どもと一緒に
「どうして続けたい?」
「やめたらどんな気持ち?」
と話しながら、改めて“目的”を整理してみることで、今の習い事がその目的に本当に合っているのかが見えてくることがあります。
私の子どもも、「将来のために…ってママは言うけど、私は楽しく弾けるだけでいい」とポロリと話してくれたことがありました。
その言葉を聞いて、「そうか、この子にとっては“楽しさ”がゴールだったんだな」とハッとしました。
やめるか続けるかを決める前に、「何のために?」を一緒に考えてみる時間は、きっと親子にとってすごく意味のある時間になると思いますよ。
やめるときも「ネガティブな終わり方」にしない工夫
子どもが「やってよかった」と思える形を残す
習い事をやめる決断をしたとしても、その経験が「失敗だった」「無駄だった」と子どもが思い込んでしまうのはとてももったいないことだと思うんです。
たとえ途中でやめることになっても、そこに「意味があった」と感じられる終わり方にしてあげたい。
私は、やめると決めたあとこそ、これまでのがんばりをしっかり言葉にして伝える時間を大事にしています。
「よくここまで続けたね」
「本当によく頑張ったね」
そうやって、できるだけ具体的に思い出しながら伝えるようにすると、子どもは「あ、私がやってきたことって大切にされてたんだ」と安心してくれるんです。
最後に写真を撮ったり、練習ノートを一緒に見返したりするだけでも、子どもの記憶の中に“やってよかった”という感触が残りやすくなりますよ。
先生や仲間への挨拶で経験を区切る
きちんと終わりを迎えるということは、子どもにとっても心の整理をつける大事な儀式になります。
とくに幼い子ほど、自分の中だけで気持ちを完結させることが難しいからこそ、外側の環境からしっかり区切ってあげることが大切です。
私はやめると決めたとき、「せっかくだから最後に先生にありがとうを伝えようね」と一緒に手紙を書いたことがあります。
本人は最初ちょっと恥ずかしそうでしたが、渡し終えたあとに少し誇らしげな顔をしていたのが印象的でした。
感謝の気持ちや思い出を“人と共有する”ことで、学んだ時間にちゃんと幕を下ろすことができるんですよね。
やめたあとも自己否定しない声かけのポイント
やめたあと、子どもがふとした拍子に
「やっぱり続けたほうがよかったのかな」
「私、向いてなかったのかな」
と不安をこぼすことがあります。
そういうときって、親のたった一言が子どもの自己評価に大きく影響するタイミングでもあるんですよね。
だから私は、「やめたことが悪かったんじゃなくて、ちゃんと自分で気持ちを整理して決めたことがすごいんだよ」と伝えるようにしています。
うまくいかなかった経験も、自分で決めたことも、すべてがその子の“強さ”の一部になっていく。
そう信じて、寄り添ってあげることで、やめた後も子どもは前を向きやすくなるんじゃないかなと思うんです。
「やめる=失敗」じゃない。親子の関係を育てるチャンスに
途中でやめた経験が子どもの自己効力感を育てることもある
「続けることに意味がある」
「途中で投げ出すのはよくない」
そう信じてきた私たち大人にとって、“やめる”という選択肢には、どこかネガティブな響きがあるかもしれません。
でも実は、途中でやめたという経験そのものが、子どもにとって大切な“選ぶ力”を育てることにつながるんです。
私の子どももある習い事をやめたとき、「自分で決めたんだ」という実感をすごく大切にしていたように思います。
「あのときはがんばったけど、やめたことにも意味があった」と自分で言った姿には、少しの誇らしささえ感じられました。
親がどうこう言うよりも、自分で自分の選択に納得できることって、すごく大きな力になるんだなと気づかされた瞬間でした。
「続ける強さ」と同じくらい「やめる勇気」も大事
習い事を続ける力は、もちろん素晴らしいことです。
でも「やめたい」と感じたときに、それを言葉にすること、その気持ちに向き合って自分で判断することって、実はすごく勇気のいることなんですよね。
私はそのとき、子どもの「やめたい」を聞いて、どこかで“逃げ”だと思いたくなる自分がいたのを感じていました。
でも、冷静に振り返ってみたら、「この子は、ちゃんと自分の限界や心の声に気づいて、それを伝えてきたんだ」と思えたんです。
やめることは、ただの放棄じゃなくて、“ちゃんと自分を見つめた”という行動でもあるんだと、改めて思いました。
「逃げること」と「方向転換すること」は、まったく違うんですよね。
新しい挑戦に進むための心の整理を一緒にしよう
習い事をやめたからといって、それで終わりじゃないし、人生の道が閉ざされるわけでもありません。
むしろ、そこから新しい興味が芽生えたり、「今度はこれをやってみたい」と前を向けるきっかけになることだってあるんです。
でもそのためには、「やめたあと」をどう過ごすかがすごく大切になってきます。
やめたことをマイナスの記憶にしないように、親としてできるのは
「次は何が楽しそう?」
「またやりたいことが出てきたら応援するね」
と声をかけてあげること。
私は、子どもと一緒に“やめたあとにやってみたいことリスト”をノートに書き出してみたんです。
「お菓子作り」
「英語」
「ダンス…」
どれも最初は気まぐれだったけど、そこから小さな「やってみたい」が新しい挑戦につながっていきました。
やめることは“終わり”じゃなくて、親子でまた新しい扉を開ける合図かもしれません。
その扉を開ける鍵を、子どもが自分の手で持てるように、そっと隣で見守ってあげられるといいですよね。
まとめ
「もうやめたい」と子どもに言われたとき、親としては本当にいろんな感情が揺さぶられますよね。
驚きや戸惑い、焦り、そしてほんの少しの寂しさや不安。
その全部を抱えたまま、子どもの前で笑顔でいようとする自分が、ちょっと苦しくなる瞬間もあるかもしれません。
でも、やめたいという言葉の裏には、子どもなりの真剣な気持ちや葛藤があることが多いんです。
そしてその声をまっすぐに聞こうとする姿勢そのものが、何よりも大切な“親の愛情”なんだと思います。
続けることがすべてじゃないし、やめることが悪いことでもありません。
どちらを選ぶにしても、親子で丁寧に話し合って一緒に考えて決めた時間は、きっと子どもにとっても「自分の気持ちを大事にしてもらえた」という安心感として残っていきます。
やめたとしても、そこまで頑張ってきた日々が消えるわけじゃありません。
その経験はちゃんと子どもの中に積み重なっていて、これからの人生の土台になっていくものです。
私自身、子どもと
「何度も話し合って」
「迷って」
「揺れて」
でも最終的にはお互いに納得して前を向けたとき、習い事そのものよりも「この子とちゃんと向き合えた」という実感が、なによりも大きな宝物になりました。
どうか、今まさに悩んでいるあなたも、自分の気持ちも子どもの気持ちも否定せず、ゆっくりでいいので一緒に答えを探していってくださいね。
それはきっと、親子にとってかけがえのない時間になるはずです。