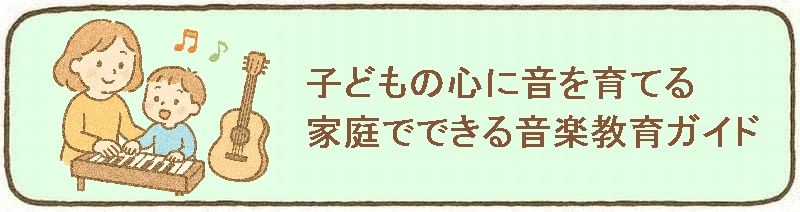「うちの子、吹奏楽をやってみたいって言い出したんです」
ある日、学校から帰ってきた我が子が、ちょっとだけ照れたような顔をしながらそう話した瞬間、胸の奥がじんわりとあたたかくなりました。
新しい世界に踏み出そうとするその目の輝きに、思わず笑顔になったのを今でも覚えています。
でもその一方で、心の中には小さな不安がいくつも浮かんできました。
どんな楽器を選べばいいのかな、家庭での練習はどうすればいいのかな、ちゃんと続けられるのかなと考えると、期待と同じくらいの不安がじわじわと広がっていったのです。
吹奏楽の世界は、一度足を踏み入れると、子どもの成長と深く関わっていく特別なものになります。
ただ音楽を学ぶだけではなく、自分で練習時間をつくる力や仲間と協力する経験、努力を積み重ねて得られる達成感など、たくさんの学びが詰まっているんです。
私自身、最初は「楽器を吹くって難しそう」「途中で投げ出さないかな」と心配ばかりでした。
でも練習を重ねるうちに、子どもの表情が少しずつ変わっていきました。
音が出たときの笑顔や、うまくいかなくて涙ぐんだときの悔しそうな顔を見ているうちに、これは単なる習いごとじゃなくて、心を育てる時間なんだと気づいたんです。
親としての役割は、何かを強制することでも、先回りして完璧に準備してあげることでもありません。
大切なのは、子どもの「やってみたい」という気持ちを信じて、そっと背中を押してあげることです。
最初は小さな一歩かもしれません。
でもその一歩が、やがて大きな自信へとつながっていきますよ。
音楽のある毎日が、親子にとってかけがえのない時間になることを、私は身をもって実感しました。
小学生が吹奏楽に興味を持ったら|親が最初に知っておきたいこと
「やってみたい!」の気持ちは、成長のサインかもしれません
小学生の子どもが「吹奏楽をやってみたい」と言い出したとき、まず大切にしてほしいのは、その一言の裏側にある「自分で挑戦したい」という前向きな気持ちです。
音楽が好きという気持ちだけではなく、友達と何かを一緒にやりたいという思いや、自分の世界を広げてみたいという欲求が隠れていることもあります。
それは決して「ただの気まぐれ」ではないんですよね。
親としては、「本当に続くのかな」「途中で飽きないかな」といった不安がよぎるのも当然です。
だけど、最初から「どうせ無理でしょ」と決めつけてしまうより、「そうなんだ、やってみたいんだね」とまずは受け止めてあげることが、子どもにとって安心できる大きな一歩になりますよ。
吹奏楽ってどんな活動?親も知っておくと安心です
吹奏楽と聞くと、トランペットやフルートなどの楽器を思い浮かべる方が多いかもしれません。
でも実際の活動はもっと幅広くて、音を出す練習だけでなく
「合奏での協調性」
「譜面を読む力」
「演奏会での経験」
など、多面的な学びが詰まっています。
学校のクラブ活動の一環として行われていることもあれば、地域のジュニア吹奏楽団に参加するケースもあります。
活動頻度や方針はそれぞれ異なるため、どんな形での参加なのか、最初にしっかり確認しておくといいですよ。
「毎週土曜日は練習がある」といったスケジュールの見通しが立っているだけでも、家庭のリズムが崩れにくくなりますし、親の心構えも整いやすくなります。
「うちの子に向いてるのかな?」と思ったときに考えてほしいこと
楽器の演奏というと、何となく
「音楽が得意な子じゃないと無理なのかな」
「器用じゃないと難しいかも」
と思ってしまいがちですよね。
けれど、実際には多くの子が初めて楽器に触れ、少しずつ音が出せるようになって、段階的にステップアップしていきます。
うちの子も最初は楽譜なんて全然読めなかったし、リコーダーだってうまく吹けてなかったんです。
それでも、自分でやりたいと思った気持ちを支え続けたことで、気づけば音楽室で堂々と演奏する姿を見ることができました。
向いているかどうかは、やってみなければわからないもの。
最初は苦戦することもあるけれど、そこを一緒に乗り越えていけるのが、吹奏楽の魅力でもあるんです。
だからこそ、「向いてないかも」と感じたとしても、それはあくまで“今の状態”であって、未来の可能性を狭めるものではないんですよ。
親としてのかかわり方は「手を出しすぎない」ことも大事です
吹奏楽は、技術も必要ですし、ある程度の継続力も求められる活動です。
だからといって、親がついつい口を出しすぎたり、練習を強制したりしてしまうと、子どもはかえって気持ちがしぼんでしまうこともあるんですよね。
うちでも一度、練習を見ながら「なんでそんな吹き方してるの?違うでしょ?」と言ってしまったことがあって、そのあと子どもがしばらく楽器を触らなくなってしまったことがありました。
あのときは本当に反省しました。
子どもにとって大切なのは、「上手になること」よりも「楽しめていること」。
そのベースがあってこそ、技術も自然と身についてくるんです。
親は見守る立場として、励ましと安心を与える存在でいてあげることが、長く続けるための何よりの支えになりますよ。
まずは情報を集めて、選択肢を一緒に考えていきましょう
吹奏楽を始めるにあたっては、
「どの団体に所属するのか」
「どんな楽器を選ぶのか」
「どれくらいの費用がかかるのか」
など、気になることがたくさん出てくると思います。
親としては、焦らずに一つひとつの選択肢を丁寧に調べて、必要なら体験会や説明会に足を運んでみるのもいいですね。
「どうせうちには無理かも」と思っていたことが、意外にも「あ、これならできそう」と感じられるかもしれません。
そして何より、「子どもが自分で選ぶ」という経験を大切にしてあげてください。
自分の選んだ楽器、自分の決めた活動であるという実感が、継続の力にもなります。
親ができるのは、その選択をサポートして、一緒にワクワクしながらスタートを切ること。
そこに温かな気持ちがあれば、きっと素敵な吹奏楽ライフが始まりますよ。
性格や体格で変わる!子どもに合った楽器の選び方
「どの楽器が向いてる?」は正解がひとつじゃないんです
吹奏楽を始めるときに、最初にぶつかる悩みのひとつが「どの楽器を選べばいいのか」ということですよね。
「フルート」
「クラリネット」
「サックス」
「トランペット」
「トロンボーン」
「ユーフォニアム」
「チューバ」
「ホルン」
「打楽器」……
ひとつひとつが魅力的で、それぞれ音色や雰囲気もまったく違って見えます。
うちの子が最初に「やってみたい」と言ったのは、友達がやっていたからという理由でトランペット。
でも実際に音を出してみたら「これ難しい……」としょんぼりしてしまって、そこから少し悩んだ時期がありました。
それでも、先生のすすめで試したクラリネットの音に「これ好きかも」と目を輝かせたのを見たとき、この経験自体がもう大切な第一歩だったんだなと実感したんです。
楽器選びに「絶対の正解」はないんですよね。
向き不向きよりも、実際に触れて、音を出して、「これ楽しいな」と思えたものを選べるかどうかが大切なんです。
最初は気軽に「いろいろ試してみようか」で大丈夫ですよ。
体格や歯の状態が気になるときはどうしたらいい?
小学生のうちは、体も小さくてまだ発育の途中。
楽器の重さや持ち方、口の形などが気になることもあるかもしれません。
特に
「前歯が抜けてるけど大丈夫かな」
「小柄だけどトロンボーンって持てるの?」
なんて不安、けっこう多いんですよね。
でも、実際の現場では、小さな体でもしっかり楽器を楽しんでいる子どもたちがたくさんいます。
学校や教室によっては、体格に応じてパーツを調整したり、補助アイテムを使ったりすることで無理なく続けられるようにサポートしてくれるところもあります。
大切なのは、「無理に理想の形に合わせる」ことじゃなくて、「今のその子に合った方法を見つけていく」ことなんですよ。
心配なときは、先生や経験者に相談してみるだけでも、きっと安心できるはずです。
性格と楽器の相性ってあるの?
「うちの子、恥ずかしがり屋なんだけど大丈夫かな」
「マイペースだから合奏でやっていけるのかな」
そんな声もよく聞きます。
実は楽器には、それぞれ性格との“相性”のようなものがあるとも言われています。
たとえば、静かで集中力のある子はクラリネットやフルートに安心感を感じやすいことがあります。
表現力のある子や明るくエネルギッシュな子はサックスやトランペットでのびのびと自分を出せることもあるんですよ。
でもそれはあくまで“傾向”であって、どの性格でもどの楽器でも続けていくうちに不思議と馴染んでいくものです。
うちの子も最初は「絶対に人前に立ちたくない」って言っていたけど、今では演奏会でソロを吹くのが楽しみになっています。
性格は、楽器を通じて変わっていくことだってあるんです。
だからこそ、最初から「向いてないかも」と思い込まずに、「一度やってみようかな」くらいの気持ちで見守ってあげてほしいなって思います。
“やってみたい”を優先することで生まれる力
何よりも大切にしてあげたいのは、子ども自身が「これをやってみたい」と思う気持ちです。
理屈や条件よりも、本人が「なんかいいな」と心が動いた瞬間って、本当に大きな力を持っているんですよね。
うまくいかない日があっても、「好きだからもうちょっとだけがんばってみる」が生まれるのは、その“好き”の気持ちがあるから。
親としては心配や先回りの気持ちもたくさん出てくるけど、
「一緒に選んだね」
「一緒に悩んだね」
そうやって振り返れる時間こそ、あとでかけがえのない思い出になっていきます。
楽器との出会いは、まるで小さな運命みたいなものです。
だから、少しだけ遠回りしても、最後に「この楽器に出会えてよかったね」って笑えるように、今はそっと背中を押してあげてくださいね。
買う?借りる?家庭に合った楽器の準備方法
「最初から買う」はちょっと待っても大丈夫
吹奏楽を始めるとき、親としてすぐに浮かぶのが「楽器って買うべきなのかな?」という悩みですよね。
新品の楽器は種類によっては数万円から十数万円以上するものもあって、「せっかく買っても続かなかったらどうしよう」と不安になるのも当然です。
実は、最初から購入しないという選択肢もちゃんとあるんですよ。
学校や地域の団体によっては、楽器を貸し出してくれるところもありますし、音楽教室によっては入会中にレンタルできる制度が整っていることもあります。
我が家も、最初の一年はレンタルから始めました。
「うちの子、本当にやりたいと思っているのかな」と心配だったんですが、毎週の練習を楽しみにしている姿を見て、「ああ、これは続けられるかもしれない」と思えたんです。
その段階を踏んだことで、本人も自分の楽器がほしいという気持ちがしっかり芽生えてきて、買ったときは本当に大事にしてくれるようになりました。
無理に最初から高額な買い物をしなくても、段階を踏むことで納得して選べるようになるんですよ。
レンタル楽器のメリットと注意点
レンタルの魅力は、初期費用がぐっと抑えられることにありますよね。
子どもが「やっぱり違う楽器がいいかも」と思い直したときにも、比較的柔軟に対応できるのが大きなメリットです。
ただ、使い込まれたものだと、少し音の出しにくさがあったり、メンテナンスが不十分な場合もあるので、借りる前には必ず状態を確認しておくと安心ですよ。
とくに小学生の場合、楽器との「最初の出会い」がすごく大事なんです。
最初に吹いた楽器でいい音が出せたり、持ちやすかったりすると、それだけで自信につながって「もっとやってみたい!」という気持ちがぐんと大きくなるからです。
逆に、音がうまく出なかったり調整が必要な状態だと、「あれ、私には向いてないのかな」と落ち込んでしまうこともあるんです。
だからこそ、レンタルを検討するときには、楽器のメンテナンスがしっかりしているところを選ぶことが大切です。
子どもが「これならできそう」と思える状態かどうかも確認してあげてくださいね。
中古楽器を選ぶときのポイント
費用を抑えつつ、自分の楽器が持てるという点で中古楽器も人気があります。
状態のよい中古品なら、新品に比べて手頃な価格で手に入りやすく、愛着も持ちやすいというメリットがあるんですよね。
ただし、「安いからラッキー!」と即決してしまうのはちょっと危険です。
実際、ネット通販やフリマアプリなどでも楽器は出品されていますが、メンテナンス歴や細かいパーツの劣化具合などは、素人にはわかりにくいことが多いんです。
うちでも一度、ネットで購入しようかと迷ったことがあったんですが、楽器店の方に相談したところ、
「見えない内部の状態が悪いと、演奏に大きく影響するから注意が必要」
とアドバイスをいただいて、実店舗で試奏してから購入しました。
できれば信頼できる楽器専門店や、学校や団体と提携している店舗で見てもらうと安心ですよ。
「試奏できるか」「保証がついているか」などをチェックしておけば、初めての楽器選びもぐんと心強くなります。
「自分の楽器」だからこそ大切にできる気持ち
やっぱり、自分の楽器を手にしたときの子どもの顔って特別なんです。
レンタルや借り物のときとは違う、ちょっと誇らしげな、でも大切にしなきゃという責任感のようなものが表情ににじむんですよね。
その気持ちが、毎日の練習を頑張る原動力にもつながっていきます。
とはいえ、親としては予算や環境とのバランスも大事ですし、無理なく、その子にとってちょうどよい方法を一緒に見つけていくことがいちばん大切です。
「これからも一緒に頑張っていこうね」と、楽器と出会ったあの日の気持ちを忘れずに歩んでいけたら素敵ですね。
練習初期のつまずきを防ぐ!親子で楽しむコツ
「音が出ない…」は誰もが通るはじめの壁
初めて楽器を手にした子どもが直面しやすいのが、「音が出ない」という壁です。
大人から見ればちょっとしたことでも、子どもにとっては
「なんで…」
「自分にはできないのかな」
と思い詰めてしまうほどの大きなつまずきになることもあるんですよね。
我が家でも、最初にマウスピースをくわえてみたものの、全然音が出なくてうなだれている子どもの姿を見て、「ああ、これは気持ちのサポートが必要だな」って感じたことがありました。
練習がうまくいかないときに、ただ「頑張れ」と励ますだけでは届かないことってあるんですよね。
そんなときは、
「誰でも最初は音が出ないものだよ」
「音が出るようになったら、きっとすごくうれしくなるよ」
と、一緒に未来の楽しみをイメージしながら声をかけてあげると、子どもは少しずつ前向きな気持ちを取り戻していきますよ。
毎日の練習、どう続ける?習慣化のヒント
練習って、やっぱり“続ける”ことがいちばん難しいですよね。
小学生の子どもにとって、学校の宿題や遊びたい気持ちとのバランスを取りながら、毎日楽器に向き合うのは簡単ではありません。
でも、「ちゃんと30分やらせなきゃ」と思い込むと、かえって親子で疲れてしまうこともあるんです。
うちでは、最初のうちは「5分でいいから音を出してみようか」と声をかけることから始めました。
「練習しなさい」ではなく、「今日も音を聞かせてくれる?」というように、誘い方を少し変えるだけで、子どもの反応も優しくなることがあるんです。
習慣にしていくには、無理のないリズムと、成功体験を積ませてあげることがとても大切です。
少し音が出た、昨日より長く吹けた、それだけでも「やった!」と思える気持ちが、次の練習につながっていきますよ。
音が大きい?ご近所が気になるときの工夫
家での練習で意外と多いのが、「音が響いてしまって気まずい」という悩みです。
特に集合住宅だと、「ご近所に迷惑じゃないかな…」と気をつかうことも多くなりますよね。
そういうときは、時間帯を調整するだけでもだいぶ変わります。
「夕方の16時~18時頃に少しだけ」と決めておくだけで、ご近所トラブルを避けられることもあるんですよ。
さらに、消音アイテムやミュートと呼ばれる器具を使えば、音をぐっと小さくできる楽器もあります。
また、最近では「お風呂場で練習してます」というご家庭もあって、防音性の高い空間をうまく活用する工夫も広がっています。
大事なのは、「うるさくて迷惑かも」ではなく、「どうすればお互い気持ちよく過ごせるかな?」と前向きに考えてみることです。
親がそんなふうに向き合う姿を見て、子ども自身も音楽との付き合い方を学んでいけるのかもしれませんね。
練習が「楽しい!」と思えるようになるには
やっぱり練習を続けるには、「楽しい」と感じられることがいちばん大切です。
どれだけ上達のために必要でも、子どもが「つまらない」「苦しい」と思ってしまったら、続けるのは難しくなってしまいますよね。
うちでは、簡単なごほうびを用意したり、「今日の演奏、すごく良かったよ」と具体的に褒めることを意識したりして、楽しめる工夫をいろいろ試してきました。
ときには家族の前で“おうち発表会”を開いて、拍手喝采を浴びることで子どもがすごく自信を持てるようになったこともありました。
「楽器がうまくなること」ももちろん大事だけど、「音楽ってやっぱり楽しいな」って思える瞬間をたくさん積み重ねていくことが、いちばんの原動力になるんですよね。
だからこそ、うまくできない日も、ちょっとサボりたくなる日も、丸ごと含めて“親子で楽しむ時間”にしていけたら、それがきっといちばんの成長につながっていきますよ。
「もうやめたい…」を乗り越える親の関わり方
どんな子でも一度は「やめたい」と思う瞬間がある
吹奏楽を始めたばかりの頃は、新しいことばかりでワクワクしていた子どもでも、ある日突然「もうやめたい」と言い出すことがあります。
これは決してめずらしいことではなくて、どんな子でも一度は経験する“心の揺れ”なんですよね。
うちの子もそうでした。
発表会の直前にうまく吹けなくて、練習のたびにイライラして「もうやだ…」と涙をこぼしたことがありました。
その姿を見たとき、親としては「なんて声をかければいいのか」「ここで無理に続けさせていいのか」とすごく悩んだのを覚えています。
でも、そういうときこそ親の出番なんですよね。
大切なのは、すぐに結論を出すことじゃなくて、その子の気持ちにちゃんと寄り添うこと。
「やめたいと思うくらい頑張ってきたんだね」
「苦しいって思えるほど真剣だったんだよね」
そうやって、まずはその思いをまるごと受け止めてあげることが何より大切なんです。
失敗や挫折は、成長のチャンスになる
「やめたい」と感じる背景には、失敗やうまくいかない経験があることが多いです。
でもその壁にぶつかったとき、どう受け止めるかで子どもの成長は大きく変わってくるんですよね。
うちの子の場合も、「みんなみたいにうまくできない」「恥ずかしい」という気持ちが根っこにありました。
でも、ひとつずつ小さな成功体験を重ねていくうちに、「やめたい」から「もう少し頑張ってみようかな」に変わっていったんです。
親は、そうした“気持ちの揺れ”に寄り添って、一緒に乗り越える存在でいてあげたいですね。
上手くいかない日があっても、そこにいるだけで
「見てくれてる人がいる」
「応援してくれてる人がいる」
そう思えることが、子どもにとっては大きな安心感につながるんです。
「やらせなきゃ」じゃなく「一緒に見守る」の気持ちで
つい、「せっかく始めたんだから続けさせなきゃ」と思ってしまうことってありますよね。
でも、音楽は義務になった瞬間に、楽しさや本来の意味を失ってしまうものです。
だからこそ、続けるかどうかにこだわりすぎずに、「この子がどうしたいと思っているのか」に耳を傾けてあげることがとても大切です。
親としては、不安や焦りを感じることもあるけれど、それでも「あなたの気持ちを大事にするよ」と伝えることで、子ども自身が「信じてもらえている」と感じられるんです。
そうやって自分の気持ちに向き合えるようになると、不思議とまた一歩進む力が湧いてくることがありますよ。
うちの子も、あのとき「やめたい」と言ったことで、一度立ち止まり、自分の気持ちを整理できたからこそ、その後さらに音楽が好きになれたのかもしれません。
「続けてよかった」と思える日はきっと来る
いったん「やめたい」と思った経験も、あとになって振り返ると、「あのときがあったから今がある」と思える大切な時間だったりするんですよね。
我が家でも、あの苦しい時期を経て、演奏会の本番で堂々と演奏する姿を見たとき、「やめさせなくてよかったな」と心から思いました。
あのときの一言、あの夜の会話、あの抱きしめた瞬間が、全部つながって今があるんだなと感じたんです。
だからこそ、つまずいたときにどう関わるかが、その子の吹奏楽人生を決めるくらい大きな意味を持つんだと思います。
今まさに悩んでいるお子さんと向き合っているあなたへ。
「大丈夫、きっと大きな成長につながる日が来るよ」って、心から伝えたいです。
焦らずに、ゆっくりと、見守っていきましょうね。
まとめ|「上手になる」よりも「楽しむ」を大切に
吹奏楽を始めるとき、親としてはつい
「上達してほしい」
「長く続けてくれたらいいな」
なんて期待をしてしまうものですよね。
でも、最初の一歩で大切なのは、“結果”ではなく“気持ち”なんです。
子どもが「やってみたい」と思ったその瞬間に寄り添ってあげること。
そして最初のつまずきや迷いの中でも「楽しさ」を見失わずにいられるように、そっと支えてあげることが何よりのサポートになるんですよ。
楽器を選ぶことも、練習を始めることも、時には「向いてるのかな」「このまま続けられるかな」と不安になることもあります。
でも、そのたびに親が
「大丈夫だよ」
「楽しめたらそれで十分だよ」
と声をかけてあげられることで、子どもは安心して“自分のペース”で音楽と向き合っていけるようになります。
我が家でも、
- 音が出なかった日
- やめたいと泣いた日
- 発表会の帰り道に「楽しかった!」と笑った日
あの頃の気持ちがあったから、今の子どもがいる。
そう思える日がきっと、あなたのご家庭にもやってくると思います。
吹奏楽は、ただの習いごとではなくて、子どもの心を育ててくれる時間です。
そしてそれは、親子で共有できる宝物のような時間でもあります。
だからこそ、「上手にやらなきゃ」じゃなくて、「今日も楽しかったね」と笑い合える日々を、どうか大切にしていってくださいね。
音楽が、親子の心をつなぐきっかけになってくれることを、心から願っています。