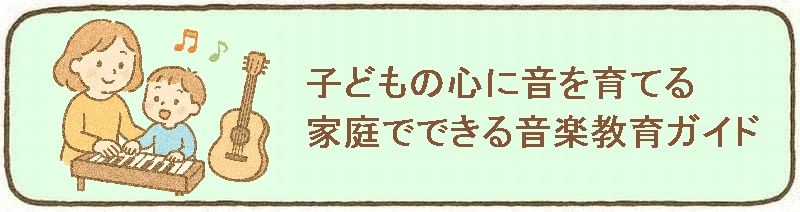ピアノの練習の時間になると、どうしてあんなに家の空気が張りつめてしまうんでしょうね。
さっきまで笑顔だったのに「練習しなさい」という一言をきっかけに空気がピリッと変わって、子どもはうつむき、親はイライラが募っていく。
あの独特の重たい空気を経験したことがある人って、実はとても多いんです。
私もその一人でした。
大切なはずの習い事が、気づけば親子ゲンカの引き金になってしまっていて、練習時間が近づくだけで心の中にじわっと緊張が走るようになっていました。
怒鳴りたくないのに声が大きくなってしまったり、ため息をついてしまったり、自分でもどうしたらいいのかわからなくなって、夜になってからこっそり涙ぐんでしまうこともありました。
けれど本当は、子どもも同じように戸惑っているんですよね。
「やりたくない」と反発しているように見える姿の裏には、思うように弾けないもどかしさや、叱られるのが怖い気持ちが隠れていることもあります。
練習そのものよりも、親子の気持ちがぶつかる構図がしんどさを生んでしまうのです。
この記事では、そんな練習タイムを少しずつ笑顔の時間に変えていくための声かけや褒め方のコツについて、私自身の体験や実感もまじえながらお話ししていきますね。
完璧な親である必要なんてないし、最初の一歩はほんの小さな工夫からで十分です。
緊張ばかりだった時間が、親子の絆を育てるあたたかな時間に変わっていくきっかけを、一緒に見つけていきましょう。
なぜ練習で親子ゲンカが起こってしまうの?
「やる気がない」ように見えても、実はちがうかも
子どもが練習を嫌がると、つい「やる気がないだけ」と思ってしまいがちですが、本当はその奥にさまざまな感情や葛藤が隠れていることが多いんです。
たとえば、うまくできないことへの悔しさだったり、自信が持てないことへの不安だったり、あるいは「怒られるかもしれない」という予感が先に立って手が止まってしまうこともあります。
大人の目には「サボっているように見える態度」でも、子どもにとっては心の中でぐるぐると気持ちが渦巻いている状態なのかもしれません。
私自身も、娘が鍵盤の前でうつむいて固まっていたとき「なに黙ってるの?やらないなら片づけるよ」と突き放すように言ってしまったことがあります。
でもそのあと、小さな声で「なんか、できないのがイヤなの」と呟いた姿に、思わずハッとさせられました。
やる気がないわけじゃなかった。
ただ、できない自分に向き合うのがしんどかっただけだったんです。
親の期待と子どもの本音がすれ違うとき
親としては「上達してほしい」「せっかく習っているんだから続けてほしい」という思いがありますよね。
それは子どもを思うからこその願いです。
でもその想いが、いつのまにかプレッシャーとしてのしかかってしまうこともあります。
子どもは子どもで、もっと遊びたい気持ちや自分のペースでやりたい気持ちを抱えていて、けれどそれをうまく言葉にできなくて、つい反抗的な態度になってしまう。
どちらかが間違っているわけじゃないのに、気持ちがすれ違って、ぶつかってしまう。
そんなときに生まれるのが「練習をめぐる親子ゲンカ」なのかもしれません。
子どもは「叱られる未来」を先に感じてしまうことがある
練習を始める前から、すでに顔が曇っているときってありませんか?
あれは、過去に叱られた記憶や緊張感が、心の中に染みついてしまっている証拠かもしれません。
「できなかったら怒られるかも」
「ちゃんとできないとまた言われる」
そんな思いが先に立って、鍵盤に向かう前からもう気持ちが固まってしまっている。
子どもにとっては、練習が「音楽を楽しむ時間」ではなく「叱られるリスクのある時間」に感じられている場合もあるんです。
そうなると、始める前から気が重くなって、ますます練習がイヤになってしまうという悪循環に陥りやすくなります。
親のイライラは「大切にしたい想い」があるからこそ
一方で、親の側にも「ちゃんとやってほしい」「できれば楽しんでほしい」という切実な気持ちがあります。
ただのイライラじゃなくて、そこには子どもの成長を願う気持ちや、自分ができる限りサポートしたいという想いがあるからこそ、怒りや焦りに変わってしまうんですよね。
「なんでやらないの?」と問い詰めたくなる瞬間も、本当は「あなたならできるって信じてるよ」という裏返しだったりします。
でもその想いがうまく伝わらないと、子どもはただ責められたと感じてしまい、心を閉ざしてしまいます。
だからこそ、親の感情にも少し余裕が必要で、その余裕を持つための工夫がとても大事になってきます。
「練習の時間」が親子の関係そのものを映し出してしまうことも
練習の時間は、実は親子の距離感や信頼関係がそのまま表れる時間でもあります。
ちょっとした言葉や表情に敏感に反応したり、「わかってくれない」と思う気持ちが募ったり。
ふだんのやりとり以上に、お互いの気持ちがぶつかりやすい場面なんですよね。
逆に言えば、ここを少しずつほぐしていくことで、親子の関係自体が深まりやすいとも言えます。
ケンカになるたびに落ち込んでしまうかもしれませんが、それは「関わろうとしている証拠」でもありますよ。
このように、練習をめぐる親子ゲンカの背景には、単純なやる気の問題ではなく親と子のすれ違いや思いの強さが関係していることが多いんです。
だからこそ、まずは「なんでやらないの?」と責めるよりも、「どんな気持ちでいるのかな」と子どもの心をそっとのぞいてみることが大切なのかもしれません。
そして、親自身も「怒ってしまう自分」を責めすぎずに、できることから少しずつ整えていく。
そんな小さな積み重ねが、ケンカを減らす大きな一歩になっていきますよ。
「また怒っちゃった…」親自身もつらい気持ちに寄り添って
完璧な親じゃなくていいんですよ
「また怒ってしまった…」その一言が頭の中をぐるぐる回って、夜になっても気持ちが晴れなかったこと、ありませんか?私はあります。
子どもにあたった自分が情けなくなって、自己嫌悪でいっぱいになって、寝顔を見ながらこっそり涙ぐんだ夜もありました。
でも、そんなときふと思ったんです。
完璧な親なんて、きっとこの世に一人もいないんじゃないかなって。
怒ってしまうのは、どうでもいい相手じゃなくて、大切にしたい相手だから。
つい言いすぎてしまうのは、子どものことを本気で想っているからこそ。
そうやって感情が動く自分を、もう少しやさしく見てあげてもいいのかもしれませんよ。
自分を責めすぎないことが第一歩
「怒ってしまった=ダメな親」と決めつける必要なんてないんです。
大事なのは、そのあとどう向き合うか。
たとえば「さっきは言いすぎちゃった、ごめんね」と伝えることだって、子どもとの信頼関係を深める大きな一歩になります。
むしろ、親が素直に謝る姿を見せることは、子どもにとって
「感情って整理できるものなんだ」
「謝るってカッコ悪くないんだ」
という安心感にもつながっていきます。
私も「ごめんね」と口にするのが怖かったときがありました。
でも、勇気を出して伝えてみたら、娘の顔がふっとやわらかくなって、そのとき初めて「謝っても親でいられるんだ」と思えたんです。
親が気持ちを整えるためにできること
子どもと向き合う前に、まずは自分の心をちょっと整えておくこともすごく大切です。
忙しい中でも、練習前に一呼吸置いたり、お茶をひとくち飲んだり、ほんの小さなことで心の余裕って変わってきますよ。
私の場合は、子どもがピアノに向かう前に、窓を開けて空気を入れ替えるようにしています。
たったそれだけでも、自分の中のざわつきがすっと落ち着いてくるんです。
「落ち着いて接しよう」と思う前に、自分の中にスペースを作ってあげると、自然と声のトーンもやわらかくなって、言葉の選び方も変わっていきます。
「自分のための時間」もちゃんと持っていい
そして何よりも伝えたいのは、あなたが「自分のためだけに使う時間」もきちんと確保していいんだよということです。
「子どものこと」
「家のこと」
「仕事のこと」
全部を抱えて毎日を回しているあなたは、本当にすごい。
でも、だからこそときどきガス抜きが必要なんです。
たとえば一人でお風呂に入る時間をちょっと長くするとか、夜に好きなドラマを一話だけ見るとか、友達にLINEを一通だけ送るとか。
そんな何気ない時間が、あなた自身を癒してくれて、また明日子どもと向き合う力になってくれますよ。
怒ってしまった自分を責めるよりも、
「疲れてたんだな」
「それくらい気持ちが動いてたんだな」
そうやって少しだけ自分に寄り添ってみる。
そうすることで、心のギュッと固まった部分が少しずつほぐれていきます。
怒りをゼロにするのではなく、怒っても大丈夫だと思える自分でいること。
それが、親自身を救ってくれる優しさにつながっていきますよ。
ケンカを減らす声かけのコツは「伝え方」より「受け止め方」
命令口調より、問いかけや共感を意識してみよう
「早く練習しなさい」
「もう始める時間でしょ」
そんな風に声をかけた瞬間、子どもの顔がムスッとこわばってしまった経験、きっと誰にでもありますよね。
私も何度もありました。
口調が強くなるのは、親の側に「やらなきゃ」という焦りがあるから。
でも、子どもにとってはそれがプレッシャーになって、やる気をますます奪ってしまうことがあるんです。
そんなとき、
「今日はどこから練習してみようか?」
「ちょっとだけ一緒にやってみる?」
そんなふうに問いかけに変えてみると、ふっと空気がやわらかくなるのを感じられることがありますよ。
子どもは命令に動くよりも、対話の中で「自分が選んだ」と感じることでスッと前に進めることがあるんです。
「なんでできないの?」から「一緒に考えようか」へ
できないことが続くと、つい「どうしてできないの?」と詰めてしまいたくなる。
でもその言葉って、子どもを責める言葉として心に残ってしまうことがあるんですよね。
私もある日、「どうしてまた間違えたの?」と娘に言ってしまったことがありました。
そのときの娘の顔、今でも忘れられません。
口をつぐんで、何も言わずに下を向いて、小さく震えていたんです。
言った私自身も胸が苦しくなって、後悔ばかりが残りました。
そのあと、「ここ難しかったね。どうしたら弾きやすくなるかな?」と一緒に考える形に変えてみたら、娘の目が少しだけ上を向いて、「うーん…じゃあ、ゆっくり弾いてみようかな」って言ってくれたんです。
答えを引き出すんじゃなくて、一緒に探していく。
その姿勢が、親子の緊張をほぐしてくれるんですよ。
ネガティブな言葉をやわらかく変換するテクニック
「またできてないじゃん」
「早くして」
「何回言わせるの」
こういった言葉は、つい口をついて出てしまいがち。
でも、ちょっと言い方を変えるだけで、子どもの受け取り方は大きく変わっていきます。
たとえば、「まだできてないね」ではなく「ここ、あとちょっとで完成しそうだね」とか。
「早くして」ではなく「そろそろ始められそうかな?」と声をかけてみると、言葉のトゲが取れて子どもも素直になりやすいんです。
私も意識して言い換えるようになってから、娘とのぶつかり合いがぐんと減りました。
言葉って、それだけで空気を変える力があるんですよね。
子どもが安心できる“受け止める姿勢”を意識して
子どもがやりたくなさそうにしているとき、すぐに
「怠けてる」
「集中力がない」
と判断してしまうと、見えてこないものがあります。
実はその奥に「今日は学校でイヤなことがあった」とか「体がちょっとだるい」とか、言葉にできない理由が潜んでいることもあるんですよね。
だからこそ、まずは「やりたくないのかもしれない」という目で見て、「そっか、なんか今日は気がのらないんだね」と受け止めてみる。
たったそれだけの言葉で、子どもは「わかってもらえた」と感じて、少しずつ心をひらいてくれます。
練習を進める前に、まず気持ちを受け止めてあげる。
そこが親子関係の土台になっていくんですよ。
「どう伝えるか」よりも、「どう受け取ってあげるか」。
その視点に立ってみると、練習の時間の意味が少しずつ変わってきます。
子どもを動かすための言葉ではなく、気持ちをそっと受け止める言葉を選ぶだけで、親子の間にあった見えない壁がゆっくりほどけていく。
その変化を、あなた自身の目で感じていってくださいね。
子どもが前向きになれる「褒め方」のポイント
結果じゃなく“努力のプロセス”を見てあげて
「うまく弾けたからすごいね」「間違えなかったから偉いね」そんなふうに結果に目を向けた褒め方、ついしてしまいがちですよね。
もちろん成果を認めることも大切。
でも、子どもが本当に必要としているのは「どこをがんばったか」「どんな気持ちで取り組んだか」に気づいてもらうことなんです。
たとえば、
「昨日より少し長くピアノの前に座れていた」
「苦手なフレーズを何度も挑戦していた」
そういう“目には見えにくい小さな努力”を言葉にして伝えると、子どもは「ちゃんと見てくれてるんだ」と感じられて、自信が育っていきますよ。
私も以前、ミスをしなかったことばかりを褒めていた時期がありました。
でもそれでは、失敗した日は全部が台無しみたいに感じてしまうんですよね。
だからこそ
「今日もあきらめずに弾いてたね」
「難しいところも最後までやってたね」
と努力を見つけることを意識するようになってから、娘の表情がぐんとやわらかくなりました。
できないときこそ「見守る勇気」が子どもを育てる
子どもがうまくいかずに悩んでいるとき、つい口を出したくなってしまいますよね。
「こうすればできるのに」と教えたくなったり、「なんでできないの」と言いたくなったり。
でも、できない時間もまた大事な成長の一部なんです。
私も「手を出さない」ってこんなに難しいことなんだと、何度も痛感しました。
でもある日、「ちょっと黙って見守ってみよう」と思って静かに座っていたら、娘が自分なりに工夫して乗り越えた瞬間があって。
そのときの「できた!」の笑顔は、今でも忘れられません。
見守るって、放っておくこととは違います。
すぐそばにいて、いつでも助けられる状態でそっと見つめること。
そういう安心感が、子どもに挑戦する勇気を与えるんですよ。
兄弟姉妹がいるときは比較ではなく個性を尊重して
兄弟姉妹がいると、どうしても「お兄ちゃんはこうだったのに」とか「妹の方が集中力がある」とか、比べてしまいがち。
でもそれって、子どもたちにとってはとてもつらいことなんですよね。
私自身も、無意識に比較するような言い方をしてしまって、あとから「あの子を否定したような気がする」と落ち込んだことがあります。
どの子にも、それぞれのテンポと得意不得意があって、それがその子の色。
だから
「あなたはこういうところが素敵だね」
「この前より、ここが上手になってきたね」
と、その子自身の変化や魅力に目を向けるようにしていくと、子どもは自分を信じられるようになります。
比べられた記憶ではなく、自分らしさを認めてもらえた実感が、子どもの心にあたたかく残っていくんですよ。
褒めることって、簡単そうで実はとても奥が深いんですよね。
だからこそ大切なのは、「何を褒めるか」よりも「どんな気持ちで見ているか」。
子どもが前向きになれる褒め方は、日々の小さな変化に気づいてあげるところから始まります。
「今日もがんばってるね」そう声をかけられた子どもは、その言葉を力にしてまた一歩進んでいけるんです。
今日からできる!親子の練習タイムを笑顔に変える工夫
毎日の声かけに使える“やわらか言葉”例
「練習の時間だよ」と言うだけでも、子どもにとっては圧のある言葉に聞こえてしまうことがあります。
まだ遊びたい気持ちが残っていたり、うまく弾ける自信がなかったりすると。
その一言が“始まりの合図”じゃなく“プレッシャーの号令”に聞こえてしまうこともあるんですよね。
そんなときは、
「そろそろ指を動かしてみる?」
「ちょっとだけ一緒に音出してみようか」
など、やさしく気持ちを向ける声かけに変えてみるだけで、子どもの反応はぐっとやわらかくなります。
私自身も、以前は「さっさとやって!」と急かしてばかりでした。
でも、ある日「ここから弾いてみようか、ママも隣で聴いてるね」と言ってみたら、娘がふっと笑って「じゃあこの部分だけね」と素直に始めてくれたんです。
その小さな成功体験が、私の声かけの自信にもつながりました。
タイムスケジュールのゆとりが親子を救ってくれる
毎日の生活の中で「早くしなさい」「もう◯時でしょ」と急かしてばかりになると、親も子もどんどん心が削られていきます。
練習の時間を確保するために、他のことをきっちり詰め込んでしまうと、ちょっとしたズレで全てが崩れてイライラが爆発してしまうんですよね。
だからこそ、少し余裕のあるスケジュールを意識することがとても大事です。
「30分きっちりやらせる」ことよりも、「10分気持ちよく終えられる」ほうが、親子にとってはずっと意味のある時間になることもあります。
うちでは、練習後に「今日はこれだけできたねシール」を一緒に貼るようにしたら、娘が自分から「今日は何分に始めようかな」と決めるようになりました。
時間を管理するのは親じゃなくて、子ども自身が「自分でできた」と感じられる工夫があると、練習の印象が変わっていきますよ。
習い事と上手につき合うための家族のルールづくり
練習をするたびに親子でぶつかってしまうなら、そもそもの“ルール”を家族みんなで見直してみるのもひとつの方法です。
「毎日◯分やる」という決まりを無理に守るよりも、「その日の気分や疲れ具合に合わせて、できる範囲でいいよ」と緩やかな枠を作るだけで、子どもが安心して取り組めるようになります。
我が家では
「やらなかった日があっても責めない」
「できた日は自分でごほうびシールを選べる」
というゆるめのルールを取り入れています。
それだけで親も「できなかった=失敗」と思いすぎずに済むようになって、気持ちに余裕が生まれました。
練習が続くことよりも、「続けたいと思える空気」があることのほうが、ずっと大切なんだと気づけたんです。
親子の練習タイムがつらい時間になるのか、それとも心が通い合う時間になるのかは、実はちょっとした工夫で大きく変わっていきます。
完璧なやり方を探すよりも、今日できる“小さな心がけ”を少しずつ積み重ねていく。
その姿勢が、子どもにとっても、そして親にとっても、練習の時間を少しずつやさしいものに変えていってくれますよ。
さいごに|「やらせる」より「一緒に育つ」気持ちで
親子の練習時間は、ただの“課題”じゃないんです
ピアノや習い事の練習って、つい
「ちゃんとやらせなきゃ」
「サボらせちゃいけない」
そう思ってしまいがちですよね。
私もそうでした。
毎日のように、
「またふざけてる」
「なんで集中しないの」
そうやってイライラしてばかりで、そのたびに罪悪感でいっぱいになって、寝る前に子どもの寝顔を見ながら何度も反省してきました。
でも、そんな日々を繰り返す中で気づいたのは、練習の時間ってただの“課題”じゃないということでした。
そこには、子どもが「できない自分」と向き合っていくプロセスがあって、親はそのそばにいて一緒に悩んだり、喜んだりできる。
そういう時間だったんだって、少しずつ実感できるようになったんです。
うまくいかない時間も、かけがえのない“親子の営み”
練習で泣いた日も、怒ってしまった日も、実はあとから振り返ると「ちゃんと向き合っていた証」だったと気づけることがあります。
「やらなかった」「怒ってしまった」そんなマイナスの記憶が、ふとした瞬間に笑い話になる日が来たりするんです。
うまくいかなかったあのときの空気さえも、いつか子どもが成長したときに「あれがあったから頑張れたのかもしれない」と思える日がくる。
そう信じて、今この瞬間の揺れや葛藤を受けとめていけたら、それだけで十分“ちゃんとやっている”って言えるんじゃないかと思うんです。
親もまた、子どもと一緒に育っていけるんですよ
子どもが練習で少しずつ成長していくように、親もまた、その姿に触れながら一緒に育っていけるんです。
「前はすぐ怒ってたけど、今日はちょっとだけ待てたな」
「今日は言い方を変えてみたら、うまく伝わったかも」
そんな些細な変化の積み重ねが、親自身の成長でもあるんですよね。
完璧じゃなくていいし、うまくいかない日があってもいいんです。
大切なのは「この子と向き合おう」と思っている気持ち。
それがある限り、親としての歩みは、いつだって前に進んでいますよ。
「やらせる」のではなく、「一緒に歩く」「一緒に育つ」
そんな視点を少し持ってみるだけで、毎日の練習時間が少しずつ、あたたかくて豊かなものに変わっていきます。
今日もうまくいかないことがあったとしても、それは“失敗”じゃなくて、成長へのひとつの途中経過。
そう思えるようになったとき、きっとあなたの心も、子どもの心も、もっと軽やかに動き出していくはずです。
焦らなくて大丈夫。
あなたの歩幅で、一歩ずつ進んでいきましょうね。
まとめ
練習をめぐる親子の時間って、本当は音を奏でるだけのものじゃないんですよね。
「子どもが少しずつ自分と向き合いながら挑戦していく姿」
「親がその後ろ姿を見守りながら時に戸惑い、悩み、それでも手を差し伸べていく姿」
そこには、言葉にしきれない感情や関係性がぎゅっと詰まっている気がします。
「また怒ってしまった」「やってくれないことにイライラする」そんな経験を重ねる中で、自分が親としてダメなんじゃないかって不安になる日もあるかもしれません。
でもね、それだけ“向き合っている証拠”なんです。
怒ったって、泣いたって、それでもまた子どものそばに戻ろうとしているあなたは、もう立派に親として頑張っているんですよ。
声かけの工夫、褒め方の視点、スケジュールの見直し、ほんの小さなことでも、毎日の積み重ねで親子の関係は変わっていきます。
完璧じゃなくていい。
失敗してもいい。
ただ「この子のために何かしたい」という気持ちを、どうか大事にしてほしいなと思います。
あなたのその優しさが、いつか子どもの心に“安心”として残っていく。
今は見えなくても、それはちゃんと育っていっていますよ。
今日からできることを、ひとつずつ。
焦らず、自分のペースで大丈夫。
そんなあなたを、私は心から応援していますね。