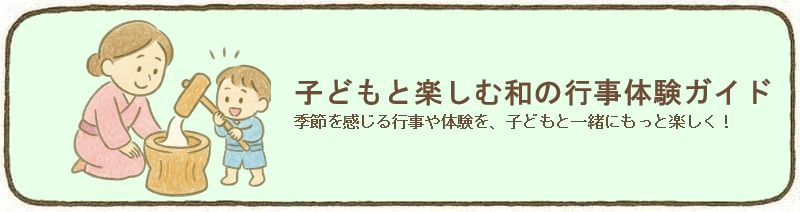節分が近づくと、スーパーに並ぶ福豆や鬼のお面に子どもが目を輝かせたり、「鬼って本当に来るの?」とソワソワしはじめたり。
そんな微笑ましい季節の訪れを感じるご家庭も多いのではないでしょうか。
節分は単なる豆まきイベントではなく、昔から「邪気を払い、福を呼び込む」大切な年中行事として受け継がれてきました。
けれど、いざ子どもと一緒に節分を迎えようとすると
「豆を投げていいの?」
「小さい子に豆を持たせても大丈夫?」
「手作りお面ってどうやって作るの?」
といった不安や疑問も出てくるんですよね。
私自身も娘が小さかった頃、「怖がらせずに楽しませるにはどうすればいいんだろう」と悩みながら準備したのをよく覚えています。
この記事では、節分の由来をやさしく伝える方法や、年齢に合わせた安全な豆まきの工夫、そして子どもと一緒に笑顔で楽しめる手作りお面のアイデアまで、実体験も交えて丁寧にご紹介していきます。
行事の本質にふれながら、親子で安心して楽しい時間が過ごせるようなヒントをお届けしますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
節分はどんな行事?子どもと一緒に楽しむ意味を知ろう
節分ってなに?その起源と意味をやさしく解説
節分とは、もともと「季節を分ける」という意味を持つ言葉で、本来は立春・立夏・立秋・立冬の前日すべてを指していたんですよ。
その中でも特に、春の始まりとされる立春の前日は“新しい一年の始まり”という意味合いが強く、現代ではこの日が「節分」として定着しています。
冬から春へと季節が切り替わるときは、昔の人たちにとって“体調を崩しやすい”とか“邪気が入り込みやすい”とされたタイミング。
そこで、無病息災を願って「鬼=邪気」を追い払い、「福=良い気」を家に招き入れる行事として、豆まきの風習が根付いたんですね。
子どもにもわかるように「鬼」と「豆」の意味を伝えよう
子どもに「なんで鬼に豆を投げるの?」と聞かれたとき、大人が難しい話を始めてしまうと、せっかくの行事が“おもしろくないもの”になってしまいかねません。
私が娘に伝えたのは、「鬼っていうのは、怒りっぽい気持ちや、泣き虫な心のことでもあるんだよ」という話でした。
実際、「ママの中にも怖い鬼がいるときあるね」と笑いながら話したら、「じゃあママにも豆投げる~!」と爆笑されました。
子どもたちにとって鬼が“完全な悪者”ではなく、自分の心の中にも潜んでいるかもしれない存在だと知ることで。
節分がただの豆まきイベントではなく、自分ごととして体験できる行事になると思うんです。
豆まきは「遊び」じゃなくて「家族の気持ちを整える時間」
つい忘れがちなんですが、節分って「遊び」ではないんですよね。
家族みんなが一つの空間で、声をそろえて「鬼は外、福は内」と言いながら豆をまく。
それって、ある意味“儀式”なんです。
私自身、子どものころに母が「心の鬼を追い出すんだよ」と言ってくれたあの声を、今でもふと思い出します。
ただお面をかぶって豆を投げるだけじゃなくて、その時間の中で
「今年も元気に過ごせますように」
「家族みんなが笑っていられますように」
という気持ちを込めること。
それが本当の“節分の体験”なのかもしれませんね。
子どもと一緒に季節を感じることで、記憶に残る行事になる
スーパーで福豆や恵方巻が並び始めたり、テレビで節分特集が流れるこの時期に、ただ行事をこなすのではなくて、「今日は節分だね、一緒に豆まこうか」と子どもに声をかけること。
そんな小さなひとことが、子どもの中に「ああ、うちの家族は行事を大切にしてたな」という温かい記憶として残っていくんですよね。
体験って、あとから思い出したときに“匂いや音や笑い声”まで蘇るから不思議です。
今年の節分も、そんなふうに“心に残る一日”にできたら素敵ですね。
豆まきの準備|安全に楽しむために気をつけたいこと
年齢別の豆の選び方は?幼児には“まき豆”の工夫を
豆まきと聞くと「炒った大豆を手に持って思い切りまく!」というイメージを持つ方も多いかもしれません。
でも、小さなお子さんがいる家庭では、ちょっとした工夫が必要です。
大豆は硬くて小さいので、誤飲やのど詰まりのリスクがあります。
特に3歳以下の子どもには、節分専用の“まき豆”として市販されているソフトタイプの小袋入り豆や、お菓子の小袋を代用するのも一つの手です。
我が家でも2歳のときには、落としても危なくないようにボーロを使って豆まきごっこをしました。
「えいっ!」と嬉しそうに投げていて、その笑顔を見たら「行事ってこういう安心感も大事だな」としみじみ思ったんです。
まき方にもひと工夫!安全と楽しさを両立させよう
豆をまくとき、ついつい夢中になってしまって「思いっきり投げちゃう!」という子もいますよね。
うちの娘も最初はフルスイングで投げていて、棚の上の小物を倒しかけたことがありました。
そこで我が家では、豆まきのルールを「優しくポーンって転がすくらい」と決めました。
それだけで雰囲気がガラリと変わって、「楽しいけど危なくない」空間を作れました。
特にリビングなど物が多い部屋では、あらかじめ安全な“まきスペース”を決めておくといいですよ。
豆が飛び散りやすい床には新聞紙やレジャーシートを敷くのもおすすめです。
後片付けもラクになりますし、子どもと一緒に「ここからここまでが鬼退治ゾーンだね」って決めると、行事に参加するワクワク感も高まります。
集合住宅ではご近所配慮も忘れずに
豆まきって“家の外にまくもの”というイメージがありますが、マンションやアパートでは近隣への配慮も大切になります。
ベランダや玄関先で豆をまくと、下の階に落ちてしまったり、鳥や虫を引き寄せてしまうことも。
実際に知人が「翌日、共用廊下に豆が残っていて苦情があった」と話していたことがありました。
そうならないためにも、窓を閉めた室内での豆まきや、袋入りのお菓子をまいて後で一緒に拾うスタイルなど、工夫することで気持ちよく行事を楽しめます。
「ここは静かにやろうね」「終わったらすぐお掃除ね」とあらかじめ子どもと話しておくことも大切です。
行事のたびに「思いやり」を教えられるって、親としても嬉しい機会ですよね。
親子で楽しむお面づくり|鬼や福の神になりきろう
お面づくりは節分の“入口”になる体験
節分の豆まきって、実は「豆をまく前」が一番盛り上がるんですよね。
我が家ではいつも、豆まきの数日前から「今年はどんな鬼のお面を作る?」という会話が始まります。
工作が好きな娘にとっては、お面づくりそのものがひとつのイベント。
特に子どもにとっては、「自分が作ったもので家族が笑ってくれる」というのが本当に嬉しいみたいで。
お面づくりの時間がそのまま、節分を“自分の行事”として受け入れるきっかけになるんです。
紙皿・画用紙・紙袋で作れる!簡単素材で十分
準備に気合いを入れなくても大丈夫。
使うのは家にあるもので十分です。
紙皿に穴を開けて、画用紙で眉毛や角をペタペタ貼りつけるだけでも立派なお面になりますし、紙袋をかぶって穴を開ける“覆面タイプ”も、意外と盛り上がります。
「顔の見えない鬼なんてこわ~い!」と笑い合いながら、親子で顔のパーツを相談して決める時間が、じわじわ楽しいんですよね。
自由なデコレーションで“自分だけの鬼”をつくろう
子どもの創造力って本当にすごくて、「赤い鬼じゃなくて、水色のやさしい鬼がいい」とか、「キラキラした星の目にする」とか、毎年こちらの予想を軽く超えてきます。
シールやマスキングテープ、クレヨン、綿、アルミホイルなど、なんでもアリでOK。
完成したらぜひ「名前」も付けてあげてください。
我が家では「もふもふおにちゃん」が家族の人気者になりました。
お面をつけてポーズをとって写真を撮るだけでも、節分の思い出がぐんと濃くなります。
かぶったときの安全対策も忘れずに
「せっかく作ったお面がズレちゃった」
「かぶったら前が見えない」
そんなことになってしまうと、子どもにとっては不安やストレスになってしまいます。
特に小さな子には、頭にしっかり固定できるように、ゴムの長さや紙の厚みを調整したり、目の穴の位置を工夫してあげたりすると安心です。
おでこやほっぺに直接当たる部分には、ティッシュや綿を貼って肌を守るのもおすすめです。
安全に楽しく過ごすためのひと手間は、きっと“またやりたい!”につながりますよ。
豆まきのやり方と声かけのヒント
「鬼は外!」の掛け声で、心の中の鬼も一緒に追い出そう
節分といえば「鬼は外、福は内!」の掛け声ですよね。
だけど、ただ言うだけじゃなくて、そこに意味を込めて伝えると、ぐっと行事の奥行きが深まります。
我が家では、豆をまくときに
「怒りんぼ鬼さん出ていけー!」
「おなか痛くなる鬼さんバイバイ!」
と、子ども自身が感じている“イヤな気持ち”を言葉にして投げるようにしてみました。
すると「そっか、自分の中にも鬼がいるのかも」と気づいた娘が、「泣き虫鬼もバイバーイ!」って笑顔で叫んでいて、なんだか胸が熱くなったんです。
ただの行事を“心の整理”にもつなげていけるって、すごく尊い時間ですよね。
年齢に合わせた“怖がらせすぎない”工夫をしよう
節分の定番「鬼の登場」ですが、年齢によってはトラウマになってしまうこともあります。
とくに未就園児~幼児期は、“本物の鬼が来る”と思い込んで本気で泣き出してしまうこともありますよね。
だから我が家では、パパが鬼役をするときには、あらかじめこっそり「ちょっとやさしめで頼むよ」と伝えておきました。
マスクもお面もせず、帽子と手ぬぐいだけで軽く変装するくらいにして。
「鬼さん、そんなにこわくないかも…」という距離感にしておいたら、娘はむしろニコニコしながら豆をぶつけていて大盛り上がりでした。
怖さよりも“楽しかった!”の記憶が残るようにする工夫、大事だなって思います。
家族で役割分担すると思い出がもっと深くなる
豆を投げる子、鬼役のパパ、豆を拾う係、声かけをするママ…と家族で役割を決めて行うと、自然と笑いが生まれてきます。
我が家では「今年の鬼はママ!」と子どもが決めた年があって、新聞紙の丸めた豆を本気でぶつけてきた娘の満面の笑みに「やられた~!」と私も大げさに倒れてあげたら、もうゲラゲラ大爆笑でした。
後から写真や動画を見返して、「あの年はママ鬼だったよね~」と話題になるのも、家族の宝物になります。
片付けまでが節分の大切な時間に
豆まきの後の片付けって、ついつい親が全部やってしまいがち。
でも、「拾うのもゲームみたいにすればいいかも?」とひらめいてからは、「誰が一番たくさん拾えるかな選手権~!」と声をかけて、家族みんなで豆拾いをしています。
片付けの時間まで笑顔で終われると、「節分=楽しい行事」って子どもの中にも定着していきますし、何より親の負担も減って助かりますよね。
節分の夜に伝えたい“ちょっとした話”で行事がもっと深まる
恵方巻や福豆にこめられた「食べる意味」を伝えてみよう
豆まきが終わったあとの夜ごはん、みなさんはどうしていますか?我が家では毎年「恵方巻」と「福豆」を囲みながら、節分の締めくくりをしています。
ただ食べるだけじゃなくて、「どうしてこれを食べるのか」という話を添えるだけで、子どもたちの表情がちょっと真剣になる瞬間があるんですよね。
たとえば、「恵方巻を恵方を向いて無言で食べると願いが叶うんだって」と伝えると、口をムギュッと結んで真剣に食べる姿が可愛すぎて、つい笑ってしまいました。
福豆も「歳の数だけ食べると病気をしないって言われてるよ」と話すと、「じゃあ来年はもっと食べられるね!」と目を輝かせていました。
食べ物にまつわる意味って、子どもにとっては“特別なごはん”に変わる魔法みたいなものなんですよね。
地域によって違う節分の風習を話題にしてみよう
節分の風習って、実は地域によって少しずつ違うんですよね。
私の実家では、玄関にいわしの頭とヒイラギの枝を飾る「やいかがし」の風習がありました。
でも夫の地元ではそんなこと一度もやったことがないそうで、「そんな怖い飾り知らなかった!」と笑っていたことがあります。
こうした“地域の違い”を話すと、子どもにとっては「同じ日本でも色々あるんだね」と視野が広がる機会になるんですよ。
祖父母に「昔はどうしてた?」と電話して聞いてみるのもおすすめです。
世代を超えたつながりが感じられる瞬間、親としてもあたたかい気持ちになりますよね。
鬼は悪者じゃない?心に残るメッセージを添えて
「鬼ってこわいもの」「悪いことをする存在」…そんなイメージがあるかもしれません。
でも最近では、鬼を単なる“悪役”として追い払うだけでなく、
「自分の中の弱い気持ち」
「ちょっと困った性格」
として捉えてみるという考え方も広がってきています。
娘と節分について話していたとき、「ママの中にもイライラ鬼がいるんじゃない?」と真顔で言われたことがありました。
その一言でドキッとして、「そうか、自分の中の鬼とも向き合わなきゃいけないのは親も同じなんだな」と気づかされました。
節分の夜、ふとしたタイミングで「どんな鬼を追い出したい?」と聞いてみると、子どもの心の中にある不安やモヤモヤを、ほんの少しだけ言葉にしてくれるかもしれません。
まとめ|豆まきとお面づくりで親子の季節の思い出を残そう
節分は、ただ豆をまいて終わりのイベントではありませんよね。
そこには、「一年を健康に過ごせますように」「心の中のイヤな気持ちも一緒に外へ出せますように」という、家族の願いがしっかり込められていると感じます。
子どもにとっては、鬼のお面を作ったり、福豆を頬ばったり、家族でわいわい騒いだりするその一つひとつの体験が、日常とはちがう“特別な思い出”になっていきます。
だからこそ、年齢に応じた豆の選び方や、安全に楽しむ工夫、鬼のとらえ方、地域ごとの風習まで含めて、親としてしっかり寄り添ってあげたいなと思うんです。
完璧じゃなくていいんです。
ちょっと不器用でも、笑いながら鬼のお面を作ったり、豆を投げて転がったり、最後にお片付けして一緒に食卓を囲んだり。
そんな“ふつうの家庭の節分”こそが、子どもの心にずっと残る温かな記憶になりますよ。
今年の節分は、豆とお面と少しのユーモアと、たっぷりの愛情を用意して、親子で楽しんでみてくださいね。