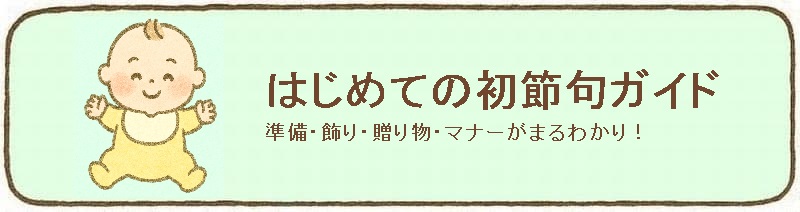初節句といえば、赤ちゃんの健やかな成長や幸せを願う大切な行事です。
桃の節句や端午の節句は、日本に古くから伝わる季節の節目でもあり、家族で赤ちゃんの無事な成長を喜ぶ大切なタイミングとなっています。
ただ最近は、「お祝いの食事会って、やらなきゃいけないのかな?」「両家を呼んで盛大にやるべき?」と悩むご家庭も増えてきました。
特に育児中のママやパパにとっては、準備や段取りの負担が大きく、せっかくの初節句なのに疲れてしまった…という声も聞こえてきます。
赤ちゃんの体調や家族のスケジュール、さらにはコロナ禍での集まりに対する配慮など、家庭ごとに事情はさまざまです。
この記事では、「初節句にあえて食事会をしない」という選択に焦点を当て、その背景や考え方、さらに代わりにできるあたたかなお祝い方法について、わかりやすくご紹介していきます。
ご家庭に合った、無理のない形で大切な節句の日をお祝いするヒントになればうれしいです。
初節句に食事会をしないのは非常識?
そもそも「初節句」とはどんな行事?
初節句とは、赤ちゃんが生まれてから初めて迎える節句行事のことを指します。
男の子の場合は5月5日の端午の節句、女の子の場合は3月3日の桃の節句がそれにあたります。
それぞれ、
- 男の子には兜や鯉のぼり
- 女の子には雛人形を飾る
この初節句は、昔から「子どもが無事に育ってくれたことへの感謝」と「これからの健康と幸せを祈る」気持ちを込めて行われてきました。
地域によっては神社にお参りしたり、お赤飯を炊いたりと、さまざまな祝い方があります。
最近では写真スタジオで記念撮影をするご家庭も多く、昔ながらの風習と現代的なスタイルが混在しているのも特徴です。
昔と今で違う?食事会の位置づけの変化
ひと昔前までは、初節句といえば親族一同が集まり、料理を囲んでお祝いするのが当たり前のように行われていました。
祖父母をはじめ親戚を招待し、手料理や仕出し弁当で盛大に祝うというスタイルが一般的だったのです。
ですが最近では、家族構成の変化や生活スタイルの多様化が進んだこともあり、こうした大規模な食事会は必須ではないという認識が広がってきました。
特に共働き家庭や、育児に忙しい時期のママ・パパにとっては「準備や対応が大変」と感じるケースも多く、自分たちのタイミングとスタイルでコンパクトに祝いたいというニーズが増えてきています。
また、親族間の距離が遠くなっていたり、気軽に集まりにくい事情があったりすることで、「集まること」にこだわらない祝い方が当たり前になりつつあるのも現代的な傾向です。
実際にやらない家庭も増えている理由とは
食事会をしないと決める家庭が増えてきている背景には、さまざまな事情があります。
まず多く挙げられるのが、赤ちゃんやママの体調面への配慮です。
特に産後間もないタイミングでの初節句だと、まだ生活のリズムが整っていなかったり、外出や長時間の来客が負担になったりすることも。
さらに、食事会の準備や段取りが大変という声も多く聞かれます。
料理の手配や部屋の片付け、親族への連絡など、やることは意外とたくさんあるんですよね。
育児に追われるなかでその負担を感じてしまい、「やらない」という選択をする人が増えているのは自然な流れといえるでしょう。
加えて、日程調整が難しい、親族との関係に気を使うのがストレスになる、といった理由から、あえて行わないという判断をするケースも多いです。
無理して開催するより、心身にゆとりを持って家族だけで静かにお祝いした方が、赤ちゃんにとってもママやパパにとっても心地よく過ごせるという考え方が、いまの時代に合っているのかもしれません。
初節句のお祝い=食事会という考え方に縛られなくても大丈夫
無理に開催しない方がいいケース
赤ちゃんがまだ夜泣きや授乳で落ち着かない時期だったり、ママ自身が産後の疲れから回復していなかったりする場合は、無理して食事会を開く必要はまったくありません。
特に初節句は、出産からそれほど日が経っていないことも多く、家族みんながまだ新しい生活リズムに慣れていない時期でもあります。
例えば、
- 夜泣きで寝不足が続いていたり
- 授乳のタイミングが安定していなかったり
また、赤ちゃんにとっても知らない人がたくさん集まる環境は刺激が強すぎて、ぐずってしまうこともあるかもしれません。
こうした状況では、食事会という形式にこだわらず、自宅で家族だけでゆったりと過ごすだけでも、十分に素敵な初節句になります。
無理をせず、赤ちゃんとパパママが心地よく過ごせる形を優先していいんですよ。
祖父母や親族に角が立たない伝え方
「今年は家族だけで静かに過ごしたいと思っていて…」「体調を見ながらお祝いの形を考えています」といった、やわらかく丁寧な言い回しで伝えると、相手も受け入れやすくなります。
ポイントは、あくまでも“感謝の気持ち”を添えて話すことです。
たとえば
ただ、赤ちゃんの生活リズムがまだ安定していないので、今回は家族だけでゆっくりとお祝いさせていただこうと思っています
事前に写真を送ったり、あとから内祝いを贈るなど、気持ちを形にする工夫を添えるのもおすすめです。
会えなくても、心はちゃんと伝わりますよ。
両家で意見が違うときの上手な調整方法
片方の親族が「ちゃんとした食事会で初節句を祝いたい」と希望する一方で、もう片方の親族が「そこまでしなくてもいい」と思っていると、夫婦の間でも板挟みになってしまうことがありますよね。
そんなときは、まず両家に同じように事情を伝え、どちらか一方に偏らないようにすることが大切です。
「どちらの気持ちもわかるけれど、今回は赤ちゃんの体調と私たちの生活を優先して、こういう形でお祝いさせてもらいたい」と伝えると、誠実さが伝わります。
さらに「後日、写真や動画を送るからね」「落ち着いたら改めて顔を見せに行きます」といったフォローの言葉を添えることで、相手の期待をやわらげることができます。
実際に会うタイミングをずらすことで、より心に余裕を持ったお祝いができることもありますよ。
食事会の代わりにできるお祝いアイデア
自宅で写真撮影+ごちそうで思い出づくり
せっかくの初節句なので、自宅でお祝い膳を囲んで写真を撮るだけでも、思い出に残る立派なお祝いになります。
最近では、特別な料理を用意しなくても、お赤飯やちらし寿司、簡単な手作りケーキなど、ちょっとした工夫で「お祝い感」を演出する家庭も増えています。
また、雛人形や兜などの飾りを背景にして、赤ちゃんに衣装を着せて写真を撮ると、まるで写真館で撮ったような素敵な記念になります。
スマホでも十分きれいに撮れる時代なので、自宅で「写真館ごっこ」をするのも楽しいですよ。
ガーランドや手作りの飾りを使ってオリジナルのフォトブースを作るのもおすすめです。
さらに、こうした写真を後日フォトブックにしたり、祖父母へのプレゼントにしたりすると、喜ばれること間違いなしです。
内祝いを贈って感謝の気持ちを伝える
食事会を開かなくても、お祝いをいただいた方には内祝いをお返しして感謝の気持ちをしっかり伝えることが大切です。
内祝いの品は、日用品やお菓子など相手に気を遣わせない範囲で選ぶと好印象ですし、赤ちゃんの名前入りグッズや写真入りのメッセージカードを添えることで、より心がこもった贈り物になります。
また、内祝いに添えるメッセージ文も、「このたびは初節句のお祝いをありがとうございました。
おかげさまで健やかに成長しています」といった一言があるだけで、気持ちがしっかり伝わりますよ。
郵送での対応もできますので、遠方の親族にも失礼のない形で感謝を届けられます。
オンライン報告も◎最近のスマートな方法
遠方に住んでいたり、感染症の影響や体調面で直接会うのが難しいときは、オンラインでの報告も今どきのスマートな選択肢です。
LINEビデオ通話やZoomなどを使って、短時間でも顔を見ながら「こんなふうにお祝いしました」と伝えるだけで、きちんと気持ちは届きます。
あらかじめ写真を共有しておいたり、簡単な動画を撮って送ったりすると、相手も状況を理解しやすくなります。
「次会えるのを楽しみにしています」と一言添えれば、会えない時間もあたたかくつながれますよ。
オンラインでのやりとりは、相手の都合に合わせて時間を調整しやすいというメリットもあるので、気軽な方法としてぜひ取り入れてみてください。
初節句を無理なく祝うために大切なこと
赤ちゃんと家族の体調・都合を最優先に
お祝いごとはもちろん大切ですが、何よりも優先すべきなのは赤ちゃんと家族の体調や都合です。
特に赤ちゃんがまだ小さいうちは、昼夜逆転や授乳間隔、急な体調の変化など、日々の生活自体が不安定なことも多いですよね。
そんななかで、無理に日程を合わせたり、準備に追われたりすると、せっかくのお祝いがプレッシャーや疲れになってしまうこともあります。
育児中のママやパパは、自分たちの体調管理にも精一杯な時期。
だからこそ「できる範囲で」「無理なくできる方法で」という視点がとても大切です。
たとえば、お祝いは後日ゆっくり写真を撮ったり、お赤飯だけ炊いて気持ちを込めたりと、小さな形でも気持ちはちゃんと伝わります。
なにより、赤ちゃんが笑顔でいてくれること、家族がホッとできる時間を持てること。
それが初節句のいちばんの喜びではないでしょうか。
形式にとらわれず、今の生活に合った過ごし方を考えてみましょう。
「食事会ありき」で悩む必要はない
「やっぱり食事会をしないといけないのかな?」「親戚にどう思われるだろう?」と不安になる気持ちもあると思います。
でも、今の時代は、昔ほど形式にこだわらず、それぞれの家族に合ったスタイルでお祝いすることが自然と受け入れられるようになってきています。
実際に、コロナ禍を経て集まりのスタイル自体が変化したこともあり、必ずしも対面での会食にこだわらなくてもよくなりました。
写真やメッセージを送ったり、後日タイミングを見て会いに行ったりすることで、気持ちをきちんと伝えることもできるんです。
何より大切なのは、「自分たちにとって無理のない、納得のいく形を選ぶこと」。
他の家庭と比べたり、ネットで見かけた風習にとらわれたりするのではなく、自分たちが心地よく過ごせる選択をすることが、初節句をよりよい思い出にするポイントになりますよ。
家族みんなが笑顔で過ごせる形を選ぼう
一番大切にしたいのは、初節句を通して家族が「笑顔で過ごせるかどうか」です。
形式や正解にとらわれすぎるあまり、気疲れしてしまったり、せっかくの時間を楽しめなかったりするのは本末転倒ですよね。
「立派な料理を用意しなきゃ」「ちゃんと飾りつけをしなきゃ」といったプレッシャーを感じるよりも、
「できることを少しずつ」
「楽しめる範囲でやってみる」
という気持ちで準備するほうが、家族みんなの気持ちが穏やかになれます。
赤ちゃんがニコニコしていて、パパやママもリラックスして笑っていられる。
そんな時間こそが、最高の初節句のお祝いになるはずです。
“今のわたしたちに合ったやり方”を大切にして、気負わず、温かい気持ちで過ごしてみてくださいね。