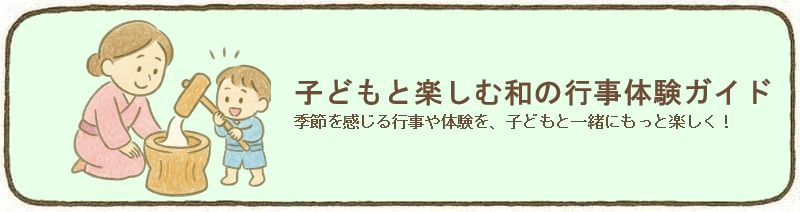親子でおやつを作る時間って、ただ食べるための準備じゃないんですよね。
小さな手でこねた団子や、あんこを包むときの真剣なまなざし、そのひとつひとつが何よりの宝物になっていく気がします。
私が初めて娘と白玉団子を作った日、粉だらけの手を見て「おもちみたいになったね~」と笑い合ったあの瞬間、今でも忘れられません。
ただの粉と水から、あんなにあたたかい時間が生まれるなんて、思ってもみなかったんです。
しかも和菓子は、日本の四季や行事ともつながっていて、食べながら季節を感じたり昔のことを伝えたりもできる。
団子やおはぎ、練り切りのようにシンプルな材料で作れるおやつは、子どもの五感を育ててくれるだけでなく、安全面にも気を配りやすいので、はじめての手作り体験にもぴったりです。
このページでは、親子で楽しめる和菓子作りを丁寧にご紹介していきますので、「料理はちょっと苦手…」と思っている方も、安心して読んでいただけたらうれしいです。
もちもち白玉団子は、はじめての“和菓子職人体験”
白玉団子は、親子で作る和菓子の中でもとくに手軽で、はじめての「食べもの作り」にぴったりな存在です。
材料は少なく、こねて丸めて茹でるだけというシンプルさなのに、できあがると「お店のみたい!」と子どもの目が輝くあの瞬間に、親のほうがじーんとしてしまったりもしますよね。
何より、白玉団子って“触って気持ちいい”“丸めて楽しい”“食べておいしい”が全部そろっていて、粘土遊びの延長のような感覚で小さな子どもでも関わりやすいんです。
そしてこの体験が「自分の手で何かを作るって面白い!」という小さな自信につながっていくのだと思うと、大人としてもできるだけ優しく丁寧に見守ってあげたくなります。
子どもが手を出したくなる柔らかさ
白玉粉に水を少しずつ加えていくと、最初はボソボソだった粉がだんだんしっとりまとまっていって、最後にはすべすべの“耳たぶくらい”のやわらかさになります。
この変化が、子どもにとってはもう魔法みたいなんですよね。
「あれ?さっきまでバラバラだったのに!」
「うわー気持ちいい!」
って、つい何度も手のひらでころころしてしまう。
うちの子は最初「手にくっつく~」とちょっと戸惑っていたのですが、少し水分を足してあげて「こうするとベタベタしないよ」と伝えたら、すぐに夢中に。
むしろそこからが本番で、丸める工程に突入してからは
「これ赤ちゃん団子」
「こっちはお父さん団子」
などと言いながら、自分だけの世界を楽しんでいました。
火を使う工程は大人がしっかりサポート
白玉団子を茹でる工程では、やけどの危険があるため必ず大人が担当します。
お湯の中に入れるときは、団子がくっつかないようにやさしく落とし入れて、くるくるとかき混ぜてあげましょう。
しばらくすると、団子たちがふわっと浮き上がってくる瞬間が訪れます。
この「浮いてきた!」の発見は子どもにとってちょっとした感動体験で、「できたよ~!」と嬉しそうに声をあげる姿には思わずこちらまでにっこりしてしまいます。
ちなみに、浮いてきてから30秒~1分ほど茹でると、ちょうどよい柔らかさになります。
あとは冷水でキュッとしめてあげれば、もちもち食感の白玉団子が完成です。
この“茹でて浮いてくる”という工程を見せることで、加熱や変化について学ぶきっかけにもなりますよ。
仕上げのみたらしタレが、和の風味を引き立てる
白玉団子といえば、やっぱり王道はみたらし。
甘じょっぱいタレの香りが台所に広がると、「あ、これ屋台の匂いだ!」と子どもが嬉しそうに言ったりします。
作り方はとても簡単で、しょうゆ・砂糖・みりん・水・片栗粉を鍋に入れて中火でとろみが出るまで煮るだけ。
火を使うのでここも大人の出番ですが、泡立て器でぐるぐるかき混ぜる様子を見て「次はわたしもやってみたい」と興味を持ってくれる子も多いです。
出来上がったタレを団子にとろりとかけると、そのツヤツヤ感に思わず「わぁ~!」と声が出ることも。
お皿に並んだ白玉団子が、たった今まで手の中で遊んでいた“まるい粉のかたまり”だったことを思うと、子どもなりにちょっと誇らしげに見ていたりします。
食べるときのひと工夫でさらに楽しく
白玉団子はのどにつまりやすい食品のひとつなので、特に3歳以下の子どもが食べる場合は、少し小さめに作ったり半分に切ったりして提供するようにしましょう。
また、団子にフルーツやきなこ、あんこを添えて盛り付けると「お団子パフェみたい!」とさらにテンションが上がります。
串に刺して団子三兄弟風にしてみたり、顔を描いてみたりするのもおすすめです。
「自分で作ったものを食べる」という体験は、子どもにとって大きな喜びであり達成感にもなります。
ただ食べるだけじゃない、そこまでの工程全部が、ひとつの“食育”になっているんだなと感じる瞬間です。
親としては手間に感じることもあるかもしれませんが、その何倍もの笑顔が返ってくるのが、この和菓子作りの不思議なところですよね。
おはぎは“やさしさ”を包む、手のひらサイズの贈りもの
おはぎって、大人になると「和菓子の定番」みたいな印象で何気なく食べてしまうけれど、実際に子どもと一緒に作ってみると、そのやわらかさとあたたかさに驚かされるんですよね。
炊きたてのもち米の香り、あんこの甘さ、きなこの香ばしさ。
ひとつひとつの素材にやさしさが詰まっていて、手の中で包むたびにこちらまで心が和らいでいく気がします。
白玉団子に比べて少し工程が増えるけれど、「混ぜる・丸める・包む」といった作業が中心なので、小さな子どもでも無理なく参加できます。
そして行事とのつながりもあるので“季節を感じる体験”としてもおすすめです。
炊きたてのもち米に触れる特別な時間
もち米を炊くところから始めると、まずキッチンに立ちこめるお米の甘い香りに癒されます。
普通のお米よりも少しだけ水を少なめにして炊くと、べたつかず包みやすい仕上がりになりますよ。
子どもにとっては、炊飯器から湯気が上がってくるだけでもうワクワク。
「もう炊けた?」「あったか~い!」とふれた瞬間のリアクションがかわいくてたまりません。
炊き上がったら粗熱を取って、子どもと一緒にラップを使って一口大に丸めていきます。
手にくっつくのが苦手な子には、手を濡らすか少し塩水を用意してあげると作業しやすくなります。
あんこを包む作業はまるでおままごとのように
つぶあんを用意して「そっと真ん中に入れて包んでごらん」と声をかけると、子どもはまるで宝物を隠すように慎重に包もうとするんです。
「見て、できた!」と見せてくれたおはぎがいびつでも、それが愛おしくて。
うちの子も最初は全然丸くならなかったけれど、3つ目くらいからコツをつかんで、「これママにあげるね」って渡してくれた時のあの満足げな顔、今も思い出すと胸があたたかくなります。
きなこ・ごま・ココア…味も見た目も楽しくアレンジ
あんこが苦手な子や飽きてしまったときは、きなこやすりごま、ちょっと変化球でココアパウダーを使うのも楽しいです。
事前に数種類のトッピングを用意しておくと「今日はどれにしようかな?」と選ぶ楽しみも生まれて、お店やバイキングみたいな気分に。
味だけじゃなく、見た目もぐっと華やかになるので、行事のときには家族で食卓を囲んで話題が広がります。
こどもの日に作ったときは、葉っぱの上にのせて「柏餅みたい!」と子どもが喜んでいました。
思い出と季節を一緒に包む
春や秋のお彼岸におはぎを作るとき、「これはご先祖さまにもあげるんだよ」と話すと、子どもなりに手を合わせたり仏壇に並べたりして、その行動ひとつひとつに“誰かを思う時間”が生まれます。
食べることって、心を通わせる手段なんだなと実感させられる瞬間です。
家族で食べるおはぎは、甘くて、柔らかくて、なんだか心にじんわり沁みる味。
大げさかもしれないけれど、「やさしさを包む」って言葉がぴったりの和菓子だなと思います。
練り切りは、親子でつくる“食べられるアート”
和菓子って、食べるだけじゃなくて「見る楽しさ」や「季節を感じる豊かさ」もあると思うんです。
中でも練り切りは、その魅力がぎゅっと詰まった“芸術作品”のような存在で、実際に子どもと一緒に作ってみると、まるでおうちがアトリエになったみたいな時間が流れます。
ちょっと手が込んでいて難しそうに見えるかもしれませんが、材料さえそろえば、粘土遊び感覚で自由に色や形をつけていけるので、子どもの創造性を引き出すのにもぴったりです。
「お菓子=食べるだけのもの」だった子どもの認識が、「作って表現できるもの」に変わる瞬間に立ち会えるのは、大人としても胸が熱くなりますよね。
白あんと求肥の生地で、基本の“手ざわり”を楽しむ
練り切りの土台となるのは、白あんと求肥を混ぜたやわらかな生地。
市販の白あんと求肥(もしくは白玉粉+砂糖+水を加熱して作ったもの)を練り合わせるだけなので、意外とハードルは高くありません。
生地がまとまってくると、指に吸い付くようなしっとりした手ざわりに変わっていきます。
この感触が、子どもにとってはまさに粘土のような楽しさ。
「気持ちいい~」とずっと触っていたい様子で、丸めたりちぎったりしながら、自然と手先を動かしていました。
何より、安心して触れられる素材であることが大切ですよね。
色づけは“わくわくの時間”に
生地に食紅や天然色素をほんの少し混ぜて、色づけしていく作業は、まさに色遊び。
ピンクは桜、緑は葉っぱ、黄色は菜の花……と季節の風景をイメージしながら、
「今日は春の花を作ろうか」
「夏っぽくしてみる?」
そうやって声をかけると、子どもなりの世界がどんどん広がっていきます。
指先で色を練り込む動作は集中力が要るのですが、その真剣な表情がまたかわいくて。
「ちゃんと色、混ざってきた!」と嬉しそうに見せてくれたその手は、ピンクと緑でちょっとカラフルになっていたけれど、それすらも思い出になります。
型がなくても大丈夫!自由な発想で“自分だけの練り切り”を
練り切り=専用の型や道具が必要、と思われがちですが、実は型がなくても十分楽しめます。
手のひらで丸める、つまんで花びらを作る、爪楊枝やスプーンの背で模様をつけるなど、身近な道具で十分なんです。
うちでは、娘が「これはいちご!」「これはカメ!」とひとつひとつ意味を込めて作っていて、もはや味以上に“作品”としての満足度が高かったようです。
もちろん、見た目が多少崩れても気にしないことが大切。
「その形もかわいいね」と声をかけることで、のびのびと表現する時間になってくれます。
盛りつけることで、より特別なおやつに
作った練り切りは、ぜひ小さなお皿や和紙の上に並べて、お茶と一緒に楽しんでみてください。
「自分で作ったお菓子を、自分で盛りつけて、自分で選んだ器で食べる」この一連の流れが、子どもにとってとても大きな意味を持ちます。
「ママはこれが好きそうだから、こっちにしようかな」と家族のことを考えながら配置してくれたとき、ああ、これが“育ち”なんだなと実感しました。
練り切りは、ただの和菓子じゃなくて、親子のコミュニケーションを深めてくれる魔法のおやつなのかもしれません。
安全に楽しむために、気をつけたい3つのこと
和菓子作りは親子の心をぐっと近づけてくれる素敵な体験ですが、食べものを扱うからこそ「楽しかった!」だけで終わらせず、ちゃんと安全にも気を配っておきたいところですよね。
特に、小さな子どもと一緒にキッチンに立つときは、少しの工夫と準備で安心感が大きく変わってきます。
おいしい記憶が“こわい思い出”に変わってしまわないようにするためにも、ここでは3つの大切なポイントをまとめてみました。
「うちの子にはまだ早いかも」と感じていた方も、ちょっとしたサポートで楽しく参加できるようになりますよ。
①手洗い・除菌は“まほうの儀式”として楽しく
「まずは手を洗おうね」
「ここはきれいにしてから始めようね」
と声をかけても、子どもによっては「えーめんどくさい~」となってしまうこともありますよね。
でもそんな時こそ、「これはおいしくなるおまじないなんだよ」と伝えてあげると、急に表情が変わって張り切ってくれたりします。
石けんをしっかり泡立てて「手の指の間までキュキュッとね」、そして使う器具や作業台も、除菌スプレーやアルコールシートで拭いておくことが大切です。
大人がその姿を見せてあげることで「料理って、きれいにしてからやるものなんだ」と自然に身についていくんですよね。
②火や包丁を使うときは“親が主役”で
和菓子づくりの中には、みたらしのタレを煮る工程や、もち米をつぶすときの加熱作業など、火を使う場面がいくつか出てきます。
ここは迷わず大人の出番です。
子どもに無理をさせないで、
「ここはママがやるから、見ててね」
「今から熱いから、ちょっと離れててくれると助かるな」
と、やわらかく伝えてあげてください。
「一緒にやろうね」ではなく、「一緒に作ってるけど、ここは役割分担でね」と伝えることで、子ども自身も納得しながら関わることができます。
特に小さな子どもは、「大人のやっていることを見る」だけでも十分な刺激になりますし、後でその体験がしっかり根づいていきます。
③詰まらせやアレルギーへの配慮を忘れずに
和菓子の中には、もち米や白玉粉のように“もちもち”“つるん”とした食感のものも多いですよね。
でもこれが、まだ噛む力が弱い子どもにとっては少し危険な場合もあります。
のどに詰まらせないように、白玉団子はあらかじめ小さくちぎってあげたり、練り切りはやわらかさを保つ工夫をしてあげるのがおすすめです。
また、あんこやきなこ、ごまなどは一見シンプルな素材に見えますが、アレルギーの心配があるご家庭では必ず原材料を確認するようにしてくださいね。
心配な場合は、砂糖控えめのあんこや、お米そのままの味を活かした“あんなしおはぎ”にするなど、家庭に合わせたアレンジができるのも和菓子のいいところです。
まとめ
子どもと一緒に作る和菓子の時間は、ただ「おやつを作る」だけの時間ではなく、親子で心を通わせる小さな物語のようなひとときです。
白玉団子を丸めるときの笑顔、おはぎを包むときの真剣なまなざし、練り切りを彩るときの集中した沈黙。
どれも一瞬で過ぎてしまう日常の中に、たしかな成長と優しさの記憶が残っていきます。
お菓子作りを通して子どもが自分の手で何かを形にする喜びを知り、大人はその過程を見守るあたたかさを感じる。
そんな時間こそ、家庭の中でしか育てられない“心の栄養”なのだと思います。
また、和菓子という伝統の中には、日本らしい季節感や行事の意味が自然と溶け込んでいます。
「お彼岸におはぎを作る」
「お花見に団子を添える」
「七夕に星の練り切りを並べる」
そのたびに、子どもは「昔から続いてきたことの美しさ」を肌で感じ取ります。
親が「こういう時に食べるんだよ」と教えることで、文化の記憶が世代を超えて受け継がれていくんですね。
完璧じゃなくても大丈夫。
形がいびつでも、少し焦げても、それは“今の親子の形”として残ります。
失敗も笑い合える時間こそが、きっと子どもの心に一番残る味になるはずです。
ぜひ次の休日には、家族で小さな和菓子づくりの時間を楽しんでみてください。
甘くてやさしい香りと一緒に、忘れられない思い出が生まれますよ。