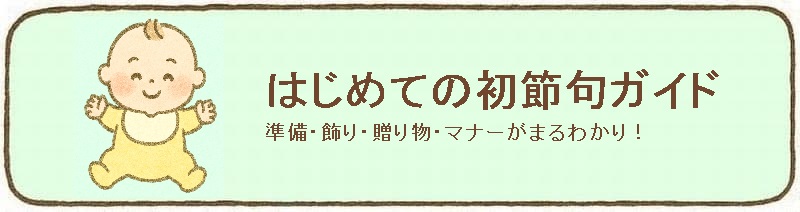初節句は、赤ちゃんの健やかな成長を願って祝う、とても大切な行事のひとつです。
生まれて初めて迎える節句ということもあり、家族にとっては特別な思い出になりますよね。
でも、「ひな人形や兜は誰が買うの?」「祖父母が用意するもの?それとも自分たち?」と悩んでしまうママやパパも少なくありません。
昔ながらの風習や地域ごとのしきたりもあれば、最近ではライフスタイルの多様化や家族構成の変化によって、初節句の祝い方もずいぶん変わってきました。
それに、祖父母との関係や考え方もそれぞれ違うので、何が正解かわからなくて戸惑うこともありますよね。
この記事では、初節句に必要な飾りや祝い品を
「誰が買うのか?」
「どう準備するのがベストなのか?」
という点を中心に、現代の事情も踏まえてわかりやすくお伝えしていきます。
できるだけトラブルにならないように、祖父母との関係を円満に保ちながら、無理のない形で初節句の準備を進めるためのポイントもご紹介しますので、これから準備を始める方はぜひ参考にしてみてくださいね。
初節句の飾りや祝い品は誰が買うのが一般的?
昔と今で違う?伝統的な考え方
昔は「初節句の飾りは母方の実家が贈るもの」とされてきました。
これは、子どもが無事に育つようにという願いを込めて、母方の祖父母がひな人形や五月人形を贈ることで、その子の健やかな成長と幸せを祈る意味があったんですね。
特に、ひな人形は女の子の厄除け、五月人形は男の子を守るお守りとされていて、「一生の守り神」として大切にされるものでした。
そのため、母方の祖父母が「孫への贈り物」として、節句飾りを用意するのが当然のように受け止められていました。
昔は嫁入りした娘の子どもに対して、実家が責任を持って祝うという考え方もあって、母方の実家の出番が大きかったわけです。
ただ、これはあくまで昔ながらの風習であって、現代では必ずしもそのとおりにしない家庭も増えてきています。
最近では、両親が自ら飾りを用意することもあれば、父方の祖父母が積極的に贈ってくれる場合もありますし、両家で相談して一緒に用意することもあります。
時代が変わるにつれて、家族の形も祝い方も多様になってきているので、「これが正解!」という決まりがないのが今のスタンダードになってきているんですね。
現代はどうなってる?実際の家庭事情とアンケート傾向
最近では、「家庭で用意した」「父方の祖父母が買った」「祖父母と両親で相談して決めた」など、いろんなパターンが見られます。
中には、両家の祖父母が一緒に買ってくれたというケースや、希望する飾りが高額だったために数年かけて少しずつそろえた、なんていう家庭もあるようですよ。
調査によると、約半数の家庭が「祖父母からの贈り物」として節句飾りを受け取っているそうですが、一方で自分たちで購入する家庭もかなり増えてきているんですね。
とくに、共働き家庭が増えて「自分たちで選びたい」「家のスペースや好みに合ったものを用意したい」と考える親が増えたのも理由のひとつです。
また、最近では節句飾りもコンパクトなタイプやモダンなデザインのものが増えていて、「インテリアに合うものを自分たちで選んだ」という声もよく聞かれます。
祖父母からの贈り物とは別に、自分たち用に小さな飾りをもうひとつ用意したという家庭もあるようです。
共働き家庭の増加や、価値観の多様化もあって、「決まった形がない分、自由に選べる」という傾向が強くなってきています。
親世代と考え方が違う場面もありますが、それぞれの家庭で納得できるやり方を見つけることが大切なんですね。
地域差や家族構成でも変わるポイント
実は、地域によっても初節句に対する考え方や習慣はけっこう違います。
関西ではひな人形を母方が贈るのが一般的とされていますが、関東では「特にこだわりはない」「両親が買うケースも多い」という傾向があります。
さらに、家族の構成や祖父母との関係性、住んでいる距離などによっても「誰が買うか」は大きく変わってきます。
たとえば、祖父母が遠方に住んでいて会う機会が少ないと、両親が準備する流れになりやすいです。
反対に近くに住んでいて頻繁に会う関係だと、「うちで用意するよ」と言ってくれることもあるようです。
また、経済的な事情も影響するポイントです。
「どちらの祖父母も援助が難しいから自分たちで用意した」という家庭もあれば、「せっかくだから立派なものを用意したい」と祖父母が進んで準備してくれた例もあります。
だからこそ、「うちはどうする?」と家族でしっかり話し合うことがとても大切なんですね。
ひな人形・五月人形は誰が買う?パターン別に解説
祖父母が贈る場合:どこまで任せてOK?
祖父母が「ぜひ買ってあげたい」と申し出てくれることもありますよね。
そんなときはありがたく甘えても大丈夫。
おじいちゃんやおばあちゃんにとっても、初節句の飾りを用意することは孫への愛情表現のひとつでもありますし、「買ってあげたい」という気持ちを受け止めることで、喜んでもらえることも多いんです。
ただし、飾りの種類やサイズ、置き場所などについては、きちんと事前に相談しておくことが大切です。
とくにマンションやアパートに住んでいる場合、豪華な段飾りなどはスペース的に難しいこともあります。
「立派すぎて置く場所がない…」なんてことになってしまうと、お互い気まずくなってしまいますよね。
「こんなに大きいとは思わなかった…」なんて後悔を防ぐためにも、写真やカタログを一緒に見ながら選ぶのがベストです。
最近ではネットショップでもたくさんの種類が見られるので、スマホやパソコンで一緒に画面を見ながら相談するだけでも、スムーズに話が進みますよ。
また、どうしても意見が合わないときは、「せっかくのご厚意だから、気持ちだけいただいて、実際のものは一緒に選ばせてもらえたら嬉しいな」と、やんわり伝えてみるのもひとつの方法です。
お互いが納得して準備できるようにすることが、何より大事なんですね。
両親が購入する場合:夫婦での話し合いがカギ
最近は「自分たちで選びたいから」と両親が購入するケースも多いです。
とくに共働きで経済的に余裕がある家庭では、インテリアに合ったデザインやサイズ、素材にこだわって、好みにぴったりの飾りをじっくり選んで準備する楽しみもあります。
初節句は赤ちゃんだけでなく、家族にとっても記念すべき大切なイベント。
「せっかくなら、自分たちで気に入ったものを選びたい」と考える夫婦も増えています。
写真映えや記念撮影を意識して、コンパクトだけどおしゃれな飾りを選ぶ人も多いですよ。
祖父母に「自分たちで準備するね」と伝えるときは、「気にかけてくれてありがとう」と一言添えると角が立たずに済みますよ。
さらに「見に来てくれるのを楽しみにしてるね」と伝えれば、関係もより良く保てます。
また、「もしよければ初節句のお祝いに〇〇をお願いしてもいいかな?」と、別の形で関わってもらう提案をしてみるのも◎。
たとえば、食事会の費用をお願いしたり、赤ちゃんの衣装をプレゼントしてもらったりと、役割分担を工夫するとお互い気持ちよく準備が進められます。
折半・共同購入する場合の注意点
「うちは半分ずつ出そうか」という話になることもありますよね。
こうした折半スタイルは、どちらか一方の負担になりすぎず、お互いが気持ちよく関わる方法として選ばれることが増えてきています。
ただし、「どちらがいくら出すか」「具体的にどの品物に使うか」など、最初にきちんと話し合っておかないと、あとでちょっとした行き違いから気まずくなってしまうことも。
たとえば、「飾りの本体は祖父母が買って、ケースや飾り台は両親が用意する」といった分担方法や、「全体費用の半分をそれぞれ負担する」という方法など、家庭によってルールはさまざまです。
だからこそ、あとあとモヤモヤしないように、金額の目安や購入時期、支払いの方法まで含めてしっかり確認しておくことがとっても大切なんですね。
また、共同購入の場合は、飾りの選び方についても家族全員の意見を取り入れることになります。
祖父母と両親で好みが違う場合もあるので、
「こういう雰囲気のものがいいな」
「サイズはこれくらいにしたいな」
といった希望を事前に共有しておくと、選ぶときにスムーズです。
特に節句飾りは早めに売り切れることもあるので、ゆとりを持って準備にとりかかるのがポイント。
余裕があれば下見を一緒に行ったり、オンラインショップで情報を共有したりと、コミュニケーションを深めながら楽しく準備が進められますよ。
初節句の祝い膳・お金・内祝いなど「他の準備」はどうする?
食事会の主催は誰がする?場所や費用の分担
初節句の食事会は、両家の祖父母を招いて行うのが一般的ですが、「どこで」「誰が準備するか」で悩むこともありますよね。
最近では、自宅で簡単に開いたり、レストランを予約したりと形式はさまざま。
費用は両親が出すことが多いですが、「祖父母が一部負担してくれた」というケースも珍しくありません。
無理なくできる形で相談してみるといいですよ。
お祝い金へのお返しは必要?マナーと実例
祖父母や親戚からお祝い金をもらった場合、「お返し(内祝い)」をどうするか迷いますよね。
一般的には、いただいた金額の3分の1~半額程度を目安に、お菓子やカタログギフトなどを贈ると丁寧です。
ただ、祖父母の場合は「内祝いは不要」と言われることも多いので、無理に贈る必要はありません。
それよりも、「ありがとう」の気持ちをしっかり伝えることが大切ですよ。
節句飾り以外に必要なものとは?
飾り以外に必要なものとしては、写真撮影のための衣装や、記念のプレート、命名札などが挙げられます。
衣装は、袴ロンパースや白いドレスなど、赤ちゃんらしさを引き立てるデザインが人気で、写真スタジオでレンタルする人もいれば、自宅で手頃な価格の衣装を用意して撮影する家庭もあります。
また、命名札は初節句の記念品としても残せるアイテムで、赤ちゃんの名前と生年月日を入れたものを飾ると、とても特別感が出ます。
記念のプレートには、節句の日付や「初節句おめでとう」などのメッセージを添えると、あとで写真を見返したときに思い出がより鮮明によみがえりますよ。
特別なものじゃなくても、手作りのガーランドや赤ちゃんの写真入りカードなど、家族で手間をかけて用意したものには、既製品にはない温かみが感じられます。
壁に飾るデコレーションや名前入りのフラッグなど、100円ショップの素材で工夫する人も多く、楽しみながら準備できるのが魅力です。
こうした小物は、節句当日だけでなく、記念写真にも映える大切なアイテムになります。
家族みんなで相談しながら「うちだけの初節句空間」をつくってみるのもおすすめですよ。
もめないために!家族とスムーズに話し合うコツ
「誰が買うか」は早めに相談しよう
「まだ時間があるから」と先延ばしにしていると、気づいたときには間に合わない…なんてことも。
初節句の飾りは思っている以上に準備に時間がかかることがあるので、できればお正月明けくらいには計画を立て始めておくと安心です。
飾りの在庫がなくなっていたり、人気のデザインは予約が必要だったりすることもあるので、早めの行動がとても大事なんですね。
とくに祖父母との関係性が大切な場面なので、ギリギリになって慌てて相談するよりも、早めに話し合いの場を持つことでお互いの希望や考え方をすり合わせやすくなります。
例えば、年末年始の帰省時に話題に出すと、自然な流れで相談しやすいですよ。
また、早めに話をすることで「思ったより大きな出費になるから相談してよかった」と感じたり、「祖父母がこんなに乗り気だったなんて知らなかった」など、嬉しい発見があることも。
初節句は家族のイベントでもあるので、なるべく全員の思いを共有しながら進めていけると理想的です。
祖父母の気持ちも大切にしつつ自分たちの意向も伝える
「買いたい」と思っている祖父母の気持ちをくんだうえで、
「でもサイズはこれくらいがいいな」
「こういうデザインが好き」
と、自分たちの希望も伝えると、円満に話が進みやすくなります。
たとえば、「せっかくなのでリビングに飾れる小さめのものがいいな」といった伝え方をすると、相手も気を悪くせずに理解してくれやすいですよ。
また、あらかじめ希望の商品やイメージ画像を用意しておくと、話し合いもスムーズに進みます。
「こういう感じが好きなんだけど、どう思う?」と聞いてみると、祖父母の意見も取り入れながら自然に会話ができて、お互いの思いを共有しやすくなります。
お互いに「思いやり」を持って話すことが大事ですね。
相手を否定せず、自分たちの思いも大切にしながら調整していく姿勢が、結果的にみんなが納得できる形につながっていきますよ。
トラブル回避には「感謝の気持ち」がポイント
誰が買うにしても、最終的にいちばん大切なのは「ありがとう」という感謝の気持ちです。
せっかくの初節句というお祝いの場がギクシャクした雰囲気にならないようにするためにも、関わってくれた人たちへの思いやりを忘れず、感謝の言葉をきちんと伝えることがとても大事なんですね。
とくに祖父母が飾りを贈ってくれたときや、お祝いをしてくれたときには、形式ばったお礼よりも
「ありがとう、すごくうれしいよ」
「気にかけてくれて本当に助かったよ」
といった、心のこもった言葉を添えるだけで、相手の気持ちもふわっと和らぎます。
さらに、電話だけでなく、写真付きのメッセージカードやLINE、手書きのお礼状などで感謝を伝えると、「こんなに喜んでもらえたんだな」と実感してもらえて、関係がさらに良好になりますよ。
感謝は言葉にしないと伝わらないもの。
少し照れくさいかもしれませんが、素直な気持ちを言葉にすることが、家族のつながりをより深めるカギになるんです。
何かをしてもらったときは、その都度「ありがとう」と言葉にしてみてくださいね。
それだけでも相手の印象がぐっと変わり、気持ちのよいやり取りが続けられるようになります。
まとめ:誰が買うかは“正解”より“納得”が大切
初節句の飾りや祝い品を誰が買うかには、実はこれといった正解はありません。
昔ながらの風習を大切にして、母方の祖父母が準備するのが当然だと考える家庭もあれば、最近の家族構成やライフスタイルに合わせて、両親が主体になって準備を進めるケースもあります。
どちらが正しいということではなく、それぞれの家庭に合った方法を見つけることが何より大切なんです。
また、最近では「親戚の中で以前こうしていたから…」といった過去の例にしばられすぎず、話し合いの中で新しい形をつくっていく家族も増えています。
「こうでなければならない」という決まりに縛られるよりも、その家族の事情や思いをベースに、より自然で心地よい形を模索していくことが、満足度の高いお祝いにつながるんですね。
大事なのは、「家族みんなが納得できる形」で進めること。
祖父母の気持ちをしっかりと受け止めながらも、夫婦での希望や実際の生活スタイル、予算面などもきちんと考慮して、無理のない範囲で計画していくことが大切です。
誰かの思いだけが一方的に反映されるのではなく、関わるすべての人が「良かったね」と思えるような形が理想ですよね。
無理せず、楽しみながら初節句をお祝いできるといいですね。
その経験は、きっと赤ちゃんにとっても、家族にとっても、一生のあたたかな思い出になるはずです。