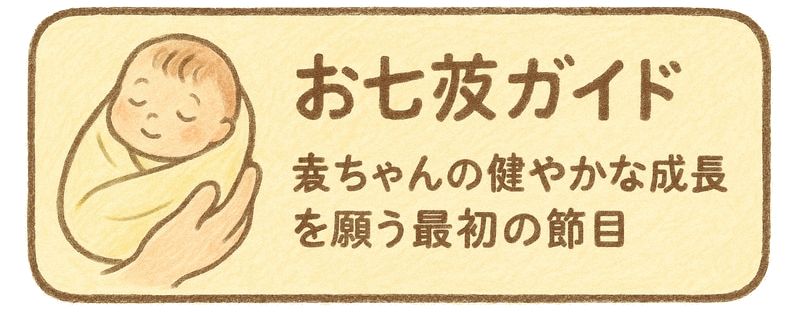「お七夜(おしちや)」って聞いたことはあるけど、
実際に自分が親になってから急に現実味を帯びてくる言葉じゃないでしょうか?
生まれて数日の赤ちゃんを前にして、「命名?お祝い?なにをどうやればいいの?」と戸惑うママ・パパも多いはず。
かくいう私も、まさにその1人でした。
上の子のときは、出産でクタクタ、夜中の授乳でフラフラ。
「お七夜?ムリムリ!」って、やらずに終わっちゃって。
でも、あとになってSNSで知人の投稿を見かけて、「やってあげたほうがよかったかなぁ…」って、ちょっとだけ心がチクリ。
だから下の子のときは、すっごくシンプルにだけど、命名の紙を書いて、家族でお祝いご飯を食べました。
そしたら不思議と、「この子を本当に迎え入れたんだなぁ」って、じんわり心があたたかくなったんです。
今回は、そんなお七夜の意味や由来、どうして7日目なのか、なにをすればいいのか
歴史から現代のスタイルまで、心を込めてご紹介します。
お七夜とはどんな行事?
赤ちゃんの誕生から7日目に祝う「初めての節目」
お七夜は、赤ちゃんが生まれて7日目に行う、日本の伝統的なお祝い行事。
命名式として名前を発表し、赤ちゃんの健やかな成長を祈るとともに、「この子を家族に迎えました」という区切りをつける節目のイベントです。
一般的には、命名書(名づけ札)を用意して、家族でささやかなお祝い膳を囲み、写真を撮る…といった流れ。
でも、やり方は家それぞれ。
命名書を飾らずに写真だけ残す家庭もあれば、退院後の疲労を考えて後日ゆっくり行う人もいます。
つまり、「しきたり通りに完璧にしなきゃ!」と思う必要はまったくないんです。
大事なのは“気持ち”と“赤ちゃんとの時間を大切にすること”。
お七夜は、ママパパの「ようこそ」の気持ちを、初めてカタチにして表す日なのかもしれません。
命名を通じて「社会の一員」として迎える日
昔から「名前をつける」ことには、深い意味があります。
それは、単に呼び名を決めることではなく
「この子はこれからこの名を背負い、人生を歩んでいく」
という家族の願いと覚悟の表明。
お七夜で命名書を飾るのは、その第一歩。
「うちの子はこの名前で生きていきますよ」と、家族や親族、時には神様へ伝えるための大切な儀式です。
現代では、出生届を提出すれば命名の手続きは済みますが、
それとは別に、“心を込めて名づけた”という実感を得られるタイミングが、お七夜なんです。
そして、将来子どもが大きくなったとき「この名前はね、こんな意味をこめてつけたんだよ」
そんな風に話してあげられたら、それってすごく素敵な家族のエピソードになりますよね。
お七夜の由来と歴史をひもとく
平安時代の「産養(うぶやしない)」がルーツ
お七夜のルーツをたどると、平安時代の「産養(うぶやしない)」という習わしに行きつきます。
この「産養」とは、出産後に母子が一定期間静かに過ごし、体を休める風習。
今でいう「産褥期(さんじょくき)」のようなもので、7日間~1ヶ月ほど、外部と接触せずに籠もる時間が設けられていました。
その「産養」が明ける7日目に行われたのが、赤ちゃんを外の世界に紹介するお祝い=お七夜です。
つまりお七夜は、母子が社会に戻る“お披露目の日”として生まれた文化なんですね。
昔は「7日目」がひとつの“生存確認”だった
昔の日本では、医療も栄養も今のように整っていませんでした。
生まれたばかりの赤ちゃんの死亡率も高く、「7日間生きられるかどうか」は、大きな山だったのです。
そのため、“生後7日を迎えられた”ということ自体が、命の強さを証明する特別な出来事でした。
家族はその日を境に、「この子はこの世界に根を下ろした」と受け止め、名前をつけて、未来へと送り出していったのです。
だからこそ、古くからのお七夜には、
- 命名の儀式
- 祝い膳(鯛、赤飯など)
- 親戚の招待と祝宴
命名書や祝膳の風習が生まれた背景
江戸時代以降、庶民にも広まったお七夜では、「命名書(名づけ札)」を飾り、祝い膳を用意するスタイルが一般的になりました。
とくに祝い膳に使われる「鯛」「赤飯」「昆布巻き」「煮しめ」などは、すべて縁起物の象徴。
「喜びが重なるように」「昆布=子生(こんぶ)」「鯛=めでたい」など、意味が込められています。
いまのご家庭で、そこまで本格的な料理を作るのは大変かもしれませんが、
冷凍やデリバリー、スーパーのお祝いプレートでも十分!
“この日だけは、ちょっとだけ特別なごはんを囲む”
その想いさえあれば、それでじゅうぶんなんです。
お七夜の意味にこめられた家族の想い
赤ちゃんの無事な誕生への感謝
妊娠がわかってから、出産まで。
十月十日、ただただ無事を祈って過ごしてきた日々。
「ようやく会えた赤ちゃんを抱きしめる瞬間」その感動って、もう言葉にならないほどのものですよね。
でも実際には、出産って命がけ。
出血、陣痛、手術…予期せぬトラブルもたくさんあります。
それでも「産まれてきてくれてありがとう」って思える奇跡。
お七夜は、その気持ちをきちんと表現できる“感謝の記念日”でもあるのです。
これからの健やかな成長を願って
生まれてきた赤ちゃんは、まだ言葉も発せず、泣いて、眠って、飲んで…の繰り返し。
でもその姿を見てると、ふと未来を想像してしまうんです。
「この子はどんなふうに笑うんだろう」
「学校に行ったらどんな友だちができるかな」
「名前を呼ばれたとき、どんな顔をするのかな」
そんな「“未来への願い”を込めて祝う日」が、お七夜なんです。
「名を与える」ことの大切さ
名前には、「意味」や「想い」や「音の響き」など、
パパやママがたくさん悩んで考え抜いたものが詰まっていますよね。
だからこそ、その名前を初めて外に向けて発表するお七夜は、赤ちゃんにとっても、ママパパにとっても、特別な意味を持つ日になるのです。
時代とともに変わるお七夜のかたち
昔ながらのしきたりにとらわれなくてOK
今の時代、家族のあり方も、ライフスタイルも多様化しています。
- 産後の回復に時間がかかる
- 里帰り中で家族がそろわない
- そもそもお祝いごとは最小限にしたい
「やらなかった=悪いこと」ではありません。
どんな形でも、「うちの赤ちゃんの記念日」として心に残れば、それが最良の形なんです。
現代の「簡略版お七夜」や「後日開催」の例
今では、お七夜を簡略化したり、後日にずらす家庭も少なくありません。
- 「命名紙+スマホ写真」だけ
- 退院後にママの体調が落ち着いてから
- 1ヶ月健診と一緒に写真館で記念撮影
記念写真や命名書だけでも心に残る祝い方に
正直、豪華な料理も、立派な命名書も、なくたっていいんです。
- 1枚の命名写真。
- そこに映るママやパパの笑顔と、ちっちゃな赤ちゃん。
- あとで見返したとき、「この子が来てくれた日のこと」を思い出せる。
そんな1枚があれば、それこそが宝物。
まとめ|お七夜は“心で祝う行事”です
お七夜は、赤ちゃんの無事な誕生を祝い、名前を贈り、
「ようこそ、この世界へ」と心から伝える行事です。
その由来や歴史を知ることで、形式に縛られず、気持ちのこもったやり方で祝えばいいんだと安心できるはず。
ママやパパが心から「おめでとう」と思えたその瞬間こそ、
赤ちゃんにとって最高の贈り物になります。
焦らず、比べず、わが家らしく。
それが、いちばんあたたかく、いちばん幸せなお七夜です。