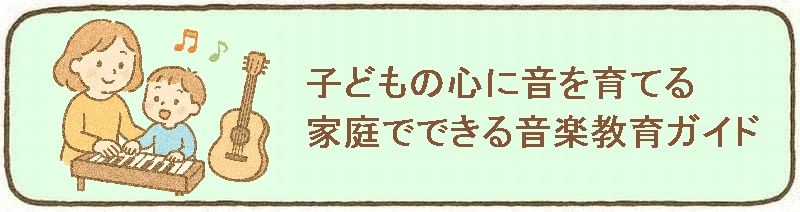初めて子どもを音楽コンクールに挑戦させようと考えたとき、多くの親御さんがまず感じるのは期待と同じくらいの不安ではないでしょうか。
せっかく舞台に立つのだから自信を持たせてあげたいけれど、
「費用はどれくらいかかるのか」
「練習はどれほど必要なのか」
「本番で緊張して泣き出したりしないだろうか」
次々にそんな心配が浮かんでしまうものです。
私自身も最初のときは「習い事の延長だろう」と気軽に考えていたのに。。。
「エントリー費用や衣装代」
「追加レッスン」
「交通費」
など現実的な出費を知って思わずため息をついたことがありますし、子どもの気持ちの浮き沈みに親としてどう寄り添えばいいのか悩む日々が続きました。
コンクールは華やかな舞台だけではなく、準備の段階から親子の気力や時間、経済面への負担があるという現実を理解しておくことがとても大切です。
それを知っていれば焦らずに計画を立てられますし、心に余裕を持ちながら本番までの過程を楽しむことができますよ。
またコンクールは結果だけでなく挑戦そのものに価値があり、努力を重ねる過程が子どもの成長や自信につながる大切な体験でもあります。
この記事ではそうした親御さんの不安を少しでも減らせるように、初めて挑戦するときに必要な費用の目安や準備の流れ、親子で心を整えるヒントを体験談も交えながらお伝えします。
知っておくだけで「やってよかった」と思える準備ができるようになりますし、子どもにとっても安心できる環境を整えてあげられるはずです。
コンクール参加を決める前に知っておきたいこと
コンクールに出る目的を親子で話し合おう
音楽コンクールに挑戦するというのは、子どもにとっても親にとっても大きな経験になります。
ですが、勢いだけで申し込んでしまうと、後から「なんで出ることにしたんだっけ?」と目的を見失ってしまうことがあるんですよね。
だからこそ最初に「何のために出るのか?」という部分を親子でしっかり話し合っておくことが、とても大切なんです。
例えば、ある子は「先生に勧められたから」と出場を決めたけれど、本人はただ楽しんで弾きたいだけだったということもあります。
別の子は「トロフィーがほしい!」と意気込んでいたのに、いざ練習が厳しくなると気持ちが折れてしまうこともあります。
目的があいまいなまま走り出すと、練習の途中で親子関係がぎくしゃくしてしまう原因にもなってしまうんですね。
うちの子の場合は「大きなステージで弾いてみたい」という夢がきっかけでした。
その気持ちを大事にしたくて、結果よりも舞台に立つことをゴールに設定したら、練習の中でも笑顔が増えて、親としてもずっと見守りやすくなったんです。
子どもの「やりたい」「やってみたい」の中にどんな気持ちがあるのかを、親がていねいに聞いてあげること。
それが、コンクールに前向きに取り組む第一歩になりますよ。
挑戦が向いているタイミングと年齢の目安
「何歳から出られるんだろう?」「うちの子にはまだ早いかも」と悩む声はよく聞きます。
たしかにコンクールは3歳から出場できるものもありますが、年齢よりも大切なのはその子の発達段階や音楽への向き合い方です。
たとえば、まだ楽譜を読むのが不安定な時期だったり、ステージに立つことに強い緊張を感じるタイプの子どもには、無理に早く参加させる必要はありません。
大切なのは「出るべき年齢」ではなく「今のこの子にとって、どんな体験がプラスになるか」という視点なんです。
私の周りには、5歳で初めて出場して表情がこわばったまま終えた子もいれば、小学2年生で初参加して「もっと弾きたい!」と目を輝かせていた子もいます。
どちらが正解ということではなく、その子の個性や準備状況によって、挑戦のタイミングは変わってくるんですね。
日々のレッスンで
「本番で弾ききる力が育ってきたか」
「先生の指示を理解して工夫ができるか」
「長時間の練習に少しずつ慣れてきたか」
そんな様子を親がそっと見守りながら「今がそのタイミングかどうか」を感じ取っていくことが何より大切ですよ。
体験者が語るメリットと気をつけたい点
音楽コンクールに出ることにはたくさんのメリットがあります。
人前で演奏することで集中力が増し、日々の練習のモチベーションが上がることもあります。
なにより「やりきった」という達成感は、子どもの心にしっかり残っていきますよ。
また、他の参加者の演奏を聴くことが刺激になり、自分ももっと上手になりたいという気持ちが芽生えるきっかけにもなります。
発表会よりも緊張感が高いからこそ、本番に向けて努力を重ねる日々は、子どもにとって大きな成長のチャンスになります。
でもその一方で、やはり気をつけなければいけない点もあります。
たとえば、親が結果に過剰に期待しすぎてしまうと、子どもは「失敗しちゃいけない」とプレッシャーを感じてしまうことがあります。
また、思ったような評価がもらえなかったときに、落ち込んだり自信をなくしてしまうこともあります。
私も初めてのコンクールで「頑張ってたし、きっと賞がもらえるかも」と期待してしまったことがありました。
でも実際には入賞できず、娘は泣きながら「もうやりたくない」と言ったんです。
その時にハッと気づきました。
賞じゃなくて、この子がここまで練習を積み重ねてきた日々こそが尊いのだと。
だからこそ、親が一歩引いて見守る姿勢もすごく大事です。
コンクールはあくまで「通過点」なんですよね。
その経験がその子の音楽人生にとって、少しでも豊かな記憶になるように、親も一緒に心の準備をしていけたらいいなと思います。
親の覚悟とサポートのスタンスを見直そう
忘れがちなのですが、実は一番試されるのは親のスタンスだったりします。
コンクールに出るというのは、単に「子どもの晴れ舞台」ではなく、
「日々の練習への付き添いや送り迎え」
「心のサポート」
まで含めて、家庭全体で取り組むようなプロジェクトなんです。
親のなかにも、「子どものために頑張りたい」と思って始めたのに。
いつの間にか「こんなにやってあげてるのに!」とイライラが積もってしまったり、練習をめぐって衝突が増えてしまったりするケースも少なくありません。
私も一度「なんでちゃんとやらないの?」と強く言ってしまい、娘を泣かせてしまったことがありました。
あのときの小さな背中を、今でも思い出すと胸が痛みます。
コンクールは子どもの挑戦ですが、それを見守る親自身も覚悟が必要です。
結果よりもプロセスを大切にすること、上手に弾けることよりも音楽を好きでいてくれること、その気持ちを忘れずにいることで、親子の関係もぐっと深まりますよ。
コンクールにかかる主な費用の目安
エントリー費用と演奏時間による金額の違い
コンクールに参加するには、まず「エントリー費用(参加費)」がかかります。
この金額は大会によってかなり幅があるのですが、未就学児~小学生部門ではおおむね8,000円~15,000円前後のことが多いです。
ですが、これが全国規模の大会になったり、演奏時間が長い部門になると2万円以上になることもあるんですよ。
演奏時間が長くなるということは、それだけステージを独占する時間が増えるということなので、当然ながらその分の参加費も高く設定される傾向にあります。
また、1次予選・本選・全国大会などと進むごとにエントリー費用が都度発生する大会もあり、全部で数万円単位になることもあります。
私の場合、最初のコンクールが地域大会だけだったので1万円ちょっとで済みましたが、知人のご家庭では全国大会まで進んで、エントリー費用だけで5万円を超えたと聞いて驚いたことがありました。
費用面でも余裕を持って計画しておくことが大切ですよ。
衣装・靴・ヘアセットなどの準備費用
コンクールの舞台は、演奏だけでなく見た目の印象も評価に含まれることがあります。
とくにピアノやバイオリンなどのソロ演奏では、衣装の華やかさや清潔感がその子の演奏を引き立てる大切な要素になることもあるんですね。
女の子ならドレス、男の子ならきちんとしたシャツとスラックス、そしてどちらにも共通するのが「舞台用の靴」。
これがまた意外と高いんです。
新品で揃えると、ドレスで1万円以上、靴で5千円~1万円、アクセサリーや髪飾りを合わせるとそれだけで2~3万円近くになることも珍しくありません。
私は最初、あまりに高額なのでフリマアプリで未使用品を探したり、お友だちからお下がりをいただいたりしてなんとか抑えました。
それでもやはり、ある程度の出費は覚悟が必要だなと実感しましたよ。
レッスン追加費用や伴奏代、交通費・宿泊費
本番が近づいてくると、多くのご家庭で「追加レッスン」が始まります。
これも費用がじわじわとかさんでくるポイントです。
通常レッスンとは別に「仕上げ用」や「模擬演奏形式」の特別レッスンが組まれることがあり、1回ごとに数千円から1万円前後がかかる場合もあります。
また、バイオリンや声楽など伴奏が必要な楽器では、プロの伴奏者にお願いすることが多く、その謝礼も別途必要になります。
本番だけでなく、合わせ練習にも何度か来てもらうことになるので、合計で数万円にのぼるケースもありますよ。
さらに見落としがちなのが交通費と宿泊費です。
コンクール会場が遠方になると、新幹線代やホテル代が発生します。
我が家も一度、県外の大会に参加したとき、1泊2日で家族3人の出費が思いのほか大きくなって、やはり事前に予算の余裕を見ておくべきだと反省しました。
予算を立てるときに見落としがちな出費
コンクールの参加には、大きな費用だけでなく「こまごました支出」がたくさんあります。
例えば、
「写真や動画の撮影代」
「控室での軽食」
「当日の送迎にかかるガソリン代や駐車場代」
「新しい楽譜の購入」
「演奏用に特別に用意した腕時計やハンカチ」
など、細かいけれど積み重なれば無視できない出費がいくつも出てきます。
とくに写真やDVDの購入は、当日その場で申し込む必要があることが多く、気がついたら「思い出だし…」と1万円近く申し込んでしまっていたなんてことも。
そうした支出を想定して、事前に「コンクール予算」をざっくりでも良いので組んでおくと、あとで慌てずに済みますよ。
費用面で無理をしない選択も大切に
「せっかくだからちゃんと揃えたい」と思う親心、すごくよくわかります。
でも、コンクールの意義はあくまで「音楽と向き合う経験」であって、高価な衣装や豪華な演出をすることではありません。
必要以上にお金をかけすぎてしまうと、親のストレスにもつながりますし、子どもにとっても「費用をかけているのだから失敗できない」と余計なプレッシャーになることがあります。
私はあるとき、「今回は手持ちの服でいいよ」と決めたことで、子どももリラックスして練習に集中できるようになりました。
必要なところにはしっかりかけつつも、
「ここは節約しよう」
「これは無理せず今あるもので」
と割り切ることも、コンクールを親子で楽しむためにはとても大切な視点だと思いますよ。
本番までの準備スケジュールと練習の進め方
3か月前から始める練習スケジュール例
「本番までに何をどれくらい準備すればいいの?」と不安になる方は多いと思います。
私も最初はまったく見当がつかなくて、ただ漠然と「とにかく練習しなきゃ」と焦ってしまいました。
でも実際は、期間を区切って少しずつ段階を踏んでいくことが、親子にとって一番安心できる方法なんですよ。
おすすめは3か月前からの逆算スケジュールです。
最初の1か月はとにかく「楽譜に慣れる・音を覚える」ことに集中して、2か月目は「表現をつける・リズムやテンポを安定させる」段階に入ります。
そして最後の1か月は「本番を想定した通し練習」や「人前で弾く練習」を繰り返すと、本番でも落ち着いて演奏できるようになります。
わが家でも「今週は右手だけ」「次の週は通してゆっくり弾く」など目標を細かく決めることで、子どもも自分の成長を感じながら進めることができました。
「今日はここまで弾けたね!」と毎日声をかけることで、小さな達成感が積み重なっていったのを今でも覚えています。
先生との連携ポイントとレッスン回数の増やし方
本番に向けては、先生との密な連携も欠かせません。
どの部分をどう仕上げていくか、何を優先して練習すべきかなど、先生の指導方針に沿って家庭でも練習を組み立てると、より効果的な仕上がりになりますよ。
とくに直前期になると「週1回のレッスンでは間に合わないかも」と思う場面が出てきます。
うちも本番2週間前からは週2回のレッスンに増やし、細かな表現の仕上げや集中力の持続練習に取り組みました。
ただ、ここで注意したいのが「無理のない範囲であること」です。
親の熱が入りすぎて子どもが疲れ切ってしまっては本末転倒ですし、先生と相談しながら「この子のペースに合った練習量」を考えることがとても大切です。
家での練習を続けるための工夫
「毎日コツコツやるのが大事」と頭では分かっていても、実際には子どもが気分屋だったり、親も忙しかったりで、思うようにいかない日もありますよね。
私も「今日はもう無理…」と、心が折れそうになる日が何度もありました。
そんなときに役立ったのが「練習を生活の一部に組み込む工夫」でした。
例えばわが家では「夕ごはんの前に10分だけピアノ」というルールを作ったんです。
最初はぐずっていた日もありましたが、習慣になってくると「今日の10分はここまで弾けた!」と子ども自身が達成感を感じるようになりました。
また、小さなごほうびもモチベーションの助けになります。
「今週3回練習できたら好きな絵本を1冊読もうね」なんていう約束も、子どもにとっては楽しい目標になりますよ。
体調管理と休養の大切さ
本番が近づいてくると、どうしても「もっと練習しなきゃ」「このままじゃ間に合わないかも」と焦ってしまいがちです。
でも、体が元気でないと、どんなに技術があってもステージでは本領を発揮できません。
特に子どもは疲れをため込みやすく、無理が続くと心まで不安定になってしまうこともあるんですよ。
私も過去に、練習に力を入れすぎて子どもが体調を崩し、本番を辞退したことがありました。
あのときの悔しさは今でも忘れられません。
だからこそ「休む勇気」も持っておくことが大切だと思うんです。
しっかり眠れているか、ごはんを楽しく食べられているか、笑顔が出ているか。
そうした日常の安定があってこそ、舞台でも堂々とした演奏ができるんだと実感しました。
練習を詰め込みすぎず、心と体のバランスを大切にしながら、親子で一歩ずつ準備を進めていけるといいですね。
親子の心構えとメンタルサポート
子どもの不安やプレッシャーを和らげる声かけ
子どもにとって、コンクールという非日常の舞台はとても大きなチャレンジです。
普段は楽しんで練習している子でも、本番が近づくと「失敗したらどうしよう」「みんなの前で間違えたら恥ずかしい」といった不安な気持ちが顔を出すことがあります。
そういうときに大切なのは、親がその気持ちを打ち消すのではなく、まず受け止めてあげることです。
「大丈夫、大丈夫!」と軽く言ってしまうと、子どもは「気持ちを分かってもらえていない」と感じてしまうこともあるんですね。
わが家では、「緊張するって、それだけ本気で向き合ってるってことなんだよ」「本番に出られるだけで、すごいことだよ」と伝えるようにしていました。
すると子どもは「そっか…そうかも」と、少しずつ安心していった様子でした。
心の中にある小さな不安を、言葉でなぞってもらえると、人ってすっと呼吸が深くなるんですよね。
親自身の気持ちの整え方と焦らない工夫
意外と見落としがちなのが、親自身のメンタルです。
子どものサポートをするつもりが、いつの間にか自分の方が緊張してしまったり、「もっと練習させた方がよかったのでは」と後悔の波に飲み込まれてしまったり。
私も本番前の夜に眠れなくなったことがあります。
でも、親が不安になればなるほど、その空気は子どもにも伝わってしまうんですよね。
子どもはとても敏感で、親の表情や声のトーンから「今日はお母さんピリピリしてるな…」と察してしまいます。
だから、まずは親自身が「うまくやらせること」よりも「見守ること」に意識を向けるようにしてみてください。
私は「今日は一緒にここまで来られてうれしいな」と声に出して伝えるようにしたら、自分の中でもスッと肩の力が抜けて、子どもにも自然と笑顔で向き合えるようになりました。
結果にとらわれずに、今日この時間を一緒に味わうこと。
それが本番前の親の心構えとして、一番大切だったなと思っています。
本番当日のトラブルに落ち着いて対応するために
コンクール当日というのは、普段とは違う緊張感や環境で、予想もしないトラブルが起こりやすいものです。
忘れ物、会場での迷子、衣装のトラブル、楽譜のページが外れるなど、小さなことでも子どもにとっては大きな事件に感じられることがあります。
うちも一度、会場直前で靴のストラップが壊れてしまったことがあったのですが、安全ピンと予備のゴムで応急処置をしてなんとか乗り切ったことがありました。
あのとき「焦らず対応できてよかったね」と子どもに言ってもらえて、なんだか泣きそうになりました。
事前にチェックリストを用意しておく、予備のアイテムを用意しておく、スケジュールに余裕を持って行動する。
そんな準備が、トラブルを乗り越える安心材料になります。
そして、何かあっても「大丈夫、なんとかなるよ」と親が落ち着いていることで、子どもも安心して舞台に向かうことができますよ。
結果に一喜一憂しすぎないための考え方
コンクールには順位や評価がつきます。
それは避けられないことですが、だからといって「賞をとること」だけが目的になってしまうと、終わったあとに心がついていけなくなってしまうこともあります。
我が家も一度、入賞できなかったときに子どもがふてくされて泣いてしまったことがありました。
そのとき私は、賞を取らせてあげられなかった自分を責めてしまったのです。
でも、時間がたって振り返ると「こんなに一生懸命に練習して、本番でがんばったことこそが、この子の宝物だったんだ」と思えるようになったんです。
結果はただの数字。
心を込めて音を届けた時間は、どんな評価よりも尊いと私は思います。
「よくがんばったね」「最後まであきらめずに弾ききってかっこよかったよ」と、終わった直後に伝えてあげてくださいね。
子どもの心に残るのは、親のその言葉です。
コンクールはゴールではなく、子どもにとっての学びと成長の通過点。
結果に振り回されず、そこまでの努力をしっかりと讃えてあげることが、何よりのメンタルサポートになりますよ。
当日までに揃えておきたい持ち物リスト
忘れがちな小物と予備アイテム
コンクール当日は、子どもも親もいつもより緊張していますし、慣れない場所での行動になるので、うっかり忘れ物をしてしまうことも少なくありません。
だからこそ、事前にしっかりと持ち物を確認しておくことが安心につながるんですよ。
まず忘れがちなのが「予備の楽譜」です。
万が一のトラブルに備えて、コピーを1部持っておくと安心です。
あと「衣装の替えボタン」や「靴擦れ対策の絆創膏」「髪留めの予備」なども持っておくと、現場で焦らずに済みます。
うちの娘は本番直前にカチューシャの飾りが外れてしまったのですが、たまたま持っていたヘアゴムで代用できて本当に助かりました。
慌ててしまうと子どもにも不安が伝わってしまうので、こうした「ちょっとしたトラブル」を事前に想定しておくと、親も気持ちに余裕が持てますよ。
他にも、演奏前に手が冷えてしまう子には「カイロ」や「小さなブランケット」、待ち時間が長くなりそうなときには「塗り絵や絵本」なども持っておくと安心です。
意外と控室が寒かったり、順番が押して時間が長引いたりすることもあるので、快適に待てる準備をしておくのがポイントです。
楽譜・衣装・おやつ・緊急用グッズ
コンクール当日の持ち物としては、まず第一に「楽譜(コピー含む)」と「衣装一式」。
衣装は前日に必ず試着して、破れや汚れがないかをチェックしておくと安心ですし、靴も当日初めて履くのではなく、何日か前から慣らしておくと転倒防止になります。
また、演奏前にエネルギー切れにならないよう「軽くつまめるおやつ」もおすすめです。
チョコやグミのように口どけがよくて汚れにくいものだと、手間もかからず便利ですよ。
ただし控室が飲食禁止のケースもあるので、そのあたりは事前に案内をしっかり確認しておいてくださいね。
そして「緊急用グッズ」として、絆創膏や安全ピン、ティッシュ、ウエットシート、髪用スプレーやコームなども忘れずに。
これらは小さなポーチにまとめておくと、すぐに取り出せて便利です。
私は初参加のときに、あれこれ詰め込みすぎて荷物がパンパンになってしまったことがありました。
なので、事前に「絶対必要なもの」「あると安心なもの」を分けてチェックリストを作っておくと、無駄なく準備が進められますよ。
コンクール当日は、荷物の多さ以上に「気持ちの余裕」が大切になります。
「これだけ準備してあるから大丈夫」と思えることが、親子の安心にもつながります。
完璧を目指しすぎなくていいので、ひとつひとつを丁寧にそろえて、子どもが気持ちよく舞台に立てるように整えていきましょうね。
まとめ:コンクールは子どもの成長の大切な一歩
音楽コンクールという舞台は、子どもにとってただの発表の場ではなく、それまでの時間すべてが「成長の通過点」になる貴重な経験です。
毎日の練習でつまずいたり、泣いたり、笑ったりしながら少しずつ前に進むその過程こそが、親にとっても子どもにとっても心に残る宝物になっていくんですよね。
正直に言うと、私も最初は「賞を取ってほしい」「上手に弾いてほしい」といった気持ちが強くて、子どもよりも私の方が力んでいたかもしれません。
でも本番が終わって、舞台から戻ってきた我が子の顔を見たとき、ふっと肩の力が抜けて「この子はこの舞台に立っただけで本当にすごいことをやり遂げたんだ」と素直に思えたんです。
うまく弾けたかどうかも大切ですが、それ以上に
「最後まで自分の音を届けようとしたこと」
「緊張しながらも諦めなかったこと」
「ひとつの目標に向かって努力し続けたこと」
…それらすべてが、その子の中にしっかり積み重なっていきます。
そしてその経験は、音楽だけでなく、これからの人生を支えてくれる力になると思うんです。
親としてできることは、完璧に整えてあげることではなくて、つまずいたときにそっと手を差し出せる存在でいることなんだと思います。
「できたね」「がんばったね」とその頑張りをまるごと認めてあげることで、子どもはきっとまた前に進んでいけますよ。
コンクールに挑戦するのは勇気がいることですが、その一歩を踏み出した親子には、きっとかけがえのない時間が待っています。
どうか焦らず、自分たちのペースで、あたたかい気持ちで歩んでいってくださいね。
応援しています。