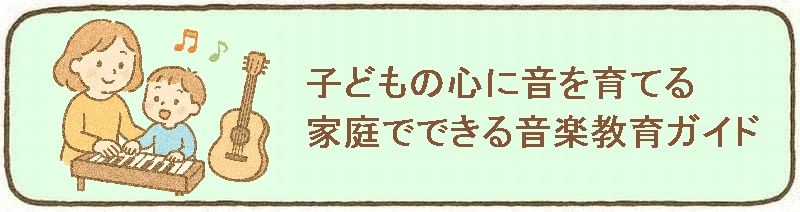合唱コンクールの季節になると、教室の空気が少しずつ変わっていくのを感じますよね。
放課後になるとピアノの音が響いて、子どもたちの声が重なっていく。
その光景はとても美しいものなのに、その裏側で誰にも言えない小さな不安や焦りを抱えている子がいることも、実は少なくありません。
特にソプラノやアルトといった高音・低音パートを担当する子どもたちは、心と体の両方に繊細な変化が起きやすい時期にいます。
声が出ないという悩みは、その子の努力ややる気の問題ではなく、成長や心理的な不安と深く関係していることも多いんです。
私自身、子どもが合唱コンクールに向けて練習していたとき、ある日突然「もう歌いたくない」とぽつりとこぼした姿を見て、胸が締めつけられるような思いをしました。
まわりの子が大きな声で歌っている中、自分だけ声が出ないという経験は、まだ心が柔らかい年齢の子どもにとってとても大きな衝撃になります。
自信を失い、心の奥に「自分は下手なんだ」という思いが静かに積み重なってしまうこともあるのです。
だからこそ、声が出ないことを責めたり焦らせたりするのではなく、その背景にある心と体のサインを見逃さないことが大切です。
合唱は声をそろえる競技ではあるけれど、子どもたちにとっては自分の気持ちを音に乗せる特別な体験でもあります。
たとえ声が出ない時期があったとしても、それは決して「できない子」という印ではありません。
その子が少しずつ自分の声と向き合い、自信を取り戻していくための大切な時間なんです。
この記事では、声が出ないときに親や先生がどう寄り添い、どんなサポートができるのかを、心の視点と具体的な対策の両面から丁寧にお話ししていきますね。
「ソプラノもアルトも出ない…」と感じたときにまず考えたいこと
合唱コンクールの練習が始まると、「どうしてあの子だけ声が出ないんだろう」といった声が聞こえてくることがあります。
ソプラノの高音もアルトの低音も、それぞれに難しさがあります。
でも、特に小学生の時期は、体も心もまだ成長途中で、大人が思うよりずっと繊細な理由で声が出にくくなることがあるんです。
たとえば、ちょっとした体調不良や声変わりの始まり、前の日に嫌なことがあって気持ちが沈んでいた、周りの視線が気になって緊張してしまった。
そんな小さな変化が、声の出方に大きな影響を与えることもあるんですよね。
声が出ないという状況を目の前にしたとき、私たちはつい「どうして歌わないの?」「もっと頑張って」と言ってしまいがちです。
でも、本当に大切なのは、その子が今どんな気持ちでそこに立っているのかを想像することからなんです。
「声が出ない=頑張っていない」と決めつけないで
声が出ないという状態は、決してその子が手を抜いているわけではありません。
実は、声が出ない子ほど「出さなきゃ」「迷惑をかけてるかも」と強く感じていて、心の中では必死に頑張っていることが多いんです。
私もかつて、クラスでソプラノを担当していたとき、声がかすれてうまく出せないことが続いたんですね。
そのときの「出せない自分はみんなの足を引っ張っているんじゃないか」というプレッシャーがどれほど苦しかったか、今でも覚えています。
だからこそ、周囲の大人が「出ない=怠けている」という誤解をしないことが、その子を守る大きな支えになります。
「出ない声」の裏にある“心の声”に気づくことが大切です
子どもたちは自分の気持ちをうまく言葉にできないことがあります。
「声が出ない」と言っていても、そこには
「本当は頑張りたいけどうまくいかない」
「恥ずかしい」
「失敗したくない」
といった複雑な感情が隠れていることが多いんです。
声が出せないという表面的な現象だけを見てしまうと、大切な“心の声”を見逃してしまうことになります。
親として、あるいは先生として、まずはその子の心の状態を感じ取ってあげる姿勢がとても大切なんですよ。
子どもは思っている以上に「まわりの目」を気にしています
「自分だけできていない」「先生に迷惑をかけているかも」「友だちに変に思われていないかな」。
小学生の子どもたちは、まだまだ未熟に見えても、実は心の中ではこうしたことを敏感に感じ取っているんです。
声が出ないこと自体よりも、それによって「悪く思われるかもしれない」という不安の方が強くて、それが余計に声を出しづらくさせていることもあります。
自信が持てなくなってしまう前に、まわりがあたたかく見守ることで、安心して声を出せる環境をつくってあげたいですね。
親の「気づいてあげたい」という姿勢が何よりの支えになります
声が出ない子どもにとって、家庭は最後の安心できる場所です。
学校で頑張ってきたあと、家で
「どうだった?」
「うまくいかなくても大丈夫だよ」
と声をかけてもらえるだけで、子どもはホッと肩の力を抜けるんですよね。
反対に、
「また声が出なかったの?」
「もっと頑張らなきゃ」
といった言葉が続いてしまうと、心はどんどん閉じてしまいます。
親が完璧な対応をする必要はないけれど、「ちゃんと見てるよ」「無理しなくていいんだよ」と伝えるだけで、子どもの心には安心が広がっていきますよ。
「出ない声」を責めるより、「そばにいること」を選んでみてください
声が出ない期間が長くなると、つい不安になってしまうこともあると思います。
でも、無理に「どうにかしなきゃ」と焦るよりも、今は一緒に寄り添って乗り越えていく時間なんだと捉えてみてくださいね。
私自身、声が出なかった時期に、何も言わずに隣に座ってくれていた母の存在に、どれだけ救われたか今でも思い出します。
アドバイスよりも、叱咤よりも、ただ“そばにいてくれる”という安心感が、子どもにとっては何より大きな力になるんです。
高音が出ない理由とは?ソプラノ・アルトで異なる原因と傾向
「なんであの子は声が出ないの?」そんなふうに感じたことがある方もいるかもしれません。
でも、その“出ない声”には、それぞれの子にとっての理由があるんですよね。
ソプラノとアルトでは、音の高さだけでなく、体の使い方や気持ちの動きにも違いがあるんです。
私もかつて合唱でアルトパートを担当していた時期がありましたが、
「声が低くて目立たないのがイヤ」
「本当はソプラノをやりたかったのに」
という感情が混ざって、うまく声が出せなかったことを今でも覚えています。
ただ技術の問題ではなく、心と体のバランスが崩れている時、声って驚くほど正直に反応するものなんですよね。
ソプラノが出ない子にありがちな声の特徴と体の状態
ソプラノは明るくて高い音域が中心になるので、のびやかな声を求められることが多いです。
でも、高音を出すためには、実はとても繊細な身体の使い方が必要になるんですよね。
特に息のコントロールや腹式呼吸がまだうまくできない小学生にとっては、どうしても喉だけで出そうとしてしまって、結果的に苦しそうな声になったりかすれたりしてしまうことがあります。
そしてその経験が「また失敗したらどうしよう」という不安につながってしまい、さらに声が出づらくなる悪循環に入ってしまうこともあるんです。
だからこそ、練習のときに無理に声を張らせるのではなく、
「リラックスしていいよ」
「ちょっとずつ慣れていこうね」
といった声かけが、心と体の負担をやわらげてくれますよ。
アルトの低音が苦手な子に多い「不安」と「戸惑い」
アルトは落ち着いた低めの音域を支えるパートで、表面的には目立ちにくいけれど、実はハーモニーの土台をつくるとても大事な役割です。
ただ、音程が取りづらい上に、他のパートにつられやすくて、自分の音が見つけられなくなる子も少なくありません。
特に女の子の場合、「声が低いのが変に聞こえるかも」と恥ずかしさを感じたり、「こんな声で合ってるのかな」と不安になったりして、声を出すこと自体にブレーキがかかってしまうんです。
私の知り合いの子も、「アルトって地味だし、自分がいなくてもバレないかも」って言って泣いていたことがありました。
でもその子の声が入ると、合唱全体の響きがぐっと安定して、みんなの歌が見違えるほど豊かになったんですよ。
そんなふうに、アルトを担当する子にも
「あなたの声がちゃんと届いてるよ」
「とても大事なパートだよ」
って伝えてあげることが、その子の背中をそっと支える力になります。
成長のタイミングと声の変化が重なることもあります
小学生の中学年から高学年にかけては、声変わりの入り口に差しかかる子も出てきます。
女の子でもホルモンバランスの影響で、声質が少し変わったり、いつもと違う感覚を覚えたりすることがあります。
男の子は早い子であればすでに声が揺らぎ始めていることも。
それに気づいていないまま「なんで出ないの?」と責めてしまうと、子どもはますます自分の体に自信が持てなくなってしまうんです。
だから、声が出にくくなった時期が「成長の合図」かもしれないという視点を持ってあげてほしいなと思います。
「大丈夫、体が変わる時期なんだよ」と伝えてあげるだけで、その子の不安はすっと軽くなることがあるんです。
声の変化に戸惑っているのは、子ども自身も同じですからね。
無理なく声を出せるようにするための練習法と声かけアイデア
「もっと大きな声で歌って!」と言われても、出ないものは出ないんですよね。
出せない自分を責めてしまって、ますます声が出しづらくなっていく…。
それは子どもだけでなく、見守る親としても苦しくなる瞬間だったりします。
実際、私の子どもも合唱の練習で何度も「うまくできない」と泣いて帰ってきたことがあって、そのたびにどう声をかければいいのか悩みました。
でも、そこで私が気づいたのは、声って“気持ち”にすごく左右されるんですよね。
だからこそ、技術よりもまず“安心して声を出せる空気”をつくってあげることが、いちばんの近道なんです。
声を出す前に心をほぐす:緊張を取るウォーミングアップ
本番に近づくにつれて、子どもたちの中に
「間違えたらどうしよう」
「失敗したらみんなに笑われるかも」
という緊張がじわじわと増えていきます。
そのまま声を出そうとすると、喉が固くなってしまって、余計に苦しくなるんですよね。
だから、声を出す前にまず心と体をほぐす時間をつくるのがおすすめです。
たとえば、顔をふにゃふにゃにして変顔をしたり、わざと変な声で歌って笑い合ったり。
そんなふうに笑いがあるだけで、体がゆるんで声の通りも変わってきますよ。
「いい声を出さなきゃ」と身構えるより、「まず楽しもう」から始めた方が、子どもの中にある“歌いたい気持ち”が自然と引き出されてくるんです。
毎日の練習が苦痛にならない工夫:ゲーム感覚で高音トレーニング
繰り返しの練習って、どうしても飽きやすいし、うまくいかないとどんどん嫌いになってしまうもの。
でも、少しの工夫で「やらされる練習」から「やってみたくなる練習」に変えられるんです。
たとえば、「音の階段ゲーム」といって、ドレミファ…と階段をのぼるように声を出していく遊びにすると、「あともう一段いけるかな?」と自分で挑戦したくなっていきます。
うちの子も、「今日は10段まで行けた!」なんて笑顔で話してくれるようになりました。
声を鍛えることはもちろん大事ですが、それ以上に「できた!」という小さな達成感の積み重ねが、自信にもつながっていくんですよね。
「出ない」より「出せた!」を育てる褒め方と励まし方
大人ってつい、「そこ違うよ」「もっとこうして」と直したくなっちゃうんですよね。
もちろんアドバイスは必要な時もあるけど、それ以上に子どもは“できたこと”を見てほしいんです。
たとえば、昨日より少し声が伸びただけでも、「今の、前よりすごくきれいだったね」と伝えると、その一言がぐっと心に残るんです。
私も、子どもが小さな声で歌っただけでも、「今日、ちゃんと聞こえたよ」と笑いながら声をかけていました。
そうすると不思議と、次の日は少しだけ声が大きくなるんですよね。
声が出るようになるために必要なのは、トレーニングよりもまず「自分の声を出していいんだ」と思える安心感なんです。
親や先生の「うれしい」「いいね」の一言が、その安心感の土台になりますよ。
「みんなと同じ」を目指すより「その子なりの一歩」に目を向けて
全員で声を合わせるのが合唱の醍醐味だとしても、その中で一人ひとりの成長スピードは違います。
「なんであの子だけ出てないの?」と比べてしまうと、どうしても苦しくなるんですよね。
大切なのは、昨日のその子と今日のその子を比べること。
「今日は1音だけでも高い声が出せたね」
「昨日より少し自信ある顔してたね」
そんなふうに、その子なりの一歩を見つけてあげることが、いちばん大きな応援になるんです。
私もつい周りの子と比べてしまって、落ち込んだ経験があるからこそ、今は「比べない見方」を心がけるようになりました。
そうすると、見える景色も、子どもの表情も変わってくるんですよ。
合唱練習で「出ない子」への対応で気をつけたいこと
合唱の練習が続いてくると、
「どうしてあの子はまだ声が出ないんだろう」
「このままで本番、大丈夫かな」
そうやって、まわりの大人もつい不安になってしまうことがありますよね。
でもそのとき、子ども本人がいちばん「どうにかしなきゃ」と思っていることも多いんです。
焦る気持ちはわかるけれど、無理に声を出させようとしたり、他の子と比べてしまうと、かえって逆効果になることもあるんですよ。
声が出ないときほど大切なのは、その子の“心の安全”を守ってあげること。
練習の質を高める以前に、「ここなら安心して声を出していいんだ」と思える場所をつくることが、いちばんの近道なんです。
無理に歌わせない、責めない、目立たせない
たとえ声が出なかったとしても、クラスの輪を乱しているわけじゃないし、やる気がないわけでもありません。
声が出ない子ほど、「出したいのに出せない」という葛藤を抱えているんですよね。
そんなときに、「どうして歌わないの?」とストレートに聞かれてしまうと、心がギュッと縮こまってしまって、ますます声が出なくなってしまいます。
無理に歌わせるのではなく、
「声は少しずつ出せるようになっていくものだよ」
「今は聴いてくれるだけでも大事な役割だよ」
と伝えてあげることで、その子の存在をちゃんと認めてあげることができます。
目立たせない配慮も大切です。
「一人で歌ってみて」といった場面では、できれば避けてあげたいですね。
子どもにとって“できない自分をみんなに見られること”は、思っている以上に怖いことなんです。
先生やクラスメイトとの関わりでつまずかないために
合唱は「みんなでつくる音楽」だからこそ、周囲の人との関係性が子どもに与える影響もとても大きいです。
たとえば、先生が無意識に「〇〇さんはもう大きな声で歌えてるのにね」と言ってしまったり。
クラスメイトの中に「声出してよー」と軽く言ってしまう子がいたりすると、それだけで心が閉じてしまうこともあります。
特に小学生の時期は、人間関係のバランスがすごく気になる年頃です。
だからこそ、大人が「できない子を責める空気」をつくらないことが本当に大切です。
「それぞれペースがあるよね」
「練習中は静かに見守ろうね」
と、クラス全体に優しい空気を広げていく工夫も必要ですよ。
みんなで支え合うという経験は、歌だけじゃなく、これからの人間関係にもきっと生きていきます。
家でもできるメンタルサポート:親にできることは?
学校でがんばっている子どもにとって、家は心を回復させる場所です。
だからこそ、家では「声が出たかどうか」よりも、「今日も練習、よくがんばったね」と、その努力に目を向けてあげてくださいね。
「声出た?」と聞かれるだけでプレッシャーに感じてしまう子もいます。
うちでは、帰ってきたらまず「おかえり」と言って、合唱の話は子どもから話し出すまで待つようにしていました。
時には、「今日はうまくいかなかった…」と涙ぐむ日もあったけれど。
そんな日は一緒にアイスを食べながら「つらかったね」と共感するだけで、翌日の表情が少し柔らかくなっていたりするんです。
親にできるいちばん大切なサポートは、「結果」を見守ることではなくて、「その子の感情」に寄り添っていくことなんですよ。
それでも不安なときは?第三者のサポートを検討してみて
どれだけ寄り添っていても、どれだけあたたかく見守っていても、
「このままでいいのかな」
「本当に声が出るようになるのかな」
と不安になってしまうこと、ありますよね。
実際、私もそうでした。
子どもが何度も悩んで立ち止まっている姿を見て、「もう少し違う方法があればいいのに」と思ったことが何度もありました。
そんなときに考えてほしいのが、親や先生だけで抱え込まずに“少し外の力”を借りてみるという選択です。
それは決して「家庭ではダメだった」ということじゃなくて、その子に合った新しいきっかけを見つけるひとつの手段なんです。
音楽教室やボイストレーナーの力を借りてみるのもひとつの方法
学校の合唱指導は、どうしても「みんなで同じように」という流れになりがちです。
でも、声が出ないことで悩んでいる子には、その子のペースや特徴に合わせたサポートが必要なこともあるんですよね。
最近では、子どもの発声に特化したボイストレーナーや、楽しく学べる音楽教室も増えていて、「苦手」を「好き」に変えるきっかけをもらえる場所もたくさんあります。
実際に私の知人の娘さんも、学校の合唱では自信がなかったけれど、個人レッスンを数回受けたことで、「声が出るって楽しい!」とキラキラした顔になっていったんです。
無理に通わせる必要はありませんが、「誰かに頼ってもいい」と思えること自体が、親子にとって大きな安心材料になりますよ。
成長過程による声の変化なら、焦らず見守ることも大切です
特に高学年の男の子や、成長が早い女の子には、声変わりやホルモンバランスの変化が影響していることもあります。
そうした変化は一時的なもので、数か月、あるいは一年のうちに自然と落ち着いてくることも多いんです。
だからこそ「すぐに解決しなきゃ」と焦らないで、「今はそういう時期なんだね」と捉えてあげることもとても大事な対応なんですよね。
うちの息子も、ある時期から声がかすれて出にくくなり、「僕、もう歌えないかもしれない」と泣いたことがありました。
でも半年ほど経ったら、何事もなかったようにまた大きな声で歌えるようになっていて、あのとき無理に練習を強いなくてよかったなと心から思いました。
「どうにかしなきゃ」ではなく「一緒に歩もう」の気持ちを忘れずに
子どもがつまずいている姿を見ると、なんとかしてあげたくなるのが親心。
でも、どうにかして“治す”ことよりも、「一緒に考えようね」「何か別の道もあるかもね」と言ってあげられることが、子どもにとっていちばんの救いになることもあります。
合唱が苦手でも、音楽そのものを嫌いになってほしくない。
そのためには、解決策を探すプロセスも、親子でゆっくり歩いていけるようなものであってほしいですよね。
第三者のサポートを受けるという選択は、親が無力だということではなくて、“子どものためにできることを増やす”という前向きな一歩なんです。
だから安心して、必要だと思ったら周りの手を借りてみてくださいね。
まとめ:声が出ない時こそ、心の声に寄り添うチャンスですよ
合唱コンクールの練習中、「声が出ない」という悩みは、ただの技術的な問題ではなく。
その子の心の状態や体の変化、さらには人との関わり方までが複雑に絡み合ったサインであることがほとんどです。
だからこそ、声が出ない子どもに対して「どうして出さないの?」と責めるような関わり方ではなく、
「どんな気持ちなんだろう」
「どんな不安を抱えているのかな」
そうやって、その子の内側にある思いに寄り添う姿勢が、なによりも大切になってくるんですよね。
私も、わが子が声を出せずに悩んでいたとき、「練習してるのに…どうして?」と戸惑ったことがあります。
でも、その子なりに頑張っていること、自分の中で必死に葛藤していることに気づいてからは、「声が出ること」ばかりを目標にするのではなく、「心がほぐれて、また歌いたいと思えるようになること」を目指すようになりました。
すると、少しずつですが表情が柔らかくなっていって、やがて自然と小さな声が漏れるようになったんです。
そのときのあの嬉しさといったら、たぶん一生忘れられません。
声が出ない時期って、親にとっても子どもにとっても苦しいし、不安になります。
でも、それは決して後ろ向きなことではなくて、子どもの心に寄り添い直すための、とても大切な“気づきの時間”でもあるんです。
「歌えなくても、あなたの存在は大切だよ」
「どんなときも、そばにいるよ」
そんなふうに伝えられることが、子どもにとっては大きな安心になって、少しずつ自分の声を信じられるようになっていくんですよ。
合唱コンクールは、ただ上手に歌うためのイベントじゃなくて、子どもたちが自分の声と、そして仲間とのつながりと向き合うかけがえのない時間です。
だからこそ、「出ない声」を責めるのではなく、その裏にある“心の声”に耳を澄ませてあげてくださいね。
焦らず、責めず、信じて見守っていく。
そうして過ごした時間は、子どもにとっても親にとっても、きっと心に残る宝物になりますよ。