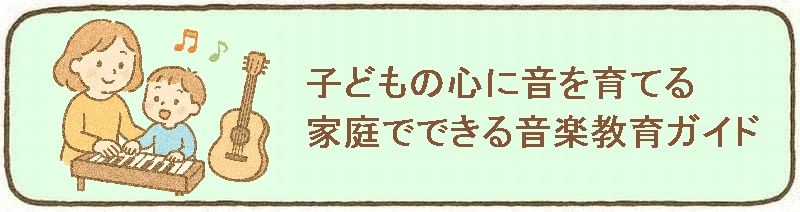「リコーダーの音が出ない…」そんなふうに悩むお子さんの姿を見たとき、親として胸がキュッと痛むことはありませんか。
授業では他の子の音が鳴っているのに、自分のリコーダーだけスースーと風の音しか出ない。
何度も挑戦してもうまくいかず、だんだん肩を落としてしまう姿を見ると
「どうして鳴らないのかな」
「このまま嫌いになってしまったらどうしよう」
そんなふうに心配になりますよね。
リコーダーは小学生にとって最初に向き合う本格的な楽器のひとつです。
音楽が好きになるか嫌いになるかの分かれ道にもなりやすく、最初のつまずきがその後のやる気や自己肯定感にも影響してしまうことがあります。
だからこそ家庭でのサポートはとても大切です。
ただ「練習しなさい」と声をかけるだけではなく、なぜ音が出ないのかを一緒に探して、子ども自身が安心して試せる環境を整えてあげることが、上達の近道になるんです。
私自身も子どもの練習を見ているうちに、単なる技術だけではなく心のサポートがどれほど大事かを実感しました。
できない悔しさや恥ずかしさを抱えている子に「大丈夫、ゆっくりでいいよ」と寄り添うことで、顔がふっと和らぎ吹き方が自然に変わっていく瞬間があるんです。
この記事では、そんな経験を交えながら音が出ない原因をわかりやすく解説し、親子で楽しく取り組める練習の工夫や声かけのコツをお伝えしていきます。
リコーダーが鳴ったときの「できた!」という笑顔を、親子で一緒に増やしていけるようなお手伝いができたらうれしいです。
リコーダーの音が出ないとき、親としてまず大切にしたいこと
リコーダーがうまく鳴らないというだけで、子どもは
「自分は下手なんだ」
「みんなの前で失敗して恥ずかしい」
と感じてしまいやすいものです。
特に小学生の時期は、周囲との違いや劣等感にとても敏感で、「できない自分=だめな自分」と極端に捉えてしまうことも少なくありません。
こうした自己否定の感情は、ただの音楽の授業の話にとどまらず、その子の自己肯定感や学校生活への姿勢、時には学習全体への自信にまで影響を与えてしまう可能性もあります。
だからこそ、親として「音が出ないことは恥ずかしいことではない」とまず安心させてあげることがとても大切なんです。
「どうして音が出ないの?」とつい原因を追及したくなる気持ちもよくわかります。
でもその前に
「うまくいかなくて悲しかったね」
「頑張って吹いてたの、見てたよ」
と、まずは感情に寄り添ってあげることで、子どもは「わかってもらえた」という安心感を持つことができます。
その安心感があってこそ、「もう一度やってみようかな」という気持ちが自然と湧いてくるんです。
努力や根性ではなく、心がほっとできること。
それがリコーダーに限らず、子どもの学び全体に通じる、土台になるんですよ。
「音が出ない=下手」じゃないんですよ
リコーダーの音が出ないのは、決して才能の問題ではありません。
むしろ、指の動きや息の加減など、子どもにとってはまだまだ発達途中の部分に原因があることがほとんどです。
それを「自分は下手なんだ」と思い込ませてしまうのは本当にもったいないこと。
たとえ音が鳴らなくても、その子なりに一生懸命取り組んでいることは間違いありません。
その姿を認めてあげることで、自己否定から自信への小さな一歩が生まれます。
「なんでできないの?」ではなく、
「やってみたんだね、えらいね」
「前より音に近づいてるよ」
そういった言葉をかけてあげると、子どもは安心して挑戦を続けることができます。
技術的なアドバイスよりも先に、まずは心を整えてあげる。
それが親にしかできない、とても大きなサポートになるんですよ。
焦らず、嫌いにならないようにサポートしてあげてくださいね
リコーダーに限らず、最初につまずいた経験が「嫌い」につながってしまうことってよくあります。
「また授業あるのか…」「どうせ鳴らないし…」そんな思いを持たせてしまうと、せっかく音楽に触れる機会が苦痛になってしまうかもしれません。
でも逆に、
「前よりちょっとだけ音に近づいたね」
「先生の吹いてるのと同じ音出たかも!」
という体験があるだけで、子どもの心はふわっと軽くなり、自然と音楽に前向きになっていくんです。
大切なのは、親が焦らないこと。
「早くできるようになってほしい」という思いは、知らず知らずのうちに子どもにプレッシャーを与えてしまうことがあります。
「あの子はもうできてるのに」という比較は、親子どちらの心も疲れさせてしまうだけ。
たとえ周囲と進み具合が違っても、その子のペースでじっくり寄り添ってあげることが、音楽を楽しむ力を育てていく土台になりますよ。
「できた!」を共有できる親子時間が宝物になるんです
うちの子も最初は「無理、絶対できない」と言って拗ねてしまう日が続きました。
でも、ある日ポンと音が出たときの目の輝きと笑顔は今でも忘れられません。
「鳴った!」「いま音出た!」と興奮気味に何度も吹いて見せてくれる姿に、私の方が感動してしまいました。
そんな小さな「できた!」の瞬間を親子で一緒に喜べること。
それこそが家庭で練習する最大のメリットなんだと思います。
学校では得られない安心感の中で、自分のペースで向き合える時間。
その経験が、リコーダーだけじゃなく「挑戦すること」そのものを楽しめる力にきっとつながっていきますよ。
リコーダーの音が出ない5つの主な原因とチェックポイント
リコーダーの音が出ないとき、つい「吹き方が悪いのかな?」と思ってしまいがちですが、実は小学生の子どもたちにとってリコーダーはとても繊細で難しい楽器なんです。
まだ指先が未発達だったり、力の加減がうまくできなかったり、原因はさまざま。
しかも子ども自身は「何が間違っているのか」がうまく言葉にできないことが多くて、それが悔しさや戸惑いにつながってしまうんですよね。
そんなときに大人が「ちゃんと押さえて」「もっと強く吹いて」などとアドバイスしても、子どもにとってはプレッシャーに感じてしまうこともあるんです。
だからこそ、まずは優しく一緒に原因を探すことから始めてみましょう。
ここでは、家庭でチェックできるリコーダーの音が出ない代表的な5つの原因と、親子で取り組める改善ポイントをご紹介していきますね。
指の押さえ方がゆるいと音が漏れてしまうんです
リコーダーの穴はきちんとふさがれていないと、空気が漏れてしまってきれいな音にはなりません。
よくあるのが「指の腹ではなく先っぽで押さえている」ケースで、子ども自身はふさいでいるつもりでも、わずかな隙間から空気が漏れてスカスカした音になってしまいます。
「しっかり押さえて!」と伝えるよりも、一緒に穴の上に指を置いて、ピタッとふさがっているかを確認してあげるのがコツです。
リコーダーを外して指を見せながら「ここに丸く跡がついてるかな?」と聞いてみると、子どもも感覚をつかみやすくなりますよ。
息の量や吹き方に慣れていない可能性もありますね
リコーダーは息を強く吹きすぎても、弱すぎてもきれいな音は出ません。
初めて触る子どもは「とにかく息を入れればいいんでしょ?」と思いがちで、全力で吹いてしまうことがよくあります。
すると「ピィーッ」と耳障りな音になったり、逆に弱すぎて何も鳴らなかったり。
ストローをそっと吹くような「フーッ」という息の量がちょうどいいんですが、それが意外と難しいんですよね。
そんなときは、親が実際に吹いて見せるのもおすすめです。
目の前で吹いて「これくらいの息だよ」と体感で伝えてあげると、子どもも真似しやすくなります。
リコーダーに汚れや破損がある場合もありますよ
意外と見落としがちなのが、リコーダー自体に問題があるケースです。
学校で貸し出されたリコーダーや数年使っているものは、内部にホコリや水滴がたまっていたり、ジョイント部分が緩んで空気が抜けてしまっていたりすることがあります。
特に冬場などは温度差で結露が発生しやすく、吹き口が濡れてしまうだけで音がかすれてしまうこともあるんです。
一度分解して洗ってしっかり乾かしてあげるだけで、見違えるように音が戻ることもあるので、定期的なお手入れはとても大切ですよ。
口や手のサイズと楽器が合っていないこともあるんです
まだ手が小さい低学年の子どもにとって、ソプラノリコーダーのサイズは案外大きく感じることがあります。
穴をすべてふさぐには指を広げないといけないし、無理な角度で握ってしまうと指が届かずに音が出にくくなります。
そんなときは、リコーダーを少し斜めに構えてもいいですし、椅子に座って安定した姿勢で構えるだけでもぐっと吹きやすくなることがありますよ。
「こう持たなきゃいけない」という正解を押しつけるよりも、「楽に吹ける持ち方を一緒に見つけてみようね」と柔らかく提案してあげることで、子どもも安心して試行錯誤できるんです。
緊張や苦手意識から「うまく吹けない」こともありますよ
最後に忘れてはいけないのが、心の状態による影響です。
授業中に周りの友達の前で吹くというだけで緊張してしまい、普段はできていたことも突然うまくいかなくなることがあります。
「いつもは鳴るのに今日はダメだった…」という日は、もしかしたら緊張や不安が原因かもしれません。
家ではできていたのに本番で失敗すると、自己否定や恥ずかしさでさらに苦手意識が強くなってしまうこともあります。
だからこそ、家庭では「失敗してもいいよ」「家では思いきりやってごらん」と安心できる場をつくってあげることが何より大切なんです。
親がニコニコ見守っているだけで、子どもはグッと吹きやすくなることがあるんですよ。
家庭でできる!音が出るようになる練習アイデアと声かけ
学校の授業だけではどうしても時間が足りなかったり、周りと比べて焦ってしまったりすることがありますよね。
家庭での練習は、そういったプレッシャーから少し離れて、自分のペースでリコーダーに向き合える大切な時間になります。
でも、ただ「練習しなさい」と言っても子どもの心はなかなか動かないものです。
特に音が出なくて困っている子にとっては、練習そのものが苦痛になってしまうこともあります。
だからこそ、親がそっと寄り添いながら、「音が鳴る楽しさ」を一緒に感じる工夫や声かけがとても大切なんです。
ここでは、私が実際に子どもと試して効果を感じた練習アイデアや、やる気を引き出す言葉のかけ方をご紹介しますね。
まずは「鳴る経験」を重ねてあげましょう
最初から曲を吹こうとすると、指使いや音程、リズムといろんな要素が重なってしまって、うまくいかないことの方が多いんです。
まずはドの音だけ、次はレまで、というように、ひとつずつステップを刻んで「ちゃんと音が鳴った!」という体験を積み重ねていくことが、子どもの自信につながります。
「できるようになった音」をリストにして一緒にチェックを入れていくと、見える形で達成感も味わえて、子どもの表情がどんどん前向きに変わっていくのが感じられますよ。
「ちょっとだけ練習」が毎日の積み重ねになるんです
長時間の練習は逆効果になることもあります。
子どもの集中力は思っているより短くて、5分~10分でも十分効果的です。
うちでは、宿題が終わったあとに「よし、リコーダーちょっとだけやってみる?」と声をかけて、1曲ではなく「1音だけ」「3回だけ」という小さな目標を一緒に決めて取り組みました。
そのほうがハードルが下がって、子どもも「これならやれるかも」と自然に吹き始めてくれましたよ。
何より「今日はここまでできたね」と毎日区切りをつけて終わることで、次の日も前向きに続けられるようになります。
親が「できた!」を心から喜ぶ姿が、子どもの原動力になります
「吹けるようになったね」「昨日より音がきれいだよ」と言葉にして伝えることはもちろん大切ですが。
でも、何より子どもが一番うれしそうだったのは、私が思わず拍手してしまったときや、パッと顔をほころばせて「すごいじゃん!」と声が出てしまったときでした。
「ママが喜んでくれた」という感覚が、そのまま次のやる気に変わっていくんですよね。
上達の速度よりも、親がどんなふうに向き合ってくれるかの方が、子どもにとってはずっと大きな支えになっていると感じました。
うまくいかない日があっても大丈夫だよと伝えてあげてくださいね
毎日うまくいくわけではありません。
「昨日できた音が今日は鳴らない。」
「昨日よりも不機嫌でやる気がない。」
そんな日は誰にでもあるし、むしろそれが普通です。
そういうときに「どうして今日はできないの?」と言ってしまうと、子どもはさらに自信を失ってしまいます。
私が心がけていたのは、「今日は疲れてるのかもね」「じゃあ今日はお休みにしてみる?」と提案してあげること。
その優しさが、翌日への前向きな気持ちにつながっていくんです。
焦らなくていい、比べなくていい。
その姿勢を家庭の中で大事にしていけるといいですね。
上達を助けるおすすめグッズや教材
リコーダーの練習は、努力だけでなく「ちょっとした道具の工夫」でグッと楽しく、やりやすくなることがあります。
学校の授業ではどうしても「みんな一緒のリコーダー」で「同じような進め方」になります。
でも家庭では、その子に合った補助アイテムや教材を使うことで、苦手意識をやわらげてあげることができるんです。
特に音が出にくくてつまずいている子にとっては「自分でも吹けるかも」と思えるような体験が、リコーダーへの気持ちを前向きに変える大きなきっかけになりますよ。
ここでは、実際に使ってよかったと思えるおすすめのグッズや教材をいくつかご紹介していきますね。
初心者向けリコーダーは「吹きやすさ」が段違いなんです
学校指定のリコーダーはスタンダードで万能ではあるけれど、息の強さにシビアだったり、指のサイズによってはふさぎにくかったりすることがあります。
初心者向けに作られているリコーダーは、息を入れたときに音が出やすいよう設計されていて、最初の「鳴らない…」という挫折を感じにくくなっています。
うちの子も、市販の軽めのタイプに変えてみたことで、初めてきれいに「ド」が鳴ったときにニコッと笑って「リコーダー、楽しいかも」って言ったんですよ。
少しでも「できる」感覚を味わえるようにしてあげることで、継続への意欲も変わってきますよ。
シールや指ガイドで「穴の場所がわかる」安心感を
まだ指の動きが不慣れなうちは、どこを押さえるのかがわからなくなって混乱することがよくあります。
そんなときは、穴のすぐ横に小さなシールを貼って「ここを押さえてね」と目印をつけてあげると、迷わずに構えられるようになりますよ。
教材によっては、ドレミの指番号が書かれたガイドシートがついているものもあります。
そうやって視覚からサポートしてあげることで、子どもが「次はどこを押さえればいいの?」と不安になるのを防げます。
少しの工夫で「わからない」が「わかる」に変わるんです。
YouTubeや音源付き教材で「お手本の音」を一緒に聞く時間をつくろう
リコーダーが苦手な子の中には、「どんな音が正解なのかよくわからない」という子も少なくありません。
自分の出している音が正しいのか、先生と同じなのか、比較する機会がないまま不安を抱えてしまうんです。
そんなときは、YouTubeやCD付きの教材などで実際の演奏を聞かせてあげると、「あっ、こういう音を目指せばいいんだ」とイメージがつかめるようになりますよ。
一緒に聞きながら「これ、かっこいいね」「これやってみる?」と声をかけてあげることで、自然と「やってみたい」という気持ちが生まれていきます。
ゲーム感覚で取り組める練習ノートやシール帳もおすすめです
子どもは楽しさがあるとぐんと伸びます。
練習したらシールを貼る、できた音をチェックして表にするなど、ゲームのように取り組める仕組みがあると、続けやすくなるんです。
うちでは「今日はドとレが吹けたら星マークね」とルールを決めて一緒にノートをつけていたら、自分から「今日は何の音に挑戦しようかな?」と計画するようになりました。
結果よりもプロセスを楽しむ姿勢が育っていくのがわかって、こちらも励まされましたよ。
練習がうまくいかないときの心のケアとサポートのコツ
リコーダーの練習をしていると、どんなにがんばっていても「今日はうまくいかないな」という日があるんですよね。
特に子どもは日々の体調や気分に左右されやすく、昨日できたことが今日はできない…そんなことで自信をなくしてしまうこともあります。
さらに、学校で友達と比べられたり、先生の言葉にプレッシャーを感じたりすることで、「私は音楽が苦手なんだ」と思い込んでしまうこともあるんです。
こうした心の揺れや不安に、大人が気づいて寄り添ってあげられるかどうかは、その子の「音楽との距離感」に大きく影響してきます。
うまくいかないときほど大切にしたい、心のケアと関わり方のポイントをご紹介していきますね。
「できない」はダメじゃなくて成長の途中ですよ
音が出ない日や、同じところでつまずくことがあっても、それは「ダメな日」じゃありません。
むしろ、できないからこそ気づけること、練習の意味、成長のチャンスがたくさんあるんです。
「昨日より今日はうまくいかなかったね。
でも、そこに気づけたのはすごいことだよ」と声をかけてあげるだけで、子どもの心はふわっとほぐれていきます。
失敗を否定せずに、「ここからどうするか」を一緒に考えるスタンスが大切なんです。
うちでも、泣きながら吹いていた日があったけれど、あとから「もう一回だけやってみる」と言った姿に、ぐっと胸を打たれました。
比べすぎず、子ども自身のペースを大切にしてあげてくださいね
つい他の子と比べてしまうこと、ありますよね。
でも、その子なりのリズムやタイミングがあります。
成長がゆっくりな子にはゆっくりなりの、発見や気づきがちゃんとあるんです。
「〇〇ちゃんはもう曲を吹けるのに…」という言葉が、無意識に子どもを追い詰めてしまうこともあります。
そんなときは、あえて「昨日の自分と比べてみようか」と提案してみるのもひとつの手です。
昨日より指が早く動いたとか、音がきれいに響いたとか、比べる対象を“他人”から“自分”にシフトするだけで、子どもの表情がガラッと変わることもありますよ。
「やめたい」と言い出したときの親の対応ポイント
「もうリコーダーやだ」「学校行きたくない」そんな言葉を聞くとドキッとしてしまいますよね。
でも、そう口にする裏には、ただ音が出ないという理由だけじゃなく、恥ずかしさや不安、人前で失敗する怖さなど、いろんな感情が混ざっていることがあります。
「やめたい」と言ったときはすぐに否定せず、「どうしてそう思ったの?」とやさしく尋ねてあげてくださいね。
そして、「つらかったね」「恥ずかしかったんだね」と気持ちをそのまま受け止めてあげてください。
気持ちが整理されると、「じゃあ、少しだけまたやってみようかな」と子ども自身から前向きな言葉が出てくることがあります。
無理やりやらせるのではなく、「気持ちが戻るまで待ってるよ」というスタンスでそばにいてあげることが、長い目で見て大きな信頼と安心感につながっていきますよ。
「できた」より「がんばったね」を見つけてあげてください
結果だけに目を向けてしまうと、できなかった日はがっかりするだけになってしまいます。
でも「昨日よりも長く練習できた」「嫌だって言いながらも吹いてみた」など、小さな努力や挑戦を見つけて褒めてあげると、子どもは驚くほど表情を変えます。
うちの子も「今日は途中で泣かなかったね」と声をかけたら、「そっか、それだけでもすごい?」と笑ってくれたことがありました。
上達よりも大事なのは、心が折れないように支えてあげること。
そして、練習の先にある「音楽って面白いな」という感覚を、親子でゆっくり育てていけたら素敵ですよね。
まとめ|音が出なくても大丈夫。大切なのは「楽しめる気持ち」
リコーダーの練習を見守る中で、私自身もたくさんのことを学ばせてもらいました。
最初は、ちゃんと音が出るかどうかばかりが気になって、「できている・できていない」に目が向いてしまっていたんです。
でも、うまくいかない日や涙を流した日、逃げ出したくなった日を一緒に乗り越えるたびに。
親としての関わり方や、子どもにとって何が本当に大事なのかを少しずつ感じ取れるようになりました。
音が出るかどうかは、確かに大事なことかもしれません。
でも、それよりもっと大切なのは「リコーダーっておもしろい」「なんか楽しいかも」と、子ども自身がその時間を前向きに感じられるかどうかです。
できたときの嬉しさ、誰かに聴いてもらえた喜び、「もう一回吹いてみようかな」と思えた瞬間。
そんな気持ちの積み重ねこそが、音楽と子どもをつなぐ一番の原動力になるんですよね。
練習がうまくいかない日は、きっとこれからもあります。
でも、そんなときこそ焦らず、比べず、「大丈夫、今日はここまでがんばったね」と声をかけてあげてください。
それだけで、子どもの中の小さな自信の芽が、また明日へとつながっていきます。
音が鳴ることだけをゴールにせず、親子で笑い合った時間や、できたときにハイタッチした感触を、どうか大切にしてあげてくださいね。
きっとその積み重ねが、リコーダーだけじゃなく、子どもがこれから出会っていく「ちょっとむずかしいこと」に向き合う力になっていきますよ。