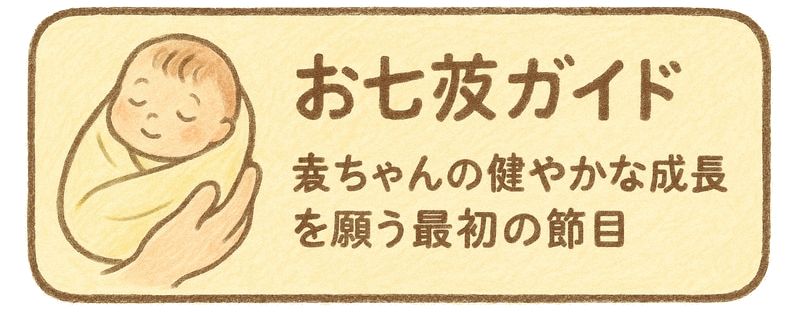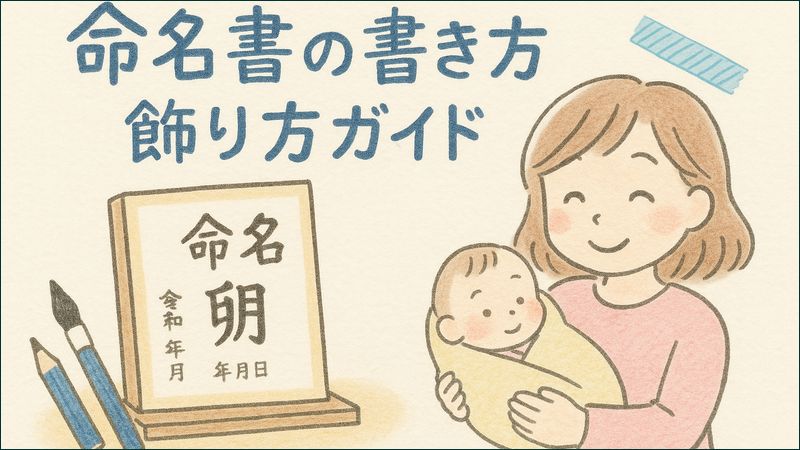
赤ちゃんの名前って、本当に不思議です。
たった一言なのに、そこに「家族の願い」や「これからの人生」が込められている。
だからこそ、初めてその名前を文字にして書く瞬間って、想像以上に胸が熱くなるんです。
「命名書」とは、その想いをかたちにした特別な一枚。
でも、いざ準備となると…
「筆で書くの?失敗したらどうしよう」
「オシャレに残したいけどセンスに自信がない」
そんなふうにモヤモヤと不安が出てくるのも自然なこと。
私も長女のときは、夜中に何度も「命名書 書き方」って検索していました(笑)。
それくらい、「間違えたくない!」という気持ちが強かったんだと思います。
だけど、最終的に完成した命名書をベビーベッドのそばに飾ったとき、
「この子にこの名前を贈ったんだ」って、心から実感できて、涙がにじんでしまったんです。
この記事では、そんな命名書の基本から応用まで、失敗しないコツと現代のアレンジ方法をたっぷりお伝えします。
あなたのご家庭らしい命名書作りのヒントになればうれしいです。
命名書ってなに?いつ使うの?
お七夜と命名書の深い関係
お七夜は「生後7日目」に行う伝統行事。
その日を境に「この子は元気にここまで育った」という区切りをつける意味がありました。
昔は新生児の死亡率が高かったため、7日間生き抜いたこと自体が大きな喜びだったんです。
だからこそ、命名書に名前を書いて、家族で祝うことは大きな意味を持っていたんですね。
今では医療が発達し、赤ちゃんの生存は当たり前のように思えますが、
「無事に7日を迎えた」という気持ちは、今も変わらず心に響くものです。
命名書はその象徴。
伝統を受け継ぎながらも、「今」を生きる私たちができる形で大切にしたいですね。
誰が書く?その選び方の意味
「命名書は誰が書けばいいの?」これは意外とよく聞かれる質問です。
昔は家長である父親や祖父が書くのが習わしでした。
でも現代では、「その家族にとって一番自然な人」が書けばOKです。
字が得意な人が書いてもいいし、パパとママで一緒に仕上げてもいい。
我が家の知人は「上の子が名前を書いた命名書」が家族全員のお気に入りになったそうです。
拙い字でも、そこにしかない愛情と物語が残るんですよね。
準備のタイミングも自由ですが、理想はお七夜の前日までに完成させておくこと。
余裕をもって練習しておくと、当日に焦らずゆったりと赤ちゃんを祝えます。
命名書の基本的な書き方
何を書く?最低限必要な内容
命名書の内容はシンプルで大丈夫です。
一般的には、
- 赤ちゃんの名前(中央に大きく)
- 生年月日(和暦・西暦どちらでも可)
- 命名日(お七夜の日)
- 命名者(父母の名前など)
この4点を押さえておけば十分。
ただ、家庭によっては「名前だけ」のシンプル版でも問題ありません。
むしろ最近は「余計な情報を省いてすっきり見せる命名書」が人気です。
レイアウトとバランスの工夫
命名書の見映えを左右するのは、「書き方のうまさ」ではなくバランスです。
名前を紙の中央に堂々と配置することで、全体が引き締まります。
命名日や生年月日は、右下や左下に控えめに書くと、メリハリが出ます。
「文字が大きすぎて紙からはみ出した…」なんてこともよくあるので、
一度コピー用紙に下書きして感覚をつかむのがおすすめです。
筆・ペン・印刷…何を選ぶ?
毛筆や筆ペンが定番ですが、必ずしもそうである必要はありません。
サインペンやボールペンでも問題ないし、パソコンでデザインして印刷するのも立派な命名書です。
実際、私の友人はCanvaを使って命名書を作り、背景に桜のイラストを入れたら「写真映え抜群」になっていました。
「字が苦手だから」と悩むよりも、「残したい形」に合わせて道具を選ぶ方がずっと心地よいですよ。
命名書をきれいに書くためのコツ
下書きは必須!安心のステップ
字がきれいに書けるかどうかは、正直センスより「準備の丁寧さ」で決まります。
薄く鉛筆で下書きをしておき、その上から筆ペンでなぞる。
これだけで失敗の確率はぐんと減ります。
また、マス目が印刷された下敷きを使うと、文字のバランスも取りやすいです。
「手書き風を残しつつ、仕上がりもきれい」な命名書にしたい人にはおすすめ。
テンプレートや代筆サービスの活用
「やっぱり字に自信がない…」
そんなときは、命名書テンプレートや筆耕サービスを使うのも立派な方法です。
最近はオンラインショップで「おしゃれな命名書テンプレート」がたくさん販売されています。
北欧風デザインや水彩タッチの背景がついた命名書は、飾るだけで部屋がお祝いムードになります。
また、プロの代筆サービスなら、数千円で一生ものの美しい命名書が手に入ります。
これは「手抜き」ではなく、「わが子にふさわしい一枚を用意する愛情の表現」なんです。
命名書の飾り方・場所の工夫アイデア
伝統的な飾り方と現代的な飾り方
命名書は昔ながらの神棚や床の間に飾るのが基本でした。
でも現代の家庭では和室がない場合も多いですよね。
その場合はリビングや玄関、ベビーベッドのそばなど、家族が自然に目にできる場所に飾るのがいいでしょう。
特にベビーベッドの横に飾ると、毎日名前を呼びながら「ここにいるんだなぁ」と実感できます。
私も朝起きてすぐ命名書が目に入るたびに、心があたたかくなるのを感じました。
おしゃれに演出するちょっとした工夫
100均グッズを使えば、命名書はもっと華やかになります。
- 木製フレームに入れるだけでナチュラルに
- 折り紙で桜や鶴を飾って和風に
- ガーランドやライトを添えて写真映えに
実際、私のママ友は「撮影用ブースを100均で作った」と言っていて、その写真がプロ並みで驚きました。
命名書はいつまで飾る?処分・保管の選択肢
飾る期間にルールはない
命名書を「いつまで飾るか」に正解はありません。
お七夜が終わったらすぐ片付ける人もいれば、初宮参りやお食い初めまでずっと飾る人もいます。
中には「1歳の誕生日まで飾っていた」という家庭も。
要は、「家族が納得できるタイミング」で良いんです。
我が家は気に入ってしまって、半年以上リビングに飾っていました(笑)。
処分と保管、それぞれの方法
- <保管するなら>
アルバムに収める、スキャンしてデータ保存、フレームに入れてインテリア化 - <処分するなら>
神社でのお焚き上げ、感謝を込めて家庭で処分
それだけで、命名書は単なる紙ではなく、思い出に昇華された宝物になります。
まとめ|命名書は「愛の形」であれば自由でいい
命名書は、伝統を大切にしつつも、今の暮らしに合わせて自由にアレンジできるものです。
字の上手下手も、フレームの値段も、実は大した問題じゃない。
そこにあるのはただ一つ、「この名前を贈る」という家族の愛情です。
どんな形でも、その一枚が「わが子の名前を初めて残した瞬間」だという事実は変わりません。
だからこそ、気負わずに「わが家らしい命名書」を作ってみてください。
どうか、あなたのお七夜が「やってよかった」と思える特別な一日になりますように。
赤ちゃんの名前が、ご家族の笑顔とともにいつまでも輝き続けますように。