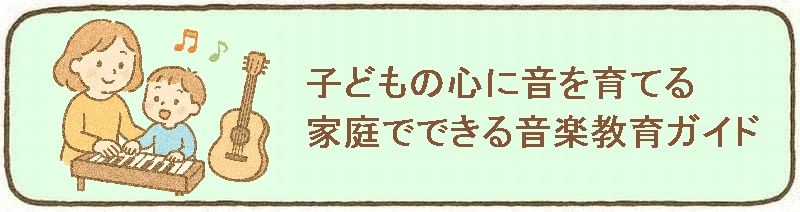「うちの子、音楽の授業がイヤなんだって」そんなふうにぽつんとこぼした我が子の一言に、思わず胸がギュッとなってしまったことはありませんか?
親としては、できればどんな教科も楽しんでほしいし、学校での時間がつらいものにはなってほしくない。
でも、実際は
「歌うのが恥ずかしい」
「リコーダーの音がうまく出せない」
「楽譜が読めない」
そんな小さなつまずきが積み重なって、子どもなりに「音楽=苦手」と思ってしまうことがあるんですよね。
そしてその裏側には、失敗への不安や「まわりと比べられる怖さ」が潜んでいることも。
だからこそ、ただ「練習しなさい」と言うのではなく、まずは親が“安心していいよ”という空気をつくってあげることがとても大切なんです。
音楽の授業が苦手でも大丈夫。
家庭でできるちょっとした声かけやサポートが、子どもの心をふわっとやわらかくして、「イヤだな」が「ちょっとならできるかも」に変わっていくこともあるんです。
この記事では、そんな日常の中でできる優しいサポートのヒントを、体験談もまじえてお届けしますね。
どうして「音楽の授業が苦手」になるの?
音楽の授業って、本来は自由に表現したり、楽しんだりするもののはずなのに、なぜか苦手意識を持ってしまう子が一定数いますよね。
親としては「なんでだろう」「何かあったのかな」と気になってしまうものです。
でも実は、音楽の授業が苦手になる背景には、さまざまな“見えにくい理由”が絡んでいることが多いんです。
ただ単に「音楽が嫌い」「やる気がない」という表面的な理由だけではなくって。
そこには“失敗を恐れる気持ち”や“自信のなさ”、“まわりとの比較”など、子どもなりの複雑な心の動きがあるんですよ。
ここでは、よくあるケースを例にしながら、子どもたちがなぜ音楽を苦手と感じやすいのかを掘り下げていきますね。
よくある悩み① 歌うのが恥ずかしい・声が出せない
歌うことって、思っている以上に「自分をさらけ出す」行為なんです。
特に小学生の中学年以上になると、自意識が強くなってきて
「変な声って思われたらどうしよう」
「間違えたら笑われるかも」
といった不安が先に立ってしまって、思いきり声を出すことができなくなってしまうことがあります。
実際、うちの娘も4年生くらいのときに「音楽の時間、声が出ない」とぽつりと話したことがありました。
家では大きな声で歌っていたのに、学校という集団の中ではどうしても周囲の目が気になってしまうんですよね。
よくある悩み② リズム感や音程がつかみにくい
「音楽ってセンスがいる教科だから…」とあきらめてしまう親御さんもいますが、実際には多くの子が、育ってきた環境や経験によって音感やリズム感の差があるだけなんです。
ただ、テンポが合わなかったり音程がズレたりすると、周りからの視線が気になって恥ずかしくなってしまって、その経験が「苦手」の意識に結びついてしまうんですね。
とくに目立ちたくない子ほど「失敗したくない」という気持ちが強くて、自分から積極的に表現しようとすることを避ける傾向が見られます。
よくある悩み③ 楽譜が読めない・記号が難しい
楽譜を読むというのは、ある意味「音楽の読み書き」です。
だけど、国語や算数のように段階的に習っていくわけではなく、突然「この音符を読んで、演奏してね」と求められることが多いので、わからないまま授業が進んでいってしまう子もいます。
音符や休符、強弱記号などは、大人にとっても最初は難解に感じるもの。
もし理解が追いついていないのに誰にも聞けなかったとしたら、ただ座っているだけの“つらい時間”になってしまっても不思議ではありません。
よくある悩み④ まわりと比べて自信がなくなる
音楽の授業は、他の教科と比べて「見られる」「聞かれる」機会が圧倒的に多いです。
声を出す、リコーダーを吹く、みんなの前で歌う、こうした一つひとつの場面で、自然と「できる子」と「できない子」の差が浮き彫りになってしまいやすいんですよね。
それが子どもにとってはすごくプレッシャーになることがあります。
本人は一生懸命取り組んでいても、周囲の子がすんなりできていたり、先生に褒められていたりするのを見ると、「やっぱり自分はダメなんだ」と感じてしまい、自信を失ってしまうこともあるんです。
よくある悩み⑤ 先生やクラスの空気に合わないとき
これは意外と見落とされがちなんですが、音楽の授業そのものよりも、「その授業の空気」が合わなくてつらいというケースもあります。
たとえば、先生の指導スタイルが厳しかったり、「間違えること」に対して厳しく反応される環境だったりすると、それだけで委縮してしまう子もいます。
また、クラスの中で「できる子」たちが目立っていて、自分は取り残されているような感覚を持ってしまうと、ますます参加しづらくなってしまうこともあります。
音楽の授業が苦手だと感じる背景には、こうしたたくさんの小さな「つまずき」や「心の壁」があります。
でも、苦手に見えるその裏には、ほんの少しの不安やプレッシャーが隠れているだけで、決してその子自身の“才能のなさ”ではないんです。
だからこそ、私たち大人が「何がこの子の気持ちを重くしているのかな?」とそっと想像してみることから、子どもを支える第一歩が始まっていくんですよ。
家庭でできる“気持ちのサポート”
子どもが「音楽の授業が苦手」と感じたとき、それをどう受け止めるかで、その後の気持ちの持ち方や向き合い方が大きく変わってきます。
大人が想像する以上に、子どもにとって学校での1時間1時間はとても濃密で、その中で「できない自分」や「恥ずかしい気持ち」に直面することは、強いストレスにもなりやすいんですよね。
だからこそ、家庭の中だけでも“ありのままの自分でいていい”という空気を感じられることが、とても大きな支えになります。
ここでは、日々の中でできる「気持ちのサポート」について、一つずつ見ていきましょう。
「苦手でもいいよ」と伝える安心感
「音楽が苦手でも大丈夫だよ」「できないことがあっても全然いいんだよ」
そんなふうに、まずは“できなくても責められない”という安心感を伝えてあげることが、子どもにとっての大きな土台になります。
子どもは、親がどう受け止めてくれるかで、自分の価値を無意識に判断していることが多いんです。
私自身、子どもが「どうせ僕は下手だから」と言ったとき、「それでも歌ってみようと思ったのがすごいよ」って声をかけたら、ほんの少しだけ目が柔らかくなったのを今でも覚えています。
できるできないではなく、その子が「やってみよう」と思えたこと自体が尊いんですよね。
音楽以外の得意を認めてあげよう
人にはそれぞれ得意不得意がありますし、それが自然なことです。
でも学校という場では「なんでもまんべんなくできること」が求められがちで、苦手なことばかりに目が向いてしまう子もいます。
だからこそ、家庭では“得意なことを再確認できる場”であってほしいと思うんです。
「絵が上手だね」
「文章の表現が豊かだね」
「人の話をよく聞けるところ、素敵だね」
そんなふうに、音楽とは関係ない分野でもしっかり褒められると、子どもの心はふっとほぐれていきますよ。
自信は、自分の好きや得意からしか育っていかないんです。
小さな“できた!”を一緒に喜ぶ習慣
子どもって、自分ひとりでは「できた!」を実感しにくいことがあります。
大人にとっては些細に思える進歩でも、子どもにとってはとても大きな一歩だったりするんですよね。
だからこそ、「さっきのリズム、合ってたね!」「今の音、きれいだったよ」と声をかけて、一緒にその一歩を喜んであげてください。
繰り返すうちに子どもは、「できない」よりも「できたかも」の感覚を持てるようになっていきます。
小さな成功体験を重ねることが、苦手の意識をゆっくりほどいていく力になるんですよ。
無理に上手を求めず、楽しめる空気を
大人がつい「もっと大きな声で!」「音程をしっかり取って!」と求めすぎてしまうと、子どもは「できなきゃダメなんだ」と感じてしまい、余計に委縮してしまいます。
私も昔、子どもにリコーダーの練習をさせようとして、「違うってば、こう!」と口うるさく言ってしまったことがありました。
結果、子どもはリコーダーを触るのも嫌がるようになってしまって、心から反省しました。
だからこそ、正しさよりも「楽しめたかどうか」を大切にすることが、心の成長には何よりも大事なんです。
上手くなることよりも、「またやってみようかな」と思える雰囲気が、子どものやる気をゆっくり育てていくんですよ。
子どもが「音楽の授業がつらい」と感じているとき、それを真正面から変えようとしなくてもいいんです。
家庭の中で「ここではそのままでいて大丈夫だよ」という空気を感じられるだけで、子どもは安心し、自分でその苦手と向き合う力を少しずつ育てていくことができます。
大切なのは、親が“なんとかしてあげなきゃ”と力むことではなく、“そばにいるよ”という安心感を伝えること。
それこそが、何よりの「気持ちのサポート」になるんですよ。
家庭でできる“具体的な学習サポート”
音楽の授業が苦手な子どもにとって、「何をしていいかわからない」状態がいちばんつらいんですよね。
でも、ほんの少しの予習や体験、日常の中での関わりだけでも、子どもの気持ちはグッと軽くなることがあります。
特別な教材やスキルがなくても大丈夫。
家庭だからこそできる、やさしい学習サポートのヒントをここでご紹介していきますね。
音符や記号が苦手な子にはカードやアプリも◎
楽譜を読むのって、大人でも最初は混乱してしまいますよね。
「ド」「レ」「ミ」の位置、拍の長さ、シャープやフラットの記号…。
でも、これを“教科書だけ”で覚えるのは、子どもにとってとても負担です。
そんなときは、音符カードやリズムカード、楽しく学べる音楽アプリなどを取り入れて、ゲーム感覚で触れていくのがおすすめです。
目で見て、手でめくって、耳で音を聞きながら覚えると、感覚的に身についていくんですよ。
うちの息子も、音符の位置がわからないときに「どこかな?カードで探してみて」と声をかけたら、遊びのような感覚でどんどん覚えていきました。
興味を引く“入り口”をつくってあげるだけで、子どもの吸収力は驚くほど変わってきますよ。
苦手な歌はお風呂や家で小さく口ずさむ練習から
「大きな声で歌いなさい」と言われるほど、余計に声が出せなくなってしまう子もいます。
だからまずは、リラックスできる場所で、自然に口ずさむような時間をつくってあげてください。
たとえばお風呂の中や、寝る前のリラックスタイムに「この曲、好きなんだよね」と一緒に歌ってみるだけで、子どもの中の“音楽=緊張”というイメージが少しずつ変わっていくんです。
完璧な音程や歌い方を目指す必要はまったくなくて、「歌ってみたいな」「ちょっと楽しいな」と思える経験を積み重ねていくことが大切なんです。
私の娘も、教科書の歌をお風呂で何となく歌っていたのをきっかけに、授業中にも少しずつ声を出せるようになっていきましたよ。
リズム感は手拍子遊びやダンスで気軽に
リズム感を身につけるには、楽器を使うよりも、まずは体を使った遊びが一番効果的なんです。
手拍子、足踏み、簡単なステップ。
こうした遊びを通して、リズムの「感覚」を身体で覚えていくことで、授業でのリズム練習もグッとラクになります。
難しく考えなくても、音楽に合わせて体を動かすだけでOK。
「ピッタリ合ってなくても楽しいね」と笑いながら一緒にやってみてください。
うちでは、好きなアニメのオープニングで“手拍子大会”をするだけでも、子どもがどんどんリズムに乗れるようになっていきました。
遊びの中に学びを自然に混ぜていくことで、苦手意識もやわらいでいくんです。
学校の授業内容を家庭で“ちょっと先取り”しておくと安心
授業で突然新しい曲が出てきたり、初めての楽譜を渡されたときに「なにこれ、知らない…」という感覚になると、それだけで不安や拒否感につながることがあります。
だからこそ、授業で出てくる内容を、ほんの少しだけ家庭で先に触れておくだけでも安心感がまったく違ってくるんです。
教科書に載っている曲を先に聞いておいたり、リコーダーの音を出す練習を少しだけやってみたり。
「聞いたことがある」
「ちょっとやったことがある」
それだけで、子どもは「知らないことに飛び込む怖さ」から解放されて、授業にも前向きに向き合えるようになるんですよ。
子どもにとって、音楽の授業が「苦手なもの」として記憶に残ってしまうのは、とてももったいないことだと思うんです。
ほんの少しの工夫で、音楽が「難しいもの」から「ちょっと面白いもの」へと変わることは十分にあります。
親ができることは完璧な指導じゃなくて、苦手を遠ざけない“ちょっとしたサポート”。
その積み重ねが、子どもにとっての「自信の芽」を少しずつ育てていくんですよ。
「できない」より「楽しめた」でOK|評価や成績との向き合い方
子どもが「音楽が苦手」と言い始めたとき、多くの親が頭をよぎるのが「通知表の評価、大丈夫かな…」という不安です。
特に小学生のうちは、「苦手を放っておいていいのかな?」「ちゃんと授業についていけてるのかな?」と心配になってしまいますよね。
でも実は、音楽の成績や評価には、他の教科とは少し違う大切な視点があるんです。
ここでは、音楽の成績にどう向き合えばよいか、そして数字や評価よりもっと大切にしたい“子どもの心の成長”について、一緒に考えてみましょう。
音楽の評価は“相対”ではなく“成長”が見られている
学校の音楽の評価って、「歌が上手いか」「リズム感があるか」だけで決まるわけではありません。
実は先生たちは、その子なりの「取り組む姿勢」や「前より少しでもできるようになったか」という“成長の過程”を見てくれていることが多いんです。
だから、声が小さくても、歌詞を覚えられなくても、「今日は勇気を出して声を出せた」という一歩が、しっかり評価につながっていることもあるんですよ。
親がその点を理解していると、子どもへの声かけも変わってきます。
「がんばってたね」「前より楽しそうだったよ」と言ってあげることで、子どもは“できたこと”に目を向けられるようになっていくんです。
成績よりも「音楽って面白いかも」で十分な価値
子どもの未来を考えたとき、音楽の通知表が「A」か「B」かよりも、「音楽ってちょっと楽しいかも」と感じられる経験の方が、よっぽど価値があると思うんです。
評価は一時のものでしかありませんが、「嫌いにならなかった」「少し好きになった」という感覚は、子どもの中にずっと残っていくんです。
音楽に限らず、何かを「楽しむ力」って、大人になってからの人生を豊かにする土台になりますよね。
「できた」「できない」にとらわれすぎず、まずは「好き」や「おもしろい」を一緒に探していけるような関わり方ができたら、それだけで十分に価値ある学びになっているんですよ。
先生との面談で伝えておくとよいこと
もし、子どもが音楽の授業に強い不安を感じているようなら、その気持ちを担任や音楽の先生にさりげなく伝えておくのもひとつの方法です。
たとえば
「声を出すのが恥ずかしくて固まってしまうようです」
「家ではリコーダーを練習しているんですが、授業では緊張してしまうようです」
といった具体的な情報があると、先生もその子に合わせた対応を考えてくださることがあります。
学校と家庭がつながっていれば、子どもも「わかってもらえている」と感じて、少しずつ安心して授業に向き合えるようになっていくんですよ。
評価や通知表の数字にとらわれてしまうと、「どうにか成績を上げなきゃ」と焦ってしまう気持ちもわかります。
でも、今この時期に大切にしたいのは、
「音楽を嫌いにならないこと」
「ちょっとだけ楽しめるようになること」
その気持ちを育てることこそが、子どもの心に一生残る“学びの土台”になるんです。
できるかどうかより、楽しめたかどうか。
そこに目を向けていけたら、子どもにとっても、親にとっても、音楽の時間はずっとやさしいものになっていきますよ。
親の不安もやわらげよう|一緒に「苦手」を受けとめる姿勢
子どもが「音楽が苦手」と感じているとき、実は一番揺れているのは親の心かもしれません。
「このままで大丈夫かな?」「ちゃんと学校でやっていけてるのかな?」そんなふうに、心のどこかがずっとソワソワしてしまうんですよね。
でもその不安、決して間違いじゃないし、放っておいていいものでもありません。
親の心が不安定なままだと、どうしても子どもにもその焦りが伝わってしまって、余計にプレッシャーをかけてしまうことがあるんです。
だからこそ、“親の不安にも寄り添うこと”が、実は子どもへの最高のサポートにつながっていくんですよ。
親の「大丈夫だよ」の一言が子どもの心を支える
「大丈夫だよ」このたった一言に、どれだけの力があるかを、私は何度も子どもに教えられました。
泣きそうな顔で帰ってきた日も、自信なさげに課題を見せてきた日も、「うまくできなくても大丈夫。
今はそれでいいんだよ」と伝えるだけで、子どもの顔が少し和らぐのが見えるんです。
親は何か“してあげる”ことに一生懸命になりがちだけど、ただ“そばで信じて見守る”ということが、子どもの安心感を育てる大きな力になるんですよ。
得意不得意は誰にでもあると伝えていこう
私たち大人だって、すべてが得意なわけではないですよね。
運動が苦手な人もいれば、人前で話すのが苦手な人もいる。
音楽が苦手なことも、まったく恥ずかしいことじゃないし、むしろ当たり前のことなんです。
「お母さんも昔は歌うのがちょっと苦手だったよ」と、自分の体験を交えて話してあげると、子どもは「そうなんだ」とホッとすることがあります。
完璧でなくていいこと、失敗しても平気なこと、それを親がまず体現して見せてあげられるといいですよね。
音楽を楽しむ家庭の雰囲気が何よりの応援になる
家庭の中に「音楽って楽しいね」という空気があるだけで、子どもの音楽への印象はガラリと変わります。
上手に歌えなくても、音程がズレていても、
「いい声だね」
「その曲、家でも歌ってくれてうれしいな」
そんなふうに、音楽が評価や結果ではなく“感情とつながるもの”なんだと感じられる場面を作ってあげてください。
テレビから流れてくる曲に一緒に口ずさむ、手拍子をしてみる、たまには家族で歌を歌ってみる。
それだけで、音楽が“苦手な教科”ではなく、“身近で温かい存在”に変わっていくんです。
子どもの苦手を前にしたとき、親としてできることは限られているように感じるかもしれません。
でも「わかるよ」「そばにいるよ」「一緒に乗り越えていこうね」という姿勢そのものが、子どもにとっての安心そのものなんです。
無理に克服させようとしなくても大丈夫。
まずは親が落ち着いて、その“苦手”を一緒に受けとめてあげられたら、それだけで子どもはきっと、自分のペースで前に進んでいけるようになりますよ。
まとめ:音楽の授業が苦手でも大丈夫|子どもに寄り添うことが一番のサポート
音楽の授業が苦手だと感じている子にとって、その1時間はとても長く感じられるかもしれません。
きっと、その子なりに「がんばらなきゃ」と思っているし、「うまくできない自分」を責めてしまっていることだってあります。
だからこそ、親ができる一番のサポートは「大丈夫だよ」「あなたのままでいいよ」と、安心を届けてあげることなんです。
上手にできるようにさせることがゴールではなくて、たとえ苦手でも音楽に対する“嫌い”が少しでもやわらいで、「ちょっとなら楽しめるかも」と思えるようになること。
それこそが、子どもにとっての大きな一歩であり、成長の土台になるんですよ。
この記事では、「どうして音楽が苦手になるのか」という心の背景から、家庭でできる気持ちの寄り添い方や学習の工夫、そして親の不安との向き合い方までを一緒に考えてきました。
どれもすぐに結果が出るような“特効薬”ではないかもしれません。
でも、日々の中で少しずつ積み重ねていけるやさしいサポートばかりです。
子どもは「できるようになること」よりも、「安心できる場所があること」でぐっと前を向けるようになります。
親の焦りや不安があるときこそ、「今のこの子に必要なのは何だろう?」と立ち止まってみることが、いちばんの愛情になるんですよ。
音楽が得意でも苦手でも、その子の価値はまったく変わりません。
できないことを責めるのではなく、その気持ちに気づいて寄り添ってあげることが、子どもにとって一生の安心につながっていきます。
だから、今日も「できなくてもいいよ」と、笑顔でそばにいてあげてくださいね。
きっとその言葉が、子どもの背中をそっと押してくれますよ。