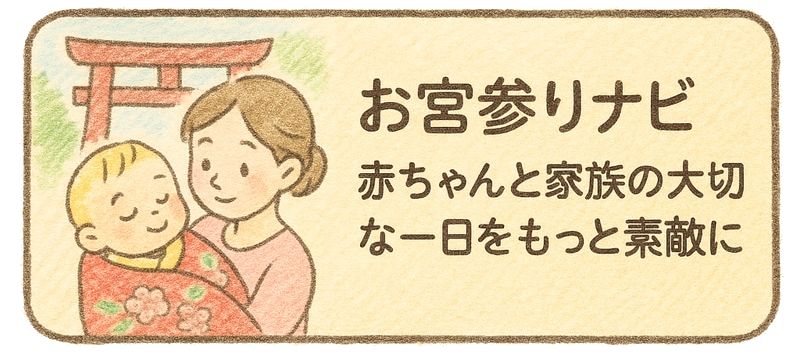「気づいたらもう生後4か月…お宮参り、すっかり忘れてた…」そんなふうに焦って検索しているママさん、今ここにいますか?(私もやらかしました…笑)
出産してからの毎日って、ほんとうに目まぐるしいんですよね。
赤ちゃんのお世話に追われて、夜泣きに振り回されて、自分のことは後回しになって、それでもなんとか今日を乗り越えるのに精一杯で…。
そんな中で、「あれ?お宮参りっていつだったっけ?」と思い出したときには、すでに時期が過ぎていた…なんてこと、正直よくあります。
私自身も、「やらなきゃやらなきゃ」と思いながら、家族の予定が合わなかったり、雨が続いたり、気づけば2ヶ月以上が経過。
「これって…もうダメなやつなの?」って、ちょっとした罪悪感まで湧いてきたりして。
でもね、安心してください。
お宮参りって、形式よりも気持ちが大切なんです。
そもそも「絶対この日までに!」なんてルールはないし、むしろ今は“家族のペースでゆっくりやる”のが当たり前になってきています。
この記事では、「お宮参りが遅れたとき、どうすればいい?」「今さら行っても大丈夫?」という不安や疑問に寄り添いながら。
遅れてしまったからこそできるお祝いの形をご紹介していきます。
一緒に“うちのタイミングで、うちらしく祝う”方法を見つけていきましょうね。
お宮参りが遅れてしまうことはよくある
体調・天候・家族の都合で延期は珍しくない
お宮参りの時期って、昔は「男の子は生後31日目、女の子は33日目」などの決まりがあったけれど、今はもうそこまでガチガチじゃありません。
時代の流れとともに、家族のあり方やライフスタイルも変わってきて、「必ずこの日までに」という風潮もずいぶん柔らかくなってきました。
たとえば
「ママが産後で動けない」
「赤ちゃんが黄疸で通院中」
「天気がずっと雨だった」
「お兄ちゃんお姉ちゃんの学校行事と重なった」
…など、ちょっとしたことで予定ってすぐズレますよね。
特に初めての育児となれば、予想外のことが次々に起こるのが当たり前。
スケジュールをきっちり守るなんて、正直ムリゲーです。
私の知り合いのママも、出産後に気分が落ち込みやすくなってしまって、お宮参りの話を聞くだけで「そんな余裕ないよ…」と泣いてしまったと言っていました。
でも春になって、少しずつ心が元気になってきた頃、「そろそろ行ってみようかな」と決めたそうです。
そのときの写真、見せてもらったんですが…赤ちゃんの笑顔がまぶしくて、パパとママの表情もどこかほっとしていて、こちらまで温かい気持ちになりました。
「遅れた」というより、「ようやく迎えられた日」なんですよね。
「私たち、やっと余裕ができたね」って微笑み合えたその日が、きっとその家族にとっての“ちょうどいい日”だったんです。
「◯日以内」は目安であって絶対ではない
昔ながらの風習で「◯日以内に」と聞くと、守らなきゃいけないルールのように感じるかもしれません。
でも実際、神社側も「何日までに来てください」なんて指示してくることはありません。
お宮参りの本質は、“赤ちゃんが無事に生まれてきたことへの感謝”と“これからも健やかに成長しますように”という願いを伝えること。
つまり、「どこで、いつやるか」よりも「どういう気持ちで行うか」が大切なんです。
しきたりって、「昔からの思いやりの形」ではあるけれど、それがプレッシャーになってしまうのなら、今の家族の状況に合わせて柔軟に変えていってもまったく問題ありません。
実際、「うちは半年後だったけど、逆に写真撮るにはちょうどよかった」「遠方の祖父母と予定を合わせるために時期をズラした」という人もたくさんいます。
だから、ちょっとくらい遅れたって大丈夫。
むしろ、“今このタイミングだからできるお宮参り”っていうのが、あなたの家族にはぴったりなのかもしれませんよ。
生後100日を過ぎたお宮参りってアリ?ナシ?
地域や神社によって柔軟な対応が可能
「もう100日過ぎてるし、神社で祈祷してもらえないかも…」と心配になるかもしれません。
でも実際は、多くの神社で柔軟に対応してくれます。
赤ちゃんの行事って、どうしても「時期」にこだわってしまいがち。
でも、今の時代は“気持ちを込めてできるタイミング”で行うことが主流です。
たとえば電話で「生後4か月ですが、お宮参りのご祈祷をお願いできますか?」と聞いてみると、たいてい「大丈夫ですよ~」ってやさしく答えてくれることが多いんです。
中には「もう少し成長されたお子さんのほうが、泣かずに落ち着いてご祈祷を受けてくれるので、ちょうどいいですよ」と言ってくれる神主さんも。
最近では「生後半年過ぎてから行ったよ」という人もめずらしくありません。
なかには1歳の誕生日の記念と一緒にお宮参りをしたというケースもあり、もはや“いつまでに”という線引きはかなりゆるくなってきています。
実際にSNSやママ友の話でも「遅れて行ったけど全然問題なかったよ」「むしろ今でよかった!」という声が多く聞かれます。
焦らなくても大丈夫。
気持ちが整ったとき、家族がそろったとき、それが“うちの正解”でいいんです。
生後4~5か月以降に行く家庭もある
体調の回復を待って、気候がよくなる時期にずらす人も多いです。
特に夏の猛暑や冬の極寒を避けて、春先や秋口に行うお宮参りは赤ちゃんにもママにも優しい選択肢。
気温や湿度がちょうどよく、服装にも悩みにくい季節なので、着物やドレスでの撮影もしやすいのがうれしいポイントです。
「うちは生後6か月だったけど、祖父母も集まれてよかった!」「首がすわってからのほうが安心だった」なんて声もよく聞きます。
なかには、「ベビーカーでの移動が楽だったし、写真も笑顔が撮れて大満足」というママも。
さらに月齢が上がると、赤ちゃんの表情が豊かになっていて、写真映えもバッチリ。
ふにゃふにゃの新生児ももちろんかわいいけど、にっこり笑ってるベビーや、手をにぎにぎしている姿もまた違ったよさがあります。
なにより、赤ちゃんの成長を家族でじっくり感じながら過ごせる時間こそが、いちばんの宝物になるはずです。
遅れてお宮参りをする場合のポイント
赤ちゃんの成長に合った服装を選ぼう
月齢が上がってくると、新生児用の祝い着ではサイズが合わないこともあります。
とくに、生後4~6か月頃になると体も大きくなって動きも活発になってくるため、布地が張ってしまったり抱っこしたときに苦しそうに見えることもあるんです。
もし着物が窮屈そうなら、ベビードレスやフォーマルなロンパースなど、動きやすくて見た目も華やかな衣装がおすすめです。
最近では「お宮参り用ロンパース」なんて名前で、和装っぽいデザインのものも売られていて、手軽さと華やかさを両立できると人気ですよ。
「おくるみで包むにはちょっと大きくなっちゃったな~」と感じたら、無理せず今の赤ちゃんに合うスタイルを選びましょう。
その子の個性や体型、成長具合に合った装いをしてあげることが、赤ちゃんにとっても居心地のよい一日になります。
また、月齢が上がると写真映えもよくなるので、衣装選びを楽しみに変えてしまうのもアリです。
「今日はどんな姿で祝ってあげよう?」と家族みんなでワイワイ相談するのも、きっと思い出になりますよ。
動きが出てくる月齢では、着心地や通気性も大切。
汗をかきやすい子なら、肌着や素材選びにも気を配ると快適に過ごせます。
特に祈祷中は30分ほど静かに抱っこしていることもあるので、通気性のいい素材や調整できる重ね着がおすすめです。
祈祷の可否は神社に事前確認を
神社によっては「お宮参り=生後◯日頃」というしきたりが色濃く残っている場合もあるので、念のため確認を。
また、予約制のところも増えてきているので、「行ける日程が決まったらすぐに電話」がおすすめです。
とくに土日祝は混雑するため、希望の時間帯を確保するには早めの連絡が◎。
時間帯によっては他のご祈祷と重なることもあるので、「静かにゆっくりお参りしたいな」という方は平日や午前中を狙うとよいですよ。
さらに、赤ちゃんの負担を考えて「短時間で済ませられるか」「控室や授乳室があるか」といったことも一緒に聞いておくと安心です。
家族みんなが心地よく過ごせるように、少しの下調べが当日をスムーズにしてくれます。
どうしても行けない時は?代わりの方法もある
お家でのお祝いでも気持ちはしっかり伝わる
「結局バタバタしてて行けなかった…」という場合でも、家族でささやかにお祝いするだけでも十分です。
忙しさや体調の都合で外出できないときこそ、無理に出かけず、自宅で落ち着いてお祝いするという選択が心の余裕にもつながります。
たとえば家の神棚に手を合わせたり、リビングにちょっとした飾りを用意して、赤ちゃんに「生まれてきてくれてありがとう、元気に育ってね」と声をかける。
それだけでも立派なお宮参り。
言葉に出すことで、ママやパパ自身の気持ちも整っていくものです。
さらに、家庭内での食事にひと工夫を加えてみるのもおすすめです。
お赤飯や鯛の塩焼きを用意したり、離乳食期でなければ赤ちゃん用の「お祝いごはん」風プレートを作ってあげるのもいい思い出になりますよ。
「今日がうちのお宮参り記念日」として、家族で写真を撮ったり手形や足形を残すなど、自宅だからこそできる記念のかたちを工夫してみると。
後から見返したときに「あのとき、家族でちゃんと祝ったな」と思える温かな記録になります。
写真だけの記念撮影や神社へのお参りだけでもOK
写真スタジオで記念の写真を撮ったり、神社にお参りだけしに行く“簡易お宮参り”を選ぶ人もたくさんいます。
祈祷なしでも、神社の雰囲気や空気感の中で記念写真を残すだけでも特別感は十分に味わえます。
私の友人は「神社の鳥居前で撮った写真、めっちゃお気に入り!」って言ってました。
赤ちゃんを囲んで家族全員で笑顔の写真を撮ることができたのは、日を選んで無理なく行けたからこそ。
最近では、お宮参り用の衣装レンタル付きフォトプランなども人気で、スタジオ撮影+ロケ撮影を組み合わせるプランも増えています。
プロに頼むのももちろんアリですが、パパやママがスマホで撮った自然な表情の写真が、いちばんのお気に入りになることも。
写真だけでも“家族の気持ち”がきちんと残ります。
あとから見返したときに、「あのときちゃんと祝ってあげられてよかったな」って思えるものになりますよ。
記念日って、“何をしたか”よりも“誰とどんな気持ちで過ごしたか”が大切だったりします。
だから、自分たちらしい形で祝える方法を選んで、それを大切な一日にしてあげてくださいね。
「遅れても祝ってあげたい」その気持ちが大切
赤ちゃんと家族のタイミングで無理なく
大切なのは“心から祝ってあげたい”という気持ち。
赤ちゃんやママの体調が落ち着いて、「みんなで穏やかに迎えられる日」を選べば、それがあなたたち家族にとってのベストなタイミングです。
たとえば、仕事の休みがなかなか合わなかったり、上の子の行事と重なってしまったり、気候が悪くて延期になったり…そんなこと、子育て中の家庭にはよくある話。
「行けるときに、みんなが笑顔で行けること」そのものが、いちばん大切なんだと思います。
記念日って、カレンダーの数字よりも、“その日をどう過ごしたか”が心に残るもの。
だからこそ、自分たちのタイミングでOKなんです。
むしろ、日にちにとらわれず「今日がうちのお宮参り記念日」と決めて、その日を丁寧に過ごすほうが、ずっと記憶に残るかもしれません。
完璧じゃなくていい。
大切なのは気持ち
「ちゃんとしなきゃ」がプレッシャーになるなら、そんなの取っ払っちゃいましょう。
“ちょっと遅れたけど、ちゃんと感謝を伝えられた”っていう経験が、あとからじんわり思い出になって残るはずです。
実際、お宮参りって“こうあるべき”が強すぎると、準備も気持ちも疲れてしまいがち。
そうではなくて、できる範囲で、自分たちらしく、小さくても温かなお祝いができたらそれでじゅうぶんなんですよね。
それに、赤ちゃんはまだ“日付”なんてわかりません。
笑ってくれるか、安心して眠れるか、それがすべて。
抱っこされて、優しく語りかけられて、おめかしして、家族に囲まれて過ごすひととき。
そんな幸せな時間こそが、赤ちゃんにとっては最高のプレゼントです。
肩の力を抜いて、自分たちらしいお祝いができればそれで十分。
ママもパパも、ほんとうにおつかれさまです。
毎日頑張っているあなたにこそ、心から「それでいいんだよ」と伝えたいです。
まとめ
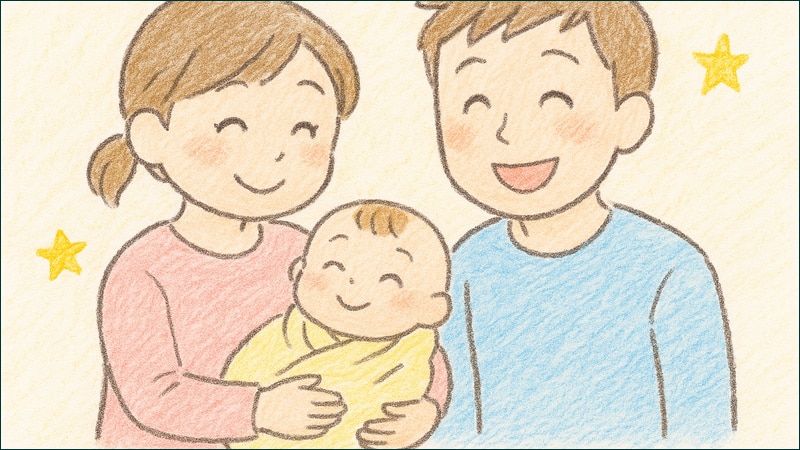
お宮参りが遅れたって、大丈夫。
むしろ「今だからこそ、家族みんなで笑顔でお祝いできる」っていうタイミングだったのかもしれません。
本来のお宮参りの意味は、赤ちゃんが元気に生まれてきてくれたことへの感謝と、これからの健やかな成長を祈る気持ちを伝えること。
だからこそ、日付や形式にこだわりすぎなくても大丈夫なんです。
昔ながらのしきたりにとらわれすぎず、赤ちゃんと家族にとって“無理のない・心地いい”方法を選んであげてください。
たとえ少し時期が遅れても、それを気にする必要はまったくありません。
「今日が私たちの記念日」「このタイミングだからこそ、心をこめて祝える」そんな気持ちでお祝いすれば、その日が特別な思い出として、ずっと心に残るはずです。
何より大切なのは、「祝ってあげたい」という気持ち。
その気持ちこそが、赤ちゃんにとって最高の贈り物になりますように。
無理しない、焦らない、でも大切にしたい。
そんな想いを、どうかあなたの形で叶えてあげてくださいね。
そして、いまこの記事を読んでいるあなたも、すでに十分にがんばっているママ・パパです。
そのあたたかい気持ちと行動力に、どうか自信を持ってくださいね。