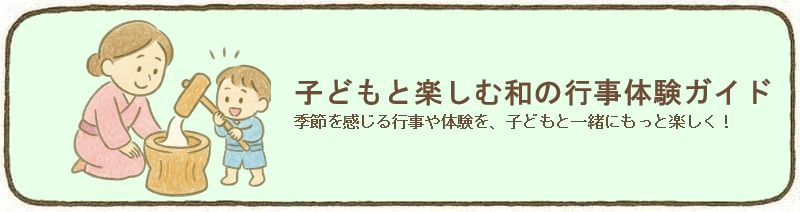子どもの頃、七夕の夜に短冊へ願いごとを書いたあの時間を、ふと思い出すことがあります。
何を願ったのかまでは覚えていないのに、折り紙を切って貼って、
「母と笑いながら笹に飾りつけをしたときの空気」
「夜風に揺れる紙の音」
そして、「お願いごとって叶うかな」と話したあの小さなときめきだけは、今でも心の奥に残っているんです。
親になった今、あのときの母の優しいまなざしや、行事を通して教えてもらった季節のぬくもりの意味が少しずつわかるようになりました。
七夕って、ただ願いごとを書く行事ではなくて、「人が人を想う」という心を伝えていく日なのかもしれません。
忙しい毎日の中でつい忘れてしまう“願うことの美しさ”や、“親子で過ごす時間の尊さ”を、あの小さな笹の葉が思い出させてくれるのです。
子どもと一緒に短冊を書くとき、私は自然と「この子の願いがどうか叶いますように」と祈ってしまいます。
そして同時に、自分の中にも静かに“あの日の子ども心”がよみがえってくるのを感じます。
七夕の行事は、単なる風物詩ではなく、親子の心がふと立ち止まって通い合う、そんなやさしい節目のような存在なんですよね。
七夕ってどんな日?子どもに伝えたい“意味”のこと
織姫と彦星の話だけじゃない、七夕の背景
七夕と聞くと、まず思い浮かぶのが「織姫と彦星が年に一度会える日」というお話ですよね。
子どもにそう伝えると、たいてい「なんでそんなに会えないの?」と目をまるくします。
でもそこから、少しずつ物語をふくらませて話していくと、ただのロマンチックなお話ではなく、努力や約束、そして再会の喜びを感じられる物語であることに気づかされます。
織姫は働き者の女性で、機織りをがんばっていたけれど、彦星と出会ってから遊びに夢中になってしまい、仕事をしなくなったという展開があるんですね。
それを見かねた神様が、1年に一度だけ会えるようにしたというエピソードには、
「日々の努力を大切にすること」
「節度ある行動が信頼につながる」
という大事なメッセージが込められていると感じます。
ただ“会える”というだけじゃなくて、そこにいたるまでの過程があることを、物語として優しく伝えてあげると、子どもたちも自然と物語の深さに引き込まれていきます。
子どもに伝えるなら“想像できる言葉”で
小さな子に七夕の話をするときは、むずかしい言葉を使う必要はありません。
「働くことってどういうことかな?」
「約束を守るって、どんなとき?」
と問いかけながら話すと、自分の経験と結びつけて考えることができます。
うちでは、織姫の話をしたあとに「もし約束を守らなかったらどうなる?」と聞くと、子どもが「そしたら、ちょっと寂しくなるかも」と答えたことがあって、そのひとことに胸を打たれました。
子どもの言葉には、ストレートな感性と優しさがあって、こちらが気づかされることも多いんですよね。
短冊の“願いごと”に込める意味と心
七夕で短冊に願いを書くというのは、ただのお楽しみではありません。
自分の思いを言葉にする、そしてそれを空に向けて届けるという行為には、「今の自分と向き合う」という大切な意味があります。
特に子どもにとっては、自分が何を大切に思っているか、自分が何を叶えたいと思っているのかを考える時間は、心の中に“願う力”を育ててくれるきっかけになります。
うちの子が幼稚園のとき、「パパともっと遊べますように」と書いていた短冊を見て、胸がいっぱいになったのを覚えています。
日々の中では口に出さない気持ちも、短冊には素直に表れていて、それを一緒に読むことで親として大切な何かに気づける瞬間があるんですよね。
“願いごと”は成長の足あとになる
子どもが書いた願いごとは、そのときどきの興味や発達段階を映し出す鏡のような存在です。
たとえば
- 年少の頃には「お菓子がたくさん食べられますように」
- 年中になると「自転車に乗れるようになりますように」
- 年長では「おともだちと仲良くできますように」
こうした変化を残しておくと、後になって振り返ったときに子どもの成長をより深く実感できます。
わたしは、毎年書いた短冊を写真に撮ってアルバムに保存するようにしています。
言葉にした願いを記録しておくことで、「あのとき、こんなふうに願っていたんだな」と、子どもの心の軌跡をたどることができるんですよ。
親子で楽しむ七夕飾りづくり
準備するのは折り紙と、少しの余裕だけでいい
七夕飾りを作ろうと思ったときに、「ちゃんとした笹を用意しないと」「凝った飾りが必要かな」と身構えてしまうことってありませんか?
でも実際にやってみてわかるのは、必要なのは材料よりも「一緒に楽しむ気持ち」だったということなんです。
うちでは、折り紙とハサミとのり、あとは100円ショップで買ったカラー毛糸と安全ピンがあれば十分でした。
子どもは、切ることそのものが楽しいし、貼るのも自由だから「こうしなきゃいけない」っていうルールはまったく要らないんですよね。
ちょっとくらいゆがんでも、紙がくしゃっとなっても、それが“その年らしさ”になって愛おしくなるんです。
まだ小さい子でもできる飾りの工夫
年齢が小さいと、ハサミがうまく使えなかったり、糊が手につくだけで泣いちゃう子もいたりしますよね。
そういうときは、事前にパーツを切っておいて、ペタペタ貼るだけでも立派な参加になりますし、色を選ぶだけでも「自分でやった感」がぐっと高まります。
うちでは、星のシールをたくさん用意しておいて、「この星は誰の願いかな?」なんて話しながら一緒に貼るようにしていたら、子どもがだんだん飾りに愛着を持ち始めたんです。
小さな手でできることに合わせて、ちょっとだけ段取りを工夫するだけで、無理なく楽しい時間に変わっていきますよ。
笹の代わりでも十分楽しめる!家庭での工夫アイデア
本物の笹を手に入れるのって、都会だと意外と難しいんですよね。
うちは去年、使っていない観葉植物に飾りを吊るしました。
ちょっと背の高いパキラの枝に毛糸で結んだだけなんですけど、窓辺に置いて風が吹くたびにゆらゆら揺れて、子どもも大喜びでした。
もし植物がなければ、壁にマスキングテープで笹の形を描いて、そこに飾りを貼るのもおすすめです。
場所を取らずに飾れて、取り外しも簡単なので、おうちの事情に合わせた楽しみ方がきっと見つかるはずです。
飾りをつくる時間は“心を開く時間”でもある
不思議なんですが、何かを一緒に作っているときって、子どもってぽつりぽつりと、ふだんは話さないようなことを話してくれるんですよね。
「◯◯ちゃんとけんかしちゃった」とか、「先生にこれ褒められたんだ」とか。
折り紙を折ったり、のりを使っているあいだの、あの“手は動かして口はゆるむ”時間が、子どもにとっての“心の入り口”になることがあるんだなって思います。
ただの工作の時間が、こんなふうに親子の気持ちを通わせてくれるって、やってみないとわからなかったんですよね。
だからこそ、うまくできなくても、完成しなくてもいいから「一緒に作る」ことそのものに意味があるって、胸を張って言ってあげてほしいなと思います。
短冊に願いを書く時間は、親子のこころをつなぐ時間
まだ字が書けない子には“ことばの通訳”を
子どもがまだ字を書けない時期って、どうしても「親が代筆する」場面が多くなりますよね。
でもその代筆って、ただ字を書くという作業ではなくて、子どもの心の中をそっと覗かせてもらう大切な時間なんだなと、私は感じています。
去年、うちの子が「わたしね、プリンが冷蔵庫からいっぱい出てくるようにしてほしいの」と笑いながら言ってきたんです。
それをそのまま短冊に書いて吊るしたのですが、そのユニークで素直な願いが、私にはたまらなく愛おしく思えて、何度も眺めてしまいました。
子どもの言葉って、飾り気がなくてまっすぐで、今その子がどんな世界を生きているのかがにじみ出るんですよね。
だから、字が書けなくても、気持ちをことばにして、親が「なるほど、それいいね」と受け止めて代筆してあげるだけで、その願いはちゃんと“自分のもの”になるんです。
そうやって、少しずつ「気持ちを言葉にする」練習にもなっていくと思うんです。
書いた願いを一緒に読んで、気持ちを味わってみる
短冊を書いたあとって、つい「はい、できた!」と飾って終わりにしてしまいがちですが、ぜひそのあとで「これ、どんな気持ちで書いたの?」と話す時間をつくってみてほしいんです。
うちでは、願いごとを書いたあとに一緒に読みあいっこして、「へえ、こんなこと思ってたんだね」って話すようにしています。
すると、普段はあまり見えない子どもの感情や考えが、ぽろっと出てきたりするんです。
「もっとママと遊べますように」なんて書かれていた日には、ちょっと胸がチクっとして、でもそれがとてもありがたくて、ギュッと抱きしめたくなったこともあります。
願いごとって、未来への希望でもありながら、“いまの気持ち”そのものでもあるんですよね。
その気持ちを一緒に感じる時間は、親子にとってかけがえのない心の通い道になります。
願いを書くことが“自分を見つめる”力になる
大人になると、願いごとってどこか恥ずかしく感じてしまうことがあります。
でも、子どもはその気持ちに素直で、ストレートに「こうなったらいいな」と夢を描くことができますよね。
だからこそ、その“夢をことばにする”という体験を、大切にしてあげたいんです。
願いを書くという行為は、自分の内側を見つめるきっかけになります。
自分は何を望んでいるのか、何が好きで、何にワクワクするのか。
そういった感覚を短冊に込めることで、自分を大切にする気持ちや、自分の気持ちに気づく力が少しずつ育っていくんですよね。
たとえその願いが叶わなくても、「自分の願いを大事にしてくれる人がいる」と感じられることは、子どもにとって大きな安心感になります。
行事を通して育まれる「祈る力」と「感謝の心」
願うことは“心を育てる力”につながっていく
七夕で願いごとを書くという行為は、ただのイベントごとではなくて、子どもたちの「心を育てる」大切な体験なんだと、私は感じています。
願いごとを書くとき、子どもは自然と「こうなったらいいな」という未来のイメージを思い描きます。
それって、自分の心の中を少しだけ先に伸ばして、未来に希望を託すっていう行動なんですよね。
うちの子が「友だちがいっぱいできますように」と書いた年、ちょうど幼稚園に慣れてきた時期で、人間関係に不安もあったんだと思います。
願いごとの中には、そのときどきの心の揺れがあって、それを素直にことばにできたこと自体が、子どもにとってすごく大きな一歩だったんですよね。
願うというのは、裏を返せば「まだ手に入っていないものを認める」ということで、それは小さな勇気でもあると思うんです。
“目に見えない存在”に気持ちを向けるということ
七夕の夜、子どもと一緒に空を見上げながら「織姫と彦星、会えてるかな?」と話す時間には、特別な静けさがあります。
目には見えないけれど、どこかにいるかもしれない何かに心を向けるって、それだけで豊かな感性が育まれていく気がするんですよね。
神さまでも星でも空でもいい、子どもが「だれかに届けたい」と思って願う気持ちは、自分以外の何かを信じようとする力でもあります。
そしてその想像力こそが、思いやりや共感といった“こころの土台”につながっていくんじゃないかなって思います。
「ありがとう」が自然に生まれる場面になることも
短冊を書き終えて、飾ったあとにふと子どもが「笹って、誰がくれたの?」とか「星にお願いしていいの?」と聞いてくることがあります。
そんなとき、「いろんな人がこの笹を育ててくれたんだよ」「星はみんなを見守ってくれてるかもね」と話すと、子どもは「そっかあ、ありがとうって言おうかな」とつぶやいたりして。
願いを書くという行動の中に、「受け取る」「お願いする」「感謝する」という流れが自然に含まれているんですよね。
誰かにお願いするには、謙虚さや感謝の気持ちが必要で、それがないとただの“欲しい”になってしまう。
でも七夕という行事の中で、子どもはその違いを、頭じゃなくて感覚で学んでいくのだと思います。
行事は“心の習慣”を育てるきっかけになる
一年に一度、同じように短冊を書いて、飾って、空を見上げる。
そんな繰り返しが、子どもにとっては「行事を通して自分を見つめる時間」になっていくんですよね。
願いを込めること、誰かに感謝すること、自分の気持ちに気づくこと。
これって、すべて心の健康やバランスを保つためにとても大事な土台なんです。
私自身、バタバタしていると「もう七夕か、どうしよう」と焦ることもあるけれど、いざ子どもと短冊を書いて飾ってみると、「ああ、やってよかったな」と必ず思うんです。
行事は“義務”じゃなくて、“ちょっと立ち止まるきっかけ”なんですよね。
そのきっかけが、子どもにとっても大人にとっても、心にやさしい習慣になっていくといいなと思っています。
まとめ|七夕を通して親子の絆を深めよう
七夕って、飾りを作ったり短冊を書いたりするだけの行事だと思われがちだけど、実際に子どもと過ごしてみると、それ以上に大切なものがたくさん見えてくるんですよね。
願いごとを言葉にする力、自分の気持ちに気づくこと、そして目に見えないものに心を向けるという想像力。
どれもこれも、机の上のお勉強だけでは育ちにくい、“生きる力の芽”のようなものなんだなと、年々強く感じるようになりました。
完璧な飾りを作る必要なんてありません。
折り紙がちょっと曲がっていても、短冊の字がにじんでいても、それはきっとその子らしさなんです。
むしろ「一緒に作った」「一緒に願った」っていう体験の積み重ねが、あとからじんわり心に残るんですよね。
大人になると、願うことや夢を見ることがちょっと照れくさくなるけれど、子どもはまだ純粋に願える力を持っていて、私たちはその時間にそっと寄り添ってあげることができる。
だからこそ、七夕という行事をただの季節イベントで終わらせるのではなく、親子の心がふっと近づく時間として大切にしていけたら、それだけで十分意味のある一日になると思うんです。
今年も、どうかあなたとお子さんの願いが、空のどこかにちゃんと届きますように。