 子育て
子育て ベビーリトミックはいつから?効果や楽しみ方、年齢別のポイントを親目線で解説
「ベビーリトミックって最近よく聞くけど、どんなことをするの?本当に効果があるの?」と悩むママやパパは多いですよね。私も最初は「まだ早いかな?うちの子に合うのかな?続けられるかな?」と不安でいっぱいでしたし、周りのママ友にも相談したほどです。...
 子育て
子育て  子育て
子育て 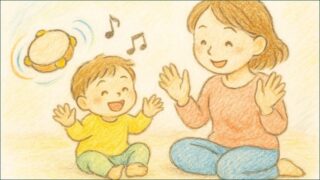 子育て
子育て  子育て
子育て  子育て
子育て  子育て
子育て 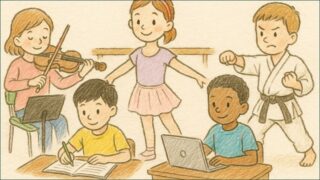 子育て
子育て  子育て
子育て  子育て
子育て  子育て
子育て