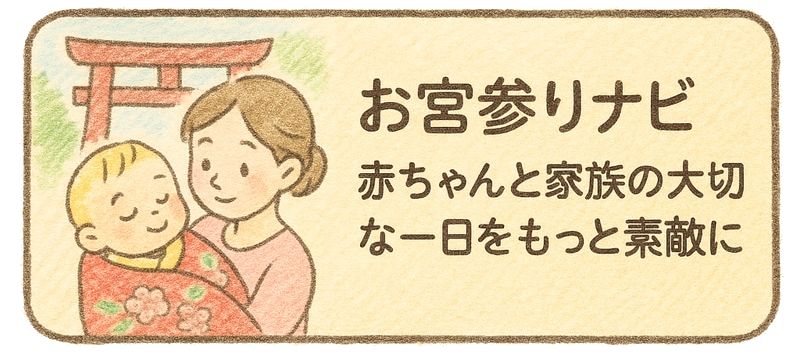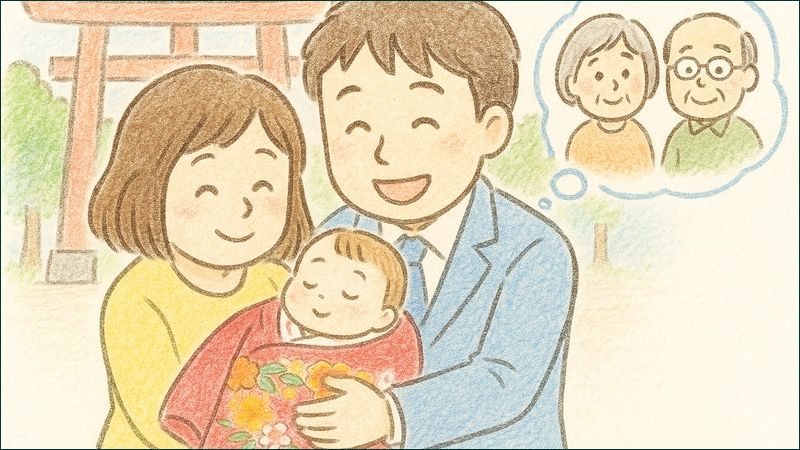
赤ちゃんの誕生を祝う大切な節目
それが「お宮参り」です。
小さな体で力いっぱいこの世に生まれてきてくれた赤ちゃんに、「これから健やかに育ちますように」と願いを込めて神社へお参りに行く。
そんな家族にとっての大切な行事だからこそ、準備にも気合いが入りますよね。
でも実際には、いざ日程を決めようとしたときに
「祖父母が仕事や体調の都合で参加できない」
「遠方に住んでいて難しい」
といった事情が出てくることも。
こちらとしても無理はさせたくないけれど、内心ではちょっと残念な気持ちや不安も出てきてしまいます。
「非常識って思われない?」
「参加してもらえないのは、うちだけなのかな?」
「祖父母にどう伝えたらいいか迷う…」
そんなふうに、心がざわざわしてしまうこともあるかもしれません。
でも、だいじょうぶです。
お宮参りには“こうしなきゃいけない”という絶対的な正解はありません。
大切なのは、赤ちゃんとご家族の気持ちがしっかりとそこにあるかどうか。
この記事では、祖父母が参加できないときでも角が立たず、みんながあたたかい気持ちになれるようなお宮参りの進め方を、やさしく丁寧にご紹介していきます。
「こういうやり方でもいいんだ」「これなら気持ちよく進められそう」そんなヒントがきっと見つかるはずです。
ほんの少しの配慮と、心を込めた言葉があれば、祖父母が来られなくても、ちゃんと素敵な思い出になります。
読んだあとに、少し肩の力が抜けて、「うちのお宮参りも、これでよかったんだな」って思ってもらえたらうれしいです。
お宮参りに祖父母が来られないケースは意外と多い
祖父母が参加できない主な理由とは?
「えっ、来られないの!?」と驚くこともあるかもしれませんが、祖父母が不参加というケースは、実はそこまで珍しいことではありません。
むしろ最近では、“お宮参り=祖父母が絶対参加するもの”という前提自体が、少しずつ変わりつつあるようにも感じます。
たとえば、「体調の問題」これは本当に大きいです。
高齢になると、長時間の外出や、慣れない場所での行事参加はそれだけで体力を使いますし、天候や気温によっては体調を崩すリスクもあります。
特に真夏や真冬のお宮参りでは、「赤ちゃんよりもおじいちゃんおばあちゃんのほうが心配かも…」なんて冗談交じりに言うママの声も。
また、遠方に住んでいることも大きな理由のひとつ。
交通費や宿泊先の手配、移動そのものの負担を考えると、「行きたいけど、今回は見送ろうかな…」という判断になるのも自然な流れです。
そして意外と多いのが、仕事や介護の都合。
「まだ現役で働いているので休みが取れない」
「自分の親の介護があって…」
といった声もあり、「おじいちゃんおばあちゃん=自由に動ける」というイメージが、今ではあまり当てはまらないケースも多いんですよね。
なかには、「自分たちのときは両親が来なかったから、うちもそういうものだと思ってるよ」と、あえて線を引いてくれる祖父母も。
そういうスタンスのご家庭では、口には出さなくても、
「若い夫婦に任せたい」
「必要以上に干渉しないほうがいい」
といった温かい気遣いが含まれていることもあります。
つまり、祖父母が来られないのは“冷たい”とか“無関心”だからではなく、その家庭ごとの背景や気遣い、生活事情があるということ。
そこにちゃんと目を向けてあげると、見えてくるものが変わってくるかもしれません。
参加しなくても非常識ではない
「親を呼ばないなんて…」と気にされる方もいますが、現在では“家族だけのお宮参り”もごく一般的になっています。
行事の形は家庭ごとにちがっていて当たり前。
大切なのは、誰が参加したかよりも、赤ちゃんの健やかな成長を願う“気持ち”です。
無理に日程を合わせようとすると、かえってトラブルのもとになることも。
まずは「参加しない=非常識」ではないという前提を、心の中にしっかり置いておきましょう。
祖父母が不参加の場合の進め方と配慮ポイント
スケジュールの再調整は必要?
一度決めたお宮参りの日程を、「祖父母の予定が合わないから変更しようか」と考えること、ありますよね。
赤ちゃんの誕生を一緒に祝ってほしいという気持ちがある一方で、相手に無理をさせてしまうのではという不安や。
あとは、せっかくの予定をどうしたらいいかという迷いが出てきます。
ただ、基本に立ち返ってみると、赤ちゃんとママの体調を最優先することが何より大切です。
産後は体の回復も完全ではないですし、赤ちゃんもまだまだ外出に慣れていない時期。
特に季節によっては暑さや寒さ、気圧の変化なども影響しますし、無理をすれば風邪をひいてしまうリスクだってあるんです。
「祖父母に合わせて日をずらそう」と気を遣うこともやさしさですが、無理に調整しようとして負担が大きくなるのは避けたいところ。
そんなときは、潔く「今回は家族だけで行く」と割り切る選択も、十分立派な判断です。
その分、写真や手紙で後日気持ちを伝えれば、ちゃんと温かい想いは届きます。
事前に伝えるときの言い方のコツ
もし祖父母に声をかけられなかったとしても、「誘わなかった」と思われるのはちょっと切ないですよね。
だからこそ、事前にやさしく、誠実に伝えることがポイントになります。
「赤ちゃんと私の体調を見ながら予定を立てたから、今回は無理せず家族だけで行くことにしたんだ。
落ち着いたら写真や様子を伝えるから、楽しみにしていてね」
そんな一言だけでも、「大切に思ってくれてるんだな」という気持ちはしっかり届きます。
直接会って伝えるのが難しければ、電話や手紙、LINEでも構いません。
何より大事なのは、言葉のトーンと気遣いの温度。
丁寧に伝えれば、きっと角は立ちません。
遠方の祖父母には「写真共有」や「お守り郵送」で心をつなぐ
当日、赤ちゃんの晴れ姿を写真におさめたら、できればその日のうちに「今お参りしてきたよ」とLINEやメールで送ってあげると、とっても喜ばれます。
また、
- 神社で授かった「お守り」や「絵馬」
- ご祈祷してもらった御札
実際、祖父母から「お守りが届いたとき涙が出たよ」と言ってもらったというママの話もあるくらい。
「会えない=何もできない」ではなくて、「会えなくても心を込めて共有する」ことができれば。
それだけで十分気持ちは通じますし、むしろその配慮がすごくうれしいものなんです。
祖父母に配慮しながら「家族だけのお宮参り」を楽しむ工夫
記念写真や動画で感謝を伝える
当日撮影した家族写真に、ちょっとした手書きのメッセージを添えて送るだけでも、祖父母にとっては本当に宝物のような一枚になります。
赤ちゃんの晴れ着姿やご祈祷後の表情は、どんな高価な贈り物よりも心を動かすもの。
「来てもらえなくて残念だったけど…」という気持ちに引っ張られすぎず、「一緒には過ごせなかったけど、こんなに元気に育ってるよ」と前向きなメッセージを添えてみてください。
さらに、写真だけでなく短い動画を撮って「じいじばあば、ありがとう」と赤ちゃんに語りかけるようなシーンを送るのもおすすめ。
直接会えなくても、声や笑顔が見られるだけで、距離を超えてぬくもりが届きますよ。
帰省時にあらためて御祈願や報告をするのも◎
もし今後、祖父母の家へ帰省するタイミングがあるなら、そのときにあらためて近所の神社に立ち寄ってささやかな御祈願をするのも、すごく素敵な方法です。
正式な儀式でなくても、赤ちゃんを連れて神様に
「無事に生まれました。これからも見守ってください」
そうやって手を合わせる時間があるだけで、その場にいる全員の心があたたまるものです。
そのとき祖父母も一緒なら「私もちゃんとお宮参りできた気がする」と思ってもらえるし、写真を撮ってまた記念を残せば、第二のお宮参りのような一日になります。
プレッシャーを感じすぎないことが大切
「こうしなきゃ」「あれもしなきゃ」と、ついついネットや周囲の声に振り回されてしまうことって、ありますよね。
とくに初めての育児や初孫のお祝いごとは、知らず知らずのうちに気合いが入りすぎてしまうもの。
でも、お宮参りは本来、赤ちゃんが無事に生まれてきてくれたことへの感謝と、これからの成長を祈る、家族のためのあたたかい行事。
豪華な着物を用意したり、有名な神社で祈祷を受けたりしなくても、家族の気持ちがこもっていれば、それが何よりの形なんです。
泣いてしまったって、途中でおむつ替えになったって、パパとママが「いい時間だったね」と感じられたなら、それだけで大成功。
完璧じゃなくても、愛情が伝わるお宮参りになりますように。
焦らず、自分たちらしいかたちで楽しんでくださいね。
祖父母との関係を大切にするために心がけたいこと
「誘ってないと思われたら…」を防ぐには
お宮参りに祖父母を誘わなかったことで、あとから気まずい雰囲気になってしまう…というのは避けたいところ。
特に、普段から連絡を取り合っていない場合や、義理の関係だと「なんとなく話しにくい」と感じてしまうこともありますよね。
でも、そんなときこそ、誤解が生まれないように“先手で伝える”ことが大切です。
「誘いたかったけど、今回はこういう事情があって…」と、赤ちゃんやママの体調を理由に添えながら、丁寧に説明してみましょう。
伝えるタイミングも重要で、できれば日程を決める前後に一言あると、より印象がやわらぎます。
「本当は一緒にお祝いできたらよかったんだけど、今回は無理のない範囲で進めさせてもらったよ」という言い方で、“気持ちはちゃんとあるよ”というのを伝えるのがコツです。
形式にとらわれず、あたたかい気持ちをやさしい言葉で表すだけで、心の行き違いはぐっと減ります。
「孫に会いたい」気持ちへのやさしいフォロー
とくに初孫だったり、久しぶりの赤ちゃんだったりすると、「会いたい」「抱っこしたい」という気持ちは想像以上に強いもの。
でも、だからこそ「今回は無理だったけど、次の機会に絶対会おうね」といった前向きな言葉を添えることで、祖父母の気持ちにやさしく寄り添うことができます。
写真や動画を送るのももちろん効果的ですが、そこに“ひとことメッセージ”を加えるだけで、感情の伝わり方はまったく変わってきます。
「泣きながらお参りしたけど、頑張ったよ
」「じいじばあばにも会わせたかったなぁ」
そんなふうに、赤ちゃん目線やママの気持ちを代弁するような文章を添えると、より気持ちが通じやすくなります。
また、次の予定。たとえば
「今度の連休に顔を見せに行くね」
「お宮参りの話をまた聞いてほしいな」
など、未来に繋がるやり取りがあると、気持ちがやわらぎ、寂しさも癒えていくはずです。
無理に予定を合わせすぎず、思いやりの気持ちを第一に
「どうしてもこの日に来てほしい」と思う気持ちも大事。
でも、その想いが強すぎると、自分たちのペースを乱してしまったり、相手にもプレッシャーをかけてしまうかもしれません。
とくにお宮参りは、産後間もないママや赤ちゃんにとっては思った以上に大変な行事。
無理をして日程を調整して、体調を崩してしまっては元も子もありません。
- 大切なのは、無理をしないこと。
- そして、無理をさせないこと。
その積み重ねが、信頼関係や家族の絆を強くしていきます。
“わたしたち家族らしいお宮参り”を大切にしながらも、祖父母への思いやりや気遣いを忘れない。
そのバランス感覚があれば、たとえ一緒に過ごせなくても、あたたかな一日を分かち合うことはできるはずです。
まとめ|祖父母がいなくても、心を込めたお宮参りに
お宮参りに祖父母が来られないときって、いろんな感情がわいてきますよね。
「寂しいな」
「気まずくならないかな」
「ちゃんとできるのかな」
…そんな不安があって当然です。
誰かと比べて「うちだけ特別?」と感じてしまったり、「どう受け止められるだろう」と周囲の目が気になったりもします。
でも、大丈夫です。
あなたの中に「赤ちゃんをお祝いしたい」「無事に生まれてきてくれてありがとう」というあたたかな気持ちがあるなら、それこそが本当に大切なこと。
どんな形式であっても、その気持ちさえあれば、お宮参りは立派な行事になります。
誰が来るか来ないか、どこでやるか、何を着るか…それよりも、「我が子の健やかな成長を祈る」その想いが、すべてを支えてくれるのです。
そしてその想いは、ちゃんと赤ちゃんにも、そして祖父母にも伝わります。
たとえ一緒にいられなくても、写真や言葉やちょっとしたやりとりの中に、その温度はにじみ出ていくもの。
無理をせず、焦らず、気負いすぎず。
あなたらしいやり方で、赤ちゃんと向き合える時間を大切にしてください。
お宮参りは、形式よりも“心”です。
だからこそ、どうか自信を持って、心のこもった、あなただけの素敵なお宮参りを迎えてくださいね。