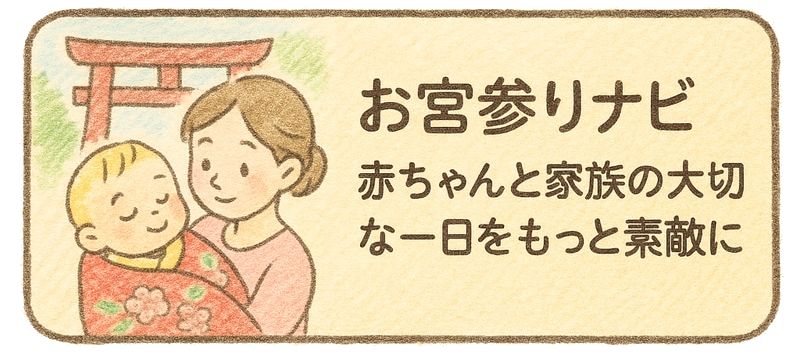お宮参りで赤ちゃんの着物に結びつける「紐銭(ひもぜに)」は、昔から「健やかに育ちますように」「お金に困らない人生を送れますように」といった願いが込められた、日本ならではの大切な風習です。
五円玉を使うことが多く、「ご縁があるように」という意味もあり、地域ごとに使う金額や飾り方、結び方にも特徴があります。
この記事では、紐銭の意味や由来はもちろん、どんな種類があるのか、どう選べばいいのか、購入できる場所や通販情報まで、初めてでも安心して準備できるようにわかりやすくまとめています。
さらに、紐銭の結び方や袋への書き方、男の子と女の子で選び方が違うのかといった細かなポイントにも触れています。
初めてのお宮参りは、赤ちゃんにとっても家族にとっても大切な節目の行事。紐銭の意味を知って、心を込めて準備すれば、思い出に残る素敵な一日になるはずです。
この記事を参考に、赤ちゃんの健やかな成長を願う気持ちを形にしてみてくださいね。
お宮参りの紐銭ってなに?
お宮参りってどんな行事?
お宮参りは、赤ちゃんが生まれて初めて神社にお参りし、元気に育つようにお願いする大切な行事です。
生後30日から100日くらいの間に行われることが多く、パパやママ、おじいちゃんおばあちゃんと一緒にお参りします。
地域や家庭によっては、お宮参りのときにお祓いを受けたり、特別なお供え物を持参したりすることもあります。
また、神社によってはご祈祷をお願いできるところもあり、赤ちゃんの健康や家族の幸福を祈る機会となります。
紐銭ってなに?どんな意味があるの?
紐銭(ひもぜに)は、お宮参りのときに赤ちゃんの産着や祝い着の紐につけるお金のことです。
「将来、お金に困らないように」という願いが込められています。
昔から「お金が赤ちゃんに引き寄せられるように」という意味もあり、紐銭は繁栄や豊かさの象徴とされています。
また、単なるお金ではなく、神社に納めることで神様からのご加護を受けるとも言われています。
そのため、昔の人々は特に縁起の良い金額や形にこだわって準備していたそうです。
どうして紐銭をつけるの?
紐銭には「この子がすくすく育って、お金にも困らず幸せに過ごせますように」という願いが込められています。
地域によっては、お宮参りのときに神社に納めることでご利益があると言われています。
昔から続く日本の大切な風習のひとつですね。
また、紐銭の結び方や使う金額にも意味があり、例えば五円玉を使うのは「ご縁がありますように」という願いが込められているためです。
さらに、家庭によっては紐銭をお守りとして大切に保管し、赤ちゃんが成長した後に特別な日に渡すこともあるそうです。
こうした風習を知ることで、紐銭に込められた願いをより深く感じられるかもしれませんね。
お宮参りの紐銭の種類と地域ごとの違い
地域によって違う!紐銭の風習
お宮参りの紐銭には、地域ごとに違いがあります。
例えば、関東では五円玉を5枚や7枚用意することが多いですが、関西では小判の形をしたお金を使うこともあります。
また、東北地方では親族が赤ちゃんのために金銭を包む風習があったり、九州では独自の飾り紐を用いることもあります。
こうした違いを知ることで、お宮参りの準備がさらに楽しくなりますね。
どんな紐銭がよいか、家族と相談しながら、地域の風習や自分たちの考えに合ったものを選んでみましょう。
男の子と女の子で違う?紐銭の選び方
- 男の子の場合は奇数(3枚・5枚・7枚)
- 女の子の場合は偶数(4枚・6枚)
これは縁起を担ぐための習わしですが、家庭によって考え方はさまざまなので、あまり気にしすぎなくても大丈夫ですよ。
また、近年では五円玉にこだわらず、金色のメダルや特別な記念硬貨を使う人も増えています。
さらに、紐銭を記念として保管し、成人式や結婚式の際に贈るという習慣を取り入れる家庭もあります。
ダイソーでも買える!お手軽な紐銭グッズ
最近では、ダイソーなどの100円ショップでも、お宮参り用の紐銭袋や飾り紐が売られています。
手軽に準備できるので、忙しいパパやママにもおすすめです!
また、手作りにこだわりたい方は、和紙でオリジナルの紐銭袋を作ったり、刺繍で飾りを加えたりするのも素敵なアイデアです。
オンラインショップやハンドメイドマーケットで、オリジナルデザインの紐銭袋を探してみるのもよいでしょう。
お宮参りが終わった後も、思い出として保管できるような紐銭グッズを選ぶのも一つの楽しみですね。
紐銭の購入方法と相場
紐銭っていくらぐらい?
紐銭には五円玉や金色のメダル、小判型の飾り銭などいろいろあります。
お値段は数百円から数千円までさまざま。
地域の風習や家庭の考えに合わせて選ぶといいですね。
一般的には五円玉を複数枚用意することが多いですが、特別な記念硬貨や金箔の入ったものを選ぶ方もいます。
また、紐銭を入れる専用の袋や装飾品も価格に影響を与えるため、セットで購入する場合の総額を考えることも大切です。
ネットで買える!紐銭の通販サイト
Amazonや楽天市場などのオンラインショップでは、紐銭セットや専用の袋が売られています。
口コミをチェックしながら選べば、失敗も少なく安心です。
また、最近ではハンドメイドサイトでもオリジナルの紐銭袋や金箔入りの特別な硬貨を販売していることもあり、個性的なデザインを求める方にはおすすめです。
価格帯も幅広く、手軽なものから高級感のあるものまで選ぶことができます。
お店で買うならどこ?
紐銭は、神社の授与所やベビー用品店、呉服店などでも手に入ります。
お店の人に聞きながら選ぶと、自分にぴったりのものが見つかるかもしれませんね。
特に呉服店では、赤ちゃんの祝い着とセットで購入することができる場合があり、伝統的なデザインを重視する方にはおすすめです。
また、神社の授与所で購入すると、御祈祷されたものが手に入ることもあり、特別な意味を持たせたい場合にはこちらを選ぶのも良いでしょう。
お宮参りの紐銭の書き方・結び方
紐銭に書く言葉って?
紐銭には「寿」や「御祝」といったおめでたい言葉を書くのが一般的です。
ほかにも、「健やかに」「成長祈願」など、赤ちゃんの幸せを願う言葉を添えることもあります。
これらの言葉は、筆ペンや毛筆で丁寧に書くと、より気持ちが伝わります。
筆記用具が苦手な場合は、シールやスタンプを活用してもよいでしょう。
最近では、印刷された紐銭袋も販売されており、手書きに自信がない方でも気軽に準備できます。
紐銭の結び方とその意味
紐銭の結び方には「縁起結び」や「蝶結び」などがあります。
縁起結びはしっかり結ばれるので、「赤ちゃんが健康に育つように」という願いが込められています。
一方、蝶結びは簡単にほどけるため、「何度でもお祝いできるように」という意味があり、出産祝いなどに使われることが多いです。
また、地域によっては独自の結び方があり、例えば関西では「固め結び」と呼ばれる結び方を用いることもあります。
どの結び方を選ぶかは、家族の意向や地域の風習に合わせて決めるのがよいでしょう。
紐銭のつけ方を画像でチェック!
紐銭のつけ方がわからないときは、ネットで画像や動画を探してみましょう。
YouTubeやブログなどにわかりやすく解説されているので、参考になりますよ。
また、最近ではSNSでもお宮参りの体験談が多く投稿されており、実際に紐銭をつけた赤ちゃんの写真やアイデアが共有されています。
手作りの紐銭袋やオリジナルデザインの紐を使用することで、より特別な思い出になるかもしれません。
お宮参りの紐銭には、赤ちゃんの健康と幸せを願う気持ちが込められています。
伝統を大切にしつつ、家族みんなで楽しく準備してみてくださいね!
また、紐銭を記念にとっておき、将来赤ちゃんが成長したときに思い出として振り返るのも素敵なアイデアです。
まとめ

お宮参りの紐銭は、赤ちゃんの健やかな成長や将来の金運を願う日本の伝統的な風習で、地域や家庭によってさまざまな形があります。五円玉に込められた「ご縁」や、結び方に込められた願いなど、一つひとつに意味があるからこそ、丁寧に選びたいものです。
近年では、通販や100円ショップなどでも手軽に購入できるようになり、オリジナルの紐銭グッズを楽しむ人も増えています。結び方や袋の書き方に工夫を加えれば、より思い出に残るお宮参りになるでしょう。
大切なのは、形よりも気持ちです。赤ちゃんを迎える家族のあたたかな願いが込められた紐銭で、幸せな門出を祝ってあげましょう。